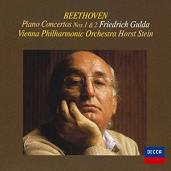ベートーヴェンのコンチェルトと言えば5曲あるピアノ協奏曲、そしてヴァイオリン協奏曲が有名で、私も全て所有しています。ただ、今日ご紹介するピアノ、ヴァイオリン、チェロと管弦楽のための協奏曲、通称三重協奏曲は取り上げられる機会も少ないですね。そもそもコンチェルトと言うのは独奏楽器が1つしかないのが基本。二重協奏曲ならモーツァルト(フルート&ハープ)やブラームス(ヴァイオリン&チェロ)等の例がありますが、三重協奏曲と言うのは調べても他にバッハ(フルート、バイオリン&チェンバロ)ぐらいしか出てきません。理由は簡単で独奏楽器が3つもあったらソロの部分が十分に取れないからです。普通のコンチェルトはオーケストラパートの後に満を持したようにヴァイオリンやピアノが存分に技巧を披露するんですが、3つもあるとそうもいかない。結局、室内楽的なピアノ三重奏になってしまい、そこに無理矢理オーケストラがくっついてるような感じになってしまいます。従ってこの曲もベートーヴェンの失敗作、凡作と言うのが一般的な評価です。

ただし、それでも作曲者はあのベートーヴェン。そこで奏でられる旋律はやはり魅力的です。作曲時期は1804年であの「英雄」と同じ年ですから、30代前半のベートーヴェンらしい活力に溢れています。ゆったりした中に雄大さを感じさせる第1楽章、静謐な美しさの第2楽章、天国的な明るさに包まれた第3楽章。改めてじっくり聴くとやはり素晴らしいとしか言いようがないですね。あのベートーヴェンだから凡作扱いされているだけで、普通に名曲ですよ。CDはソリストがジャック・ルヴィエ(ピアノ)、ジャン=ジャック・カントロフ(バイオリン)、藤原真理(チェロ)、オーケストラ演奏はエマニュエル・クリヴィヌ指揮オランダ室内管弦楽団のものです。この三重協奏曲にはオイストラフ(バイオリン)、ロストロポーヴィチ(チェロ)、リヒテル(ピアノ)の3人がカラヤン指揮ベルリン・フィルと共演した超豪華メンツによるCDもあるので、それに比べると全員小粒ですが、演奏の方はとても素晴らしいですよ。