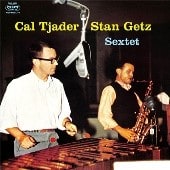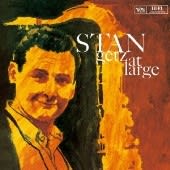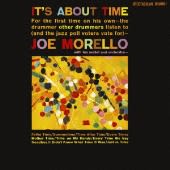ブログ再開後、ひたすら黒人ハードバップを取り上げてきましたが、今日は少し趣向を変えてブルーノートの隠れ名盤「ユタ・ヒップ・ウィズ・ズート・シムズ」を取り上げます。ユタ・ヒップについては、以前にも代表作「ユタ・ヒップ・アット・ザ・ヒッコリー・ハウス」を取り上げました。ドイツ出身の女性ピアニストで、黒人ジャズ主体の同時代のブルーノートではかなり異色の存在でした。本作は「ヒッコリーハウス」の3ヶ月後の1956年7月28日に録音されたもので、タイトル通りテナーのズート・シムズを大々的にフィーチャーしています。残りのメンバーは白人トランペッターのジェリー・ロイド、ベースにアーメッド・アブドゥルマリク、ドラムにエド・シグペンというラインナップです。

内容に入る前に一言。これ、どう考えてもズート・シムズが主役ですよね?ネームバリューももちろんですが、実際にプレイを聴いた感想も同じです。随所に披露するユタ・ヒップのソロも悪くはないですが、目立ち度では完全にズートです。ブルーノートではかの名盤「サムシン・エルス」がコロンビアと契約中のマイルス・デイヴィス名義で発売できないがために、キャノンボール・アダレイを名目上のリーダーにしたというのが有名ですが、本作も実際はズート・シムズが目的なのかもしれません。ただの邪推かもしれませんが・・・(実際ズートのブルーノート録音は本作のみです)
演奏はCD用のボーナストラック2曲を含めて計8曲です。1曲目はズートのオリジナル”Just Blues”。タイトル通りアーシーなナンバーで、のっけからズートが絶好調です。ロイドのソロを挟んで満を持してヒップのソロの出番ですが、1分もしないうちに終了で拍子抜けします。やっぱり完全にズートを聴くアルバムですね。2曲目は本作のハイライトでもある”Violets For Your Furs”。「コートにすみれを」の邦題で知られる名曲で、ジョン・コルトレーンもデビュー作「コルトレーン」で名演を残していますが、個人的にはこちらに軍配を上げます。美しいヒップのイントロに続くズートのテナーに一発でノックアウトされます。どうやったらこんなにふくよかで滋味深い音が出せるのか?まさにテナーによるバラードの極致とでも言うべき名演です。ヒップもここでは長めのソロを取りますが、端正なバラード演奏はなかなか良いです。続く”Down Home”はロイドのオリジナルで軽快なスイング調のナンバー。このロイドと言う人はあまり聞いたことがないですが、オールドスタイルの演奏が持ち味のようですね。残りは”Almost Like Being In Love””Too Close For Comfort””These Foolish Things””’S Wonderful"の歌モノスタンダード4曲に、J・J・ジョンソンの"Wee Dot”。どれも有名な曲ばかりではっきり言ってベタな選曲ですが、そこは絶好調ズートのソロのおかげで水準以上の出来に仕上がっています。リーダーのヒップはと言うと、どちらかと言うと訥々とした語り口のピアノで、絶好調ズートを横目にマイペースにプレーしています。誰がリーダーなのかと言う問題は置いといて、良い作品であることには間違いありません。