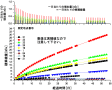5/16までに公開されたデーターを解析したものに更新しました。
--------------------
文部科学省が公開している(http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304002.htm)、簡易線量計(どうやら個人の被ばく線量を計測するために作られたポケット線量計らしい)による、福島第一原子力発電所から30km程度の距離の測定結果のうち、もっとも線量が高い地点(番号32 双葉郡浪江町赤宇木手七郎 福島第一原子力発電所から約30km北西)、2番目に線量が高い地点(番号33 相馬郡飯舘村長泥 福島第一原子力発電所から約30km北西)、連続した測定結果がある地点のうち最も線量が低い地点(番号15 田村市常葉町山根鹿島 福島第一原子力発電所から約35km西)の結果について解析し、今後一年間での被曝線量を予測した。
年間の被ばく線量の予測値は以下のような簡単なモデルによる算出なので、予測値の信頼性は保証できないが参考にはなるのではないかと思います。
放射線の被ばくそのもの関しては専門ではないので、何か間違いを見つけたら、ぜひ指摘してください。
--------------------
*ヨウ素131は核崩壊によってキセノン131に変わる。キセノンは化合物を作らない希ガスなので、核崩壊が起きると気体になって飛んでいってしまう。(=つまり観測地点からなくなる)
*セシウム137は核崩壊でバリウム137に変化する。バリウム137もさらに核崩壊するが、半減期が短いので、セシウム137の寄与が多めに見積もられるという問題はあるが曲線の形状に影響を及ぼさないので無視する。
*核崩壊による放射性物質の減少は指数関数にしたがうので、検出される放射線量もそれに従って減少する。
1つの放射性物質による線量の時間変化は
y = A1*exp(-x/t1)
( http://en.wikipedia.org/wiki/Half-life )
2成分放射性物質が存在する場合には、次のような式であらわされる。
y = A1*exp(-x/t1) + A2*exp(-x/t2) + y0
A1,A2: 最初の放射線量
y0:オフセット(自然放射線による線量)
t1,t2:それぞれの放射性物質の減衰係数
x:経過時間(日)
減衰係数と半減期の関係は次のような式であらわされる。
半減期/ 0.693=減衰係数
減衰係数には、半減期から求めた値をつかった。
ヨウ素131は8.02070 日、セシウム137は30年とした。
*解析はフィッティング解析、つまり、データー点にきちんと合うように、モデル式の変数をパソコンを使って最適化する方法で行った。
--------------------
測定エリア番号32
双葉郡浪江町赤宇木手七郎
(福島第一原子力発電所から30km程度の距離の測定結果のうち、もっとも線量が高い地点)
最初、おもにヨウ素131とセシウム137が出した放射線が計測されていると仮定して、フィッティング解析したが、どうしても、1,2日目の値が低めに出てしまう。そこで、ヨウ素131とセシウム137に加えてもう一つ放射性物質が存在していると仮定して、解析してみたところ。半減期が非常に短い成分があると考えると、測定結果とよく合うことが分かった。調べてみると、ヨウ素の放射性同位体に半減期が13 時間と短いヨウ素123というのがあるということだったので、その半減期を取り入れて解析した。
その結果を次に示す。
(サムネイル画像をクリックするとグラフが表示されます。)
グラフの下側のパネルが、一日当たりの放射線量の時間変化を解析した結果。
赤い点線で示したのが最初の30日のデータをもとにした予測曲線です。
真ん中に示した拡大図をみると予測曲線(赤い線)と実測データー(黒い点)は、ほぼ一致しているので、このモデルによる予測はある程度はあっていると思われる。
放射線量の単位はmSv(ミリシーベルト)にしてあります。
最初の30日のデータをもとにした解析結果によると、最初の放射線量の内訳は、
セシウム137(半減期30年)の寄与0.37 mSv/day
ヨウ素131(半減期約8日)の寄与:0.77 mSv/day
ヨウ素123(半減期約13時間)の寄与:0.73 mSv/day
となり、主成分は確かにヨウ素だが、セシウム137の寄与もあることが分かる。
この曲線を積分して、年間の被ばく線量を予測した結果が、グラフの上側のパネル。
この地点での年間被ばく線量の予測値は、約144mSvとなった。
やはり、この地点では、半減期の長いセシウム137があるために年間被ばく線量はかなり高い値になりそう。局所的に線量の高い場所を立ち入り禁止にするか、表層の土を入れ替えるなど対策が必要。
測定エリア番号33
相馬郡飯舘村長泥
(測定エリアのうち2番目に線量が高い地点)
(サムネイル画像をクリックするとグラフが表示されます。)
最初の30日のデータをもとにした解析結果によると、最初の放射線量の内訳は、
セシウム137(半減期30年)の寄与0.19 mSv/day
ヨウ素131(半減期約8日)の寄与:0.47 mSv/day
ヨウ素123(半減期約13時間)の寄与:0.59mSv/day
となる。33番の地点と同様に主成分は確かにヨウ素だが、セシウム137の寄与もあることが分かる。
この地点での年間被ばく線量の予測値は、78mSv となった。
測定エリア番号15
田村市常葉町山根鹿島
(連続した測定結果がある地点のうち最も線量が低い地点)
(この地点は、今は文部科学省のデーターがないので予測があっているかどうか確認できないのですが、参考のために、そのままおいておきます。)
(サムネイル画像をクリックするとグラフが表示されます。)
途中から測定結果に大きなずれ(値が突然小さくなっている)がある。
線量が低いので、途中まで、線量計に放射性物質を含んだチリが乗っていたりしたのかもしれないが、測定場所の状況や方法が公開されていないので分からない。ひとまず、予測は測定結果がずれる前までのデーターを元にしたものにしておく。
解析結果によると、、最初の放射線量の内訳は、
セシウム137(半減期30年)の寄与0.020 mSv/day
ヨウ素131(半減期約8日)の寄与:0.38mSv/day
ヨウ素123(半減期約13時間)の寄与:0.019mSv/day
となった。
線量が弱いため、データーのふらつきが大きく、予測が適切なのかわからないが、セシウムの寄与が小さいため、この地点での年間被ばく線量は7.9mSv と低い値になった。
まとめ
独立行政法人放射線医学総合研究所の放射線被ばくに関する基礎知識によると、「例えばおよそ100ミリシーベルト未満では、放射線がガンを引き起こすという科学的な証拠はありません。」となっています。これは、つまり、ほかの要因でガンになる人の割合が圧倒的に多いため、統計上、放射線の被曝によるガンの割合が見積もれない、つまり心配しなくて良い(それよりも禁煙でもしたほうが良い)ということです。
解析結果から、32以外の地点では一年間の被ばく線量の予測値は100mSvを超えておらず問題はないようです。ということで、やはり、一部の放射線量が大きい地点以外では心配する必要はなさそうです。
*参考資料
独立行政法人放射線医学総合研究所の放射線被ばくに関する基礎知識 サマリー版
http://www.nirs.go.jp/information/info.php?i13