
より
*****
前川喜平さんロングインタビュー2 「公教育」は国家の繁栄ではなく「一人ひとりの幸せ」のためにある
2020年度から導入される予定の新しい「高等学校学習指導要領」では、18歳選挙権や成人年齢の引き下げに合わせた「主権者教育」が重要なポイントになると言われている。
国民全体の政治への関心が低く……あるいは、関心はあっても「選挙では何も変わらない」という、一種の諦観が広がりつつあるこの国で「大人の入り口」に立つ高校生が、「一人の主権者」としての自覚を持ち、政治を主体的に「自分の問題」として捉えることは、民主主義の未来を支える重要な鍵となるはずだ。前文部科学省事務次官の前川喜平氏が語る、「主権者教育」の意味と重み、そして「公教育」本来の目的とは。

──2020年度から導入される高等学校の新たな学習指導要領では「主権者教育」にも重点が置かれていると言われています。そうした狙いが具体的な学習内容にはどのような形で表れているのでしょうか?
前川 今回の高等学校の学習指導要領の特に社会科系は大幅に変わります。「歴史総合」「地理総合」「公共」というのは、いわば主権者教育3点セットと言っていい。
ここにも、「ロングインタビュー1」でお話しした「政治からの圧力」と、それを逆手に取った文部科学省(以下、文科省)側のホンネという、ある意味相反する側面があって、例えば「歴史総合」は、「日本史を必須にしろ」という政治からの圧力に「わかりました、日本史やります。わかりました、やります」と応えた形をとりながら、実際には世界史と抱き合わせで、しかも、近現代を中心にしています。
そうやって、世界史の中に日本を相対化して見ていく。しかも、近現代で現代につながっているところをきっちり勉強する。16世紀ぐらいからあと、特に18世紀あたりからあとをしっかりと勉強する。産業革命や民主主義革命や、あるいは帝国主義や世界大戦といったものをしっかり学ぶことで、人類がいかにして人権とか平和とか民主主義というものを勝ち取ってきたか、あるいは、まだどこが不十分なのかという視点を持つ大きな助けにもなる。
そういう世界史の中に日本史を学ぶ、しかも今の現代につながっている部分、どうやって現代につながってきているかをしっかりと認識するというのはものすごく大事で、私は「歴史総合」が主権者教育のベースをなすような教科になると思っているんです。
例えば「ワイマール憲法」という当時では世界で最も民主的な憲法の中から、なぜヒトラーのような独裁者が生まれたのか? こういう愚かなことを日本人だって繰り返さないとは限らないよという、そのことを学ぶってものすごく大事だと思うんです。
それから地理もそうですね。日本地理、世界地理じゃなくて、「地理総合」で世界地理の中の日本地理を学ぶということで、例えば地球大の問題、食料問題、エネルギーの問題、気候変動の問題、こういったものを全体として見る視野ができてくる。
そうした歴史や地理に関する、視野の広い理解をベースに「公共」という教科の中で自らその社会を形成していく、社会の形成者としての資質をつくっていくというのは、ものすごく大事だと思っていて、これは本当にうまくこの教科を使っていただければ、本当にいい主権者教育ができるんじゃないかと思っているんですけれど。一方で、政治の側にはそういう「目覚めた主権者」は困ると言う人もいるわけです。
その人たちはむしろ、目覚めさせないような主権者教育がしたいので、いろいろ、あれしちゃいけない、これしちゃいけないという規制をかけるわけですね。それが2015年に文科省が出した通知に表れているんですけれどもね。これは18歳選挙権が施行される前、2015年の10月に、主権者教育に関する通知を出していますけれども、その通知で文科省は何と言っているかというと、いろいろと生徒にも先生にも制限を加えています。
例えば、生徒に対してはまず「学校の中では政治活動をするな」と。それどころか「学校の外」でも学校が規制できると言っているわけです。僕なんかは「ホントかよ?」と思うんですけどね。だって、高校生には基本的人権があって表現の自由も言論の自由もあるわけじゃないですか。
もちろん、学校の中には一応「施設管理権」があるので、ある程度「ここではこういうことをしないこと」というのがあるのは、仕方ないかもしれないけれど。それでも教育の場だっていうことを考えるのであれば、生徒が主体的に考えたことを表現するって、これは最大限に保障するべきですよ。
ほかの生徒の迷惑になるような方法だったら、一定の規制をかけたらいいとは思うけれど、例えば校庭のどこかで「僕はこう思うんだ」っていうような演説をしていたっていいと思うし、ビラを配ったっていいと思う。学校の中での政治活動というのは、むしろ容認どころか、促進してもいいぐらいだと思うんですよね。
ところが、文科省の通知は、まず教育課程内での政治活動はいっさい禁止。つまり、例えば総合的な時間とか、特別活動の時間に「9条改正反対の署名、みんなやってくれ」というようなことを言ったらダメというわけですね。
それどころか、教育課程外であっても学校の中では規制をしなさいと言っています。さらには、学校の外で行う政治活動についても届け出制にして構わないとかね。そうやって非常に過度に高校生の政治活動を制限しようとしている。
もちろん、教員に対しても「自分の政治的見解を言うな」と言っているんですね。それだけじゃなくて「不用意に影響を与えるな」とも言っています。でも「不用意に影響を与える」って何ですか? 例えば、先生が胸に「9」っていうバッジを付けているだけでも不用意な影響を与えることになるのか? これって非常に萎縮効果があると思うんです。
本当はそんなに気にしないで、客観的に「こういう意見がある。こういう意見もある。君たちはどう考えるか、議論しましょう」と。これでいいんですよ。もちろん「こういう意見」の中には必ず、先生自身の意見だってあるはずですし、そもそも、自分の政治的見解も持っていないような教員には主権者教育などできません。
ちなみに、こうした文科省の姿勢に日本弁護士連合会が批判的な意見書を出しています。その意見書を読むと、ドイツのことが書いてあるんだけど、ドイツには「ボイステルバッハ・コンセンサス」というのがあると言うんですね。
この「ボイステルバッハ・コンセンサス」というのは1970年代に、政治教育のあり方について学者が集まって、一定のガイドラインを作ったんですが、そのガイドラインでは、もちろん、教師は自分の政治的見解を述べて良いということになっている。
ただし、自分の見解だけではなくて、それに反対する見解も同様にきちんと説明して、生徒の自主的な判断に委ねることが大事なんですよと。そういう政治教育についてのあり方、考え方というものを当事者の中で議論して決めた。国が決めたんじゃなくてね、学者たちが集まって決めたコンセンサスなんですよね。これ、1976年ですから、もう40年前の話なんですが、このあたりにも、やっぱりドイツと日本の違いを感じます。
──それは二つの国の「戦後の後始末の仕方」の違いに始まっているんでしょうね。
前川 そうそう。つまり害虫の巣を残しちゃった国と、完全に駆除した、あるいは、それを常に駆除し続けなきゃいけないと思っている人たちとの違い。
それだけの痛恨の歴史を持っている国。ワイマール憲法がヒトラーを生み、ヒトラーがホロコーストをしでかして、とんでもない戦争で何千万人もの人を殺したと。そういうとんでもないことを、しかしそれに迎合し支持した国民がいたという……。それだけシビアな歴史観、民主主義観というのが常に彼らの中にはあって、その運用をいかに間違えないかということに対する意識が、常に一定のブレーキというか、必ず考えなければいけないプロセスとして残っているということなんですね。
──18歳選挙権や成人年齢の引き下げに伴って「主権者教育」の重要性を訴える一方で、民主主義の基礎を支える「異なる様々な意見に耳を傾け」「自分で考える」力を身に着けた、前川さんの表現を借りれば「目覚めた主権者」は困る……というのでは、まるで、一人ひとりの主権者を「自分たちに都合のいい一票」としか見ていないように感じます。
前川 最近の「公文書問題」などを見ても象徴的ですが、現実には「民はよらしむべし。知らしむべからず」みたいな社会に戻ろうとしていますよね。とにかく、真実を国民に伝えないようにしようと。その一方で、他国の脅威とか、ヘイトのような国民のネガティブな感情に訴えて、支持を勝ち取ろうという、ポピュリズム的な政治手法です。
基本的に、国民はバカだと思っているんですよ。だませると、最後までだまし通せると思っている。まあ、ここにきて国民も少し「あんまりバカにすんなよ」っていう感じになっていると思いますが、とにかく嘘も100回つけば真実になるみたいな話ですよね。そうやって、「そんなはずないじゃありませんか」と言ったら、「そうか、そんなはずないのか」って思っちゃう。大きな声で断定的に繰り返し言うと、みんなそれを信じちゃうっていう。これはヒトラーの手法ですが、最近の日本でもそれがまかり通ってきた。
僕自身、日本国民はもういっぺん戦争があってとんでもない目に遭わないと目覚めないのではないかという、極めて悲観的な思いに囚われることがときどきあるんですよ。
だけど、そうじゃないはずだと。今のドイツ国民だって、過去の歴史を学んで今の民主主義を守ろうとしているんだから、日本国民だって世界の歴史を学べばいいんだと。日本の歴史だって学ぶものがあるだろうけど、ドイツの歴史も日本人が学べばいいんでね。
ワイマール憲法からヒトラーが生まれてきた過程。全権委任法みたいな、反憲法的法律がまかり通っちゃったっていう。そうやって憲法が憲法の役割を果たさなくなってしまう、立憲主義がないがしろにされていくという過程があったわけですね。
学びの中からそういう視点を得ることで「それ、今、日本で起こっていることじゃない?」っていう気づきにつながる。そうやって過去を学ぶことから現在をちゃんと見ることができるという意味で、高等学校の新しい学習指導要領に盛り込まれた「歴史総合」は非常に大きな意味を持っていると思うんですけどね。
──最後に、公教育とは、そもそも「誰のため」にあるのでしょうか?
前川 私は「一人ひとりの個人が幸せに生きるため」だと思います。公教育というのは、国家の繁栄のためとか、国家を守り抜くためとか、そんなことのためにあるのではなくて、一人ひとりの幸せのためにある。もちろん「幸せである」ためにはまず、平和でなきゃいけないわけで、戦争が起きないようにするということが大事なわけですが、そういう「国民一人ひとりの幸せ」と平和を実現するためには、それを守る政治体制が必要で、それが憲法なんですよね。個人の尊厳というものを守るために国に対して一定の行為を禁じ、あるいは一定の行為を求めるという、そういう枠組みが憲法。
そして、憲法に記された思想良心の自由を侵すなとか、あるいは生存権を守れ、保障しろと。人を平等に扱えとか。そういう個人の、一人ひとりの幸せのために国はあるという考え方の先に、国が教育の機会をちゃんと提供するとか、最低限の生活ができる生活保護を出すとかっていう仕組みが成り立っているのが立憲政治だと思うんです。
自分たちの社会がこういうふうに成り立っている、その究極の目的は一人ひとりが幸せに暮らすことだと憲法13条に書いてある、個人として尊重され、幸福追求権があるっていう、そういう幸せを実現するための仕掛けですよと。ただし、それは自分たちで守っていかないと崩れるよと。そういうことを学ぶ必要があると思うんですね。
私は38年間ずっと「公教育」に携わる公務員として、公教育の行政や仕組みに携わる者としては、そういう考え方でやってきたんだけど、一方で、そうじゃないということを言う人たちがいるわけでね。「教育は国家のための営みである」と。教育というのは、国が人間を国のために教育するということだと。
これは、森有礼(もり・ありのり)はそうだったわけですよ。明治18年(1885年)に内閣制度ができて、伊藤博文が初代の総理大臣になって、そのときの初代文部大臣というのが森有礼という人ですね。
しかし、それ以前の明治になったばかりの頃は違っていた。文部省は明治4年(1871年)からあったけれども、それまでの間の文部省のトップの人は、文部卿といって、明治5年(1872年)に学制発布、それから太政官被仰出書(おおせいだされしょ)というのが出ていますけど。ここに出てくる思想は、国家のための教育じゃないんですよね。むしろ、どちらかというと福沢諭吉の『学問のすすめ』と同じような考え方。
「学問」という言葉は、今はなんか大学や大学の先生の専売特許みたいになっているけど、もともと学問というのは学習とか学びとかという意味で、学問するのは己のためであると。自分がその学問をすることによって、社会で身を立てていく。学問というのは、そのために必要なんだから勉強しなさいというのが『学問のすすめ』の考え方ですが、それと同じことが太政官被仰出書にも書いてあるんですよ。
「おまえら、学問なんかいらないと思っているかもしれないけれども、おまえのためなんだ」と。「勉強すると自分にとっていいことがあるんだぞ」ってね。

──それは、まさに「一人ひとりの幸せ」のための教育ですね。
前川 そうなんです。ところが、明治18年の森有礼のときからガラッと変わっているんです。森有礼は、戦前の国家主義的な教育体制の礎をつくったわけですけれども。小学校令、中学校令、師範学校令、帝国大学令というようなものを矢継ぎ早に制度として整えた。そして、その5年後(明治23年、1890年)には教育勅語が出ているわけですからね。
そうやって戦前の国家主義的教育の礎を築いたのが森有礼で、さらに、当時の山縣有朋内閣の法制局長官だった井上毅(いのうえ・こわし)、明治天皇の先生(御侍講)であった元田永孚(もとだ・ながざね)らが教育勅語を作った。だから、まあ、そういう考え方が戦争のあともしぶとく残っていて、今また、ジワジワと燃え広がりつつある。でも、公教育は「国」のためではなく、一人ひとりの「個人」のためにあるはずです。ひたすら強いものに付き従うのではなく「自分で考える力」を身に着けた「目覚めた主権者」の存在なしに、本当の民主主義などありえないのですから。
*****
 より
より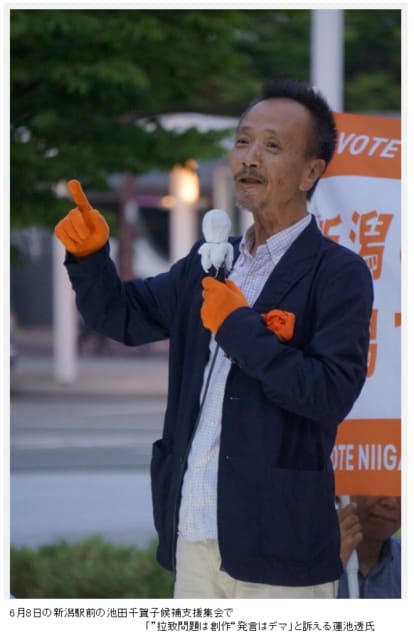











 より
より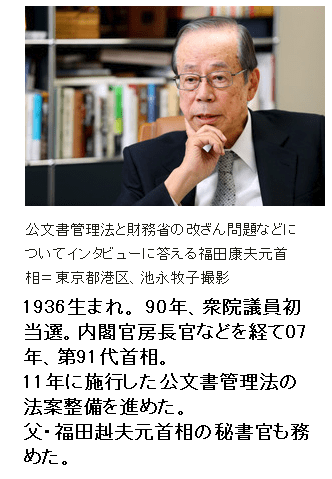 「記録を残す」とはどういうことか。新しい法律ができたとします。それはどんな社会情勢の中で、どんな議論を経てできたのか。国民がその時々の政治や行政を評価するためには、後々まで残る正確な記録が必要になる。それが選挙では投票行動につながり、政治家が選ばれ、政策が決まっていく。正しい情報なくして正しい民主主義は行われない。記録というのは民主主義の原点で、日々刻々と生産され続けるのです。
「記録を残す」とはどういうことか。新しい法律ができたとします。それはどんな社会情勢の中で、どんな議論を経てできたのか。国民がその時々の政治や行政を評価するためには、後々まで残る正確な記録が必要になる。それが選挙では投票行動につながり、政治家が選ばれ、政策が決まっていく。正しい情報なくして正しい民主主義は行われない。記録というのは民主主義の原点で、日々刻々と生産され続けるのです。 より
より

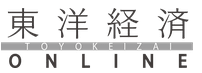 より
より

 より
より










 より
より



 より
より
 より
より

 東の東京大学と並ぶ国立大学の西の雄、京都大学の名物は、自由な校風を象徴するキャンパス周辺の立て看板(タテカン)の数々。ところが5月13日、大学当局は「景観保護条例の順守」を理由に、吉田キャンパス周辺のタテカン撤去に踏み切った。
東の東京大学と並ぶ国立大学の西の雄、京都大学の名物は、自由な校風を象徴するキャンパス周辺の立て看板(タテカン)の数々。ところが5月13日、大学当局は「景観保護条例の順守」を理由に、吉田キャンパス周辺のタテカン撤去に踏み切った。

 高い視聴率を誇る長寿番組『笑点』(日本テレビ)がネットで炎上した。理由は、5月27日放送で安倍首相や政権への風刺、批判的な回答が連発されたためらしい。
高い視聴率を誇る長寿番組『笑点』(日本テレビ)がネットで炎上した。理由は、5月27日放送で安倍首相や政権への風刺、批判的な回答が連発されたためらしい。 より
より
