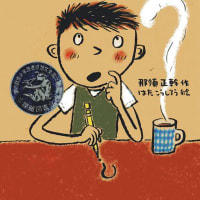ボスニアの少女エミナ
ボスニアの少女エミナ  写真/文 大塚敦子
写真/文 大塚敦子  岩崎書店 いのちのえほん 1500円
岩崎書店 いのちのえほん 1500円  2005年5月 初版
2005年5月 初版 『平和の種をまく』
『平和の種をまく』ボスニア・ヘルツェゴビナには、戦争でばらばらになってしまった民族のちがった人たちが、二度と戦争のおこらないことを祈って、みんなでいっしょに働いている畑があります。
■1945年 ナチスドイツへの抵抗運動による、チトーが中心となって旧ユーゴ連邦が建国される。
■ボスニア スロベニア クロアチア セルビア
マケドニア モンテネグロ 6つの民族 3つの宗教 4つの言語
■1979年 石油ショック 経済が危機に陥る 人々の生活は悪化 民族主義の台頭
■1980年 チトー死去
■1989年 スロベニアとクロアチアが独立を宣言 連邦との間で戦争となる
■1992年 EUの仲介で、独立が承認
■ボスニアも独立するかどうかで、国内で対立。「やらなければやられる」という恐怖心が蔓延。他の民族を排除する「民族浄化」を求めた争いが起きる。
■1995年 国際社会の仲介により、争いは終結 1つの国境にの中に2つの国があるという複雑な形態となる。「ボスニア・ヘルツェゴビナ」
■2000年 アメリカン・フレンズ・サービス・コミッティ」という団体により、「コミュニティ・ガーデン」が設立
 民族のちがう人たちが、安心して交流できる場を創ること
民族のちがう人たちが、安心して交流できる場を創ること 収入が少なく生活の苦しい人びとや、難民や避難民が、野菜を育てることで日々の食料を自給できるようにすること
収入が少なく生活の苦しい人びとや、難民や避難民が、野菜を育てることで日々の食料を自給できるようにすること 戦争で心や体に障害を負った人びとへのワークセラピー
戦争で心や体に障害を負った人びとへのワークセラピー より環境に優しい食料生産の方法を広めること
より環境に優しい食料生産の方法を広めること 「平和の種」があるなら、たくさんいろんなところに蒔きたいものだ。そんなものあるわけないと投げやりになりそうな現代。でも、歴史を振り返ったら、現代以上に残酷な戦争がたくさんあったことだろう。すぐに世界中に情報が行き渡る現代だからこそ、戦争の悲惨さは地球の裏側からでも伝わってくる。人間はそれを種にして、新しい芽を育てることができる。ボスニアなんて、私には一生行くことはできない国。日本の外に行くことすらないのに、今までもこれからも行くことのない国のことについて知ることができる。たくさんの悲惨さを知ることは、たくさんの種を蒔くこと。
「平和の種」があるなら、たくさんいろんなところに蒔きたいものだ。そんなものあるわけないと投げやりになりそうな現代。でも、歴史を振り返ったら、現代以上に残酷な戦争がたくさんあったことだろう。すぐに世界中に情報が行き渡る現代だからこそ、戦争の悲惨さは地球の裏側からでも伝わってくる。人間はそれを種にして、新しい芽を育てることができる。ボスニアなんて、私には一生行くことはできない国。日本の外に行くことすらないのに、今までもこれからも行くことのない国のことについて知ることができる。たくさんの悲惨さを知ることは、たくさんの種を蒔くこと。戦争は破壊すること。種とは自然、育てること。花を育て、野菜を育てる。ここでは、野菜を育てながら、民族を越えてつながろうとしている。まさしく「平和の種」だ。美しい山、草花たち、緑は平和の象徴だ。