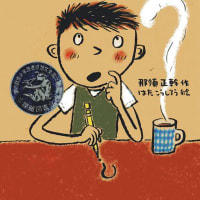松谷みよ子
松谷みよ子 講談社
講談社  1995年8月 初版 1969年作品
1995年8月 初版 1969年作品 『ふたりのイーダ』 2007.7.28
『ふたりのイーダ』 2007.7.28
「イナイ、イナイ、ドコニモ・・・・イナイ・・・。」
直樹とゆう子の兄妹は、おかあさんのいなかの町で、だれかをもとめてコトリ、コトリと歩きまわる小さな木の椅子にであい・・・。
直樹は4年生、ゆう子は2才。ゆう子は、「いーだ」とよく顔をしかめて言うので「イーダちゃん」と呼ばれていた。母が取材で九州に行くことになった。そこで二人は、母の実家の勝浦に預けられることになった。そこで、直樹は雑木林の中で、椅子がコトコト歩いて姿を見つけた。追いかけて行くと、そこには古い家があった。いつの間にかやってきたゆう子が椅子と楽しく遊んでいた。これはどういうことなのか。その家の柱にあった日めくりのカレンダーの数字は「6」・・椅子は、ゆう子のことを「イーダちゃんがもどってきた」と言った。しゃべって動く椅子。ゆう子は、椅子が言う昔死んだ女の子の生まれ変わりなんだろうか。その理由を調べようと仮病を使って留守番をしていたとき、様子を見にきてくれたりつ子さんが、その答えを見つける手伝いをしてくれる。 何年か前に読んだことがある。改めて読んでみて、その奥深さを初めて感じた。以前は、何が言いたいのかわからなかった。読んだのが子どもの頃だったのか、成人して仕方なく読んだのか。いや、途中で読むのをやめたのかもしれない。児童向けだけど、中学生くらいでないと以前の私のように中途半端で終わってしまうかもしれない。
何年か前に読んだことがある。改めて読んでみて、その奥深さを初めて感じた。以前は、何が言いたいのかわからなかった。読んだのが子どもの頃だったのか、成人して仕方なく読んだのか。いや、途中で読むのをやめたのかもしれない。児童向けだけど、中学生くらいでないと以前の私のように中途半端で終わってしまうかもしれない。
動く椅子、話す椅子、それが全然不思議に感じない。今は、物にも心を込めたり、いつもは話さないけど人と同じように見て感じて考えているのではないかと思えるようになったから。それは、物が必ず人の手に触れられるのだとわかるから。どんな物も、必ず人の心がそこにある。手作りの椅子なら尚更かも。それが人を求めて動いたっておかしくはない。
原爆が落とされたとき、きっと多くの人たちがヒロシマに入っていった。肉親や知人を求めて、瓦礫の街と化したヒロシマを歩いた。そしてその人たちの帰りを待っている人たちがうた。「真っ黒なお弁当」では、滋君を捜しにお母さんがヒロシマの町を歩いた。そのお母さんを五日市の町で待っている人たちがいた。同じように椅子は少女を待っていた。ヒロシマでどんなことがあったのか全く知らない椅子。現代を生きる私たちもその椅子と同じかもしれない。事実を知らない、感じていない。本当に心から過去の凄惨な現実に目を向けたとき、あの椅子のように崩れ落ちるかもしれない。今はまだ薄っぺらな感傷にしか浸っていない自分がここにいる。椅子はもうイーダを探すことはないだろうか。崩れた身体を本物のイーダに拾われ、直してもらい、そばに置かれているから。いや、原爆が投下され63年たった今も、椅子は探し続けている気がする。幸せであるはずのイーダを・・子どもたちを・・。