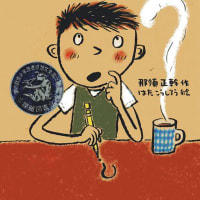■藤沢周平
■藤沢周平
■新潮社文庫 552円 他7編 『祝い人(ほいと)助八』 2007.9.8
『祝い人(ほいと)助八』 2007.9.8 
伊部助八は、御蔵役の仕事についていた。悪妻が病死して、一人で生活していた。そのためか、洗濯していない赤だらけの衣服に、風呂もめったに入らない体から、悪臭は漂い、「ほいと助八」と呼ばれていた。あるとき、親友の妹の波津が助八の家を訪ねてきた。波津は、暴力をふるう夫と離縁し実家に戻っていたのだが、その元夫が家に押し掛けてきたので、かくまってほしいと頼みに来たのだった。しばらくして、波津の実家に行ってみれば、まだその元夫がおり、波津の兄に果たし合いを申し込んでいた。助八は代わりに受けることにし、相手を倒してしまう。そのことがあって、波津からの縁談があったが助八は断ってしまった。
一方城内で殺生をした殿村を倒すよう、家老は、助八に命ずる。殿村は剣客であった。助八は、波津に準備を頼み、そこで自分の家にきてほしいと気持ちを打ち明ける。しかし、すでに波津には別の縁談がすすんでいた。助八は気を取り直して、殿村のいる屋敷に向かい、仕事を終えた。家に帰ると、いないと思って波津が自分を迎えてくれた。
そういえば小さい頃、「ほいとの子」という言い方でからかいあったことがある。何のことかは知らなかった。でも、あまりいい印象はなかった。漢字で書くと「祝い人」だったのか。これだったらいいじゃないか。それにしても武士の世界もいろいろ大変なんだなと思った。派閥争いはあるし、もめごとはあるし、恋もままならぬし、今とちがうのは腕力(武力)がものを言うこと。つまり剣の腕が大事だということ。それもひけらかしてはいけない。自分の力に過信してはいけない。
心の奥底にある切ない恋。はしばしににじみ出る恋心。この時代にはそんな切ない恋が似合っている。自分の感情を表に出してはいけないけど、ちょっとしたしぐさや行いに心を傾ける。それを感じたとき胸に染み渡る。闘い終わって家路につき、待っている波津の姿こそ、まさに切ない心の姿そのもの。 『日和見与次郎』 2007.8.5
『日和見与次郎』 2007.8.5
藤江与次郎は郡奉行下役を勤め、外回りの仕事が多い。今の藩は、財政難でそれに対する案が二派に分かれていた。与次郎は、かつて父が同じような藩の状況のとき、その派閥争いに巻き込まれ、家禄半減などの痛い思いをしていた。そこで与次郎は決して巻き込まれまいと用心していた。従姉の織江の夫の杉浦は、中立な公正な立場であるということから、殿が意見を集めて聞きたいと秘密裏に呼び出しがあった。ある日、杉浦の家が全焼した。畑中派に一派が来ていたことから疑いがもたれた。藩の案が丹波派に決定した。畑中派の杉浦惨殺問題は、証拠不十分として消えてしまった。与次郎は、影の首謀者である淵上にへの復讐を実行する。
大事な役目を負わされたばかりに、ねらわれてしまった杉浦一家は悲惨だ。ここにしっかり警護がつくべきだ。淵上は許し難いけれども、中立の立場を持つ藩にとって大事な役を言い渡した者をみすみす殺されてしまうなんて、殿も不甲斐ない。この恨みはらさでおくべきか、という「仕事人」のような結末であった。しかし、悪事を働いた者が、末端や表面の者だけ処分され、あとは悠々としているのは何とも腹立たしい。与次郎の最後の実行は、つい拍手を送りたくなる。よくぞやってくれたと。織尾が「二人の秘密ね」と言ったとか、復讐は新たな恨みを呼ぶということはないのか不安でもある。 『かが泣き半兵』 2007.7.26
『かが泣き半兵』 2007.7.26
鏑木半兵(かぶらぎはんべい)は、普請組の外回りの仕事をしていた。土木工事の監督などだが、時には石を運ぶなど汗を流すこともあった。ある日、商人町で小さな娘が守屋采女正(もりやうねめのしょう)の一門に折檻されていた。半兵はだまっておれず止めに入った。そのことがきっかけで、仕事の用で寄った長屋にその親子がおり、親密にもてなされた。お家の事情から、半兵は、長屋の一件を理由に守屋暗殺を命じられた。半兵は心極流の使い手だった。
かが泣きとは、愚痴ること、おおげさに自分のことを訴えること。でも、これってだれにでもありそう。むしろ言わない人の方が珍しいと思うけど。私なんか、ほんとちいさなことでも言ってしまう。爪が紫になるほどのけがは大きなこと。「まあ、痛かったでしょう」くらいの慰めがあってもいいじゃないかと思う。武士たるもの、忍の一字ということかな。あの母娘を助けたばかりに、命がけで斬り合いうぃしなければならなくなった。助ける優しさはすばらしい。その母に再び出会う機会があったところから歯車が外れたのだ。心の隙が命取り。半兵が剣の達人で幸いだった。 『だんまり弥助』 2007.7.15
『だんまり弥助』 2007.7.15
パターンは同じだった。性格のちがう主人公。でも、彼は生まれたときからだんまりだったわけではない。いとこの美根のことがあって以来寡黙になったのだ。それにしても、剣の達人というのは、見せびらかすわけでもなく、こうして人からさげすまれながらも、いざというときは思い切った行動に出る。もしかしたら、隠れた正義の味方かもしれない。
だまっていても、気持ちを察する友、妻・・・それはうらやましいことだ。そんな人と出会えたこと。それはもしかしたら、彼の人徳かもしれない。わからない奴は彼を笑う。しかし、人を見る目を持つ者は、彼の力となる。
彼はいざというときはけっこうしゃべることができる。うまく話せないから寡黙になったのではないからだが。ラストの、大橋家老に反対の意見を言ったとき、しどろもどろではなかった。ちゃんと証拠も調べていたし、納得させる話し方だった。ここぞとばかりの時に、行動できるすばらしい力がある。それを見抜いた友、妻だったのかも。 『たそがれ清兵衛』 2007.6.2
『たそがれ清兵衛』 2007.6.2
映画はよかったと思う。でも忘れてしまった。どんな場面に感動したのだろうか。
藤沢周平の作品はいつか読んでみたいと思っていた。でも、短編ばかりで、どうしてこれが映画にできるのだろうかと思議に思っていた。今回の「たそがれ清兵衛」だって50ページ。読んでみてたいして感動はなかった。でもこれが映画になると、最後の戦いの場面も、妻との関わりも、きっと心を動かされるのだろう。
堀を切る役を頼まれたとき、清兵衛の心には妻のことしかなかった。その清兵衛の気持ちを深く感じる描写がない。でも、淡々と物事が進んでいくなかで、清兵衛の気持ちがにじみ出てくる。そこは不思議なものだ。 『うらなり与右衛門』 2007.6.16
『うらなり与右衛門』 2007.6.16
大きな感動があるわけじゃないけど、「ほーっ、そうなんだ」と小さな感嘆の声をあげてしまう。どの時代も謀略はある。でも、正義もある。そして、正義がきっと感嘆の声を作る。与右衛門がわなにはまり、そしてわなにはめた伊黒伴十郎が、与右衛門にやられてしまう。大ぴらな敵討ちではなく、彼から刀をぬかした。まるで闇の仕置き人のような、いやだれにも彼にもわからぬようなまるで罰が下るような感覚。彼も敵討ちされているなど夢にも思っていないだろう。与右衛門の心の内はわからぬが、どの時代も正義が通るすがすがしさだ。 『ごますり甚内』 2007.6.23
『ごますり甚内』 2007.6.23
けっこうおもしろく読んでいる。淡々と物語が進んでいくところがいい。あまりぱっとしない主人公。でも剣の達人。ごますりもへつらうようなあさましい感じではなく、必死に何かを求めてやっているところがけっこう好感をもてる。そして、妻思いであり正義の味方。今まで読んだ二編も同じようなキャラで、同じような展開だった。剣の達人であるのに、一見そうは見えないところがいい。使いの帰りに三人の敵と戦う場面や、城内の廊下で栗田の首を短剣で刺す場面。イメージだけで迫力を感じる。映像でみせるにはどうしたらいいだろうかと、監督になったように考えてしまった。
こうして見てくると、武士の世界も大変なんだな思った。五十五石って、今のお金に換算するとどれくらいなんだろうか。何人か人も雇わなければいけないだろうしね。
ごますりは、けっこう人のために何かをしていることだし、人の心を思っていい気分にさせてくれる。言葉はよくないけど、続けてもいいんじゃないかな。私ももう少しこういうことができるようにならなければと思った。ごますりはエネルギーのいることだからね。 『ど忘れ万六』 2007.6.30
『ど忘れ万六』 2007.6.30
さまざまな人間がいる。でも、「ど忘れ」は年を感じさせる悲しいさがり。ほのぼとしているようで、実は本人はつらい。思い出せないことほどストレスがたまることはない。まあ、自分の子どもの名前が言えなくなったら、悲しいどころではないが。確かに年を重ねるごとにひどくなっていく。ついさっき読んだ本の主人公の名前が出てこない。
万六もまた剣の達人であった。さまざまな人間がいるけど、こうした武士として一芸が窮地を救う。しかも、それをひけらかすわけでなく、地道に鍛え求めてきた技だからこそ、いざというときに役に立つ。万六の、一喝したあとの嫁との食事風景が物語る。やってやったのにという押しつけがないところが、またいつもの日常にもどったことが一番の幸せなんだと語っている。