この一年(令和4年)の支部活動を振り返って
◆曲梶支部所属の俳句の文化功労者、
宇多喜代子先生が「ザ・テルミー」(2022年、秋季号)に掲載されました。

ご著書にサインをされる宇多先生(イトオテルミー曲梶療術所にて)

以下は、宇多先生の著書の一部の紹介です。
・「ひとたばの手紙から」(随筆)
・「宇多喜代子句集」(現代俳句文庫ー2)(古本でしか手に入りません、高価になっています。)
真二つに 折れて息する 秋の蛇
・「象 句集」(発行所 ふらんす堂)第35回 飯田 蛇笏賞受賞)
八月の窓の辺にまた象が来る
・「暦と暮らす」(NHK俳句 NHK出版)(随筆)
・「俳句と歩く」 (角川 俳句ライブラリー)(随筆)
◆令和4年は、他支部講習会に参加できました。
この数年間は、コロナ禍で講習会が自粛されていました。本年はたくさんの支部が講習会を開催しました。
支部長は、4月から11月まで4つの支部の講習会に参加しました。
☆酒井宏美支部 講習会(酒井支部 発会式)

講 師 王 若皎 先生
開催日 令和4年5月8日
テーマ 「医療現場からみた免疫力とは」
※講演の中で、王先生は「コロナの症状」についても説明していただきました。
最近では、コロナの後遺症の治療も大きな問題となっています。
☆高濱支部
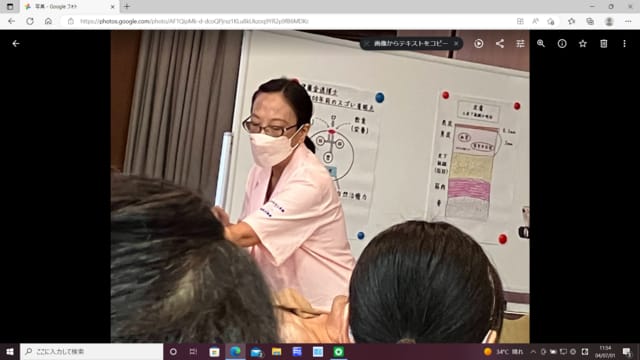
講 師 枇杷友 美樹 先生
開催日 令和4年6月26日
テーマ 「テルミーでセルフケア」~夏の不調を乗り切るために~
◆「治療」は「愛」であり「祈り」である(イトオテルミー創見者 伊藤金逸博士 語録より)
「医宗一如(光)」(伊藤金逸博士が遺した理念)
☆京阪ひまわり支部講習会(ひまわり支部発会式)

講 師 的場 直人 先生
開催日 令和4年11月3日
テーマ 大切なひとに「ナデクリャ治る」のテルミーを伝えたい
☆楠野 侈圭光支部
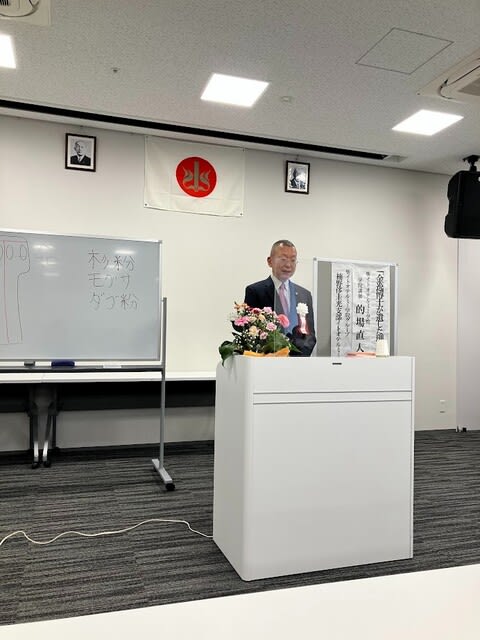
講 師 的場 直人 先生
開催日 令和4年11月13日
テーマ 「 金逸博士が遺した理念と手技」
◆11月は二度にわたり的場直人先生の講習を受けました。2回とも伊藤金逸博士の教えを聞かしていただき、感動しています。
◆近畿支部長会 講演会
講 師 松尾 征一郎 医師
開催日 令和4年9月18日(日)
テーマ 「心臓を守る日常生活」
◆学院生講習の始めと卒業
学院生でもテルミーの普及に貢献できる!
昨年の12月より学院生になり、研修に励んできた一人が支部での講習単位を修得し、卒業試験に臨むことになりました。来年の1月にもう一人が卒業の予定です。基本実技の習得、レポート提出、中間考査等をこなして、卒業となります。(支部内の研修です。)
聖イトオテルミー学院での卒業試験を経て、指導師資格(療術師)の習得となります。12月に卒業単位を修得した学院生は、すでに保有会員を10名近く持っています。すでに、テルミーの普及に貢献しています。学院生の「人が健康になってほしい。」という願いが実現しています。
他に数名が学院生として、資格習得に精進しています。願うのは「テルミー道」の習得です。
「テルミーは愛である」(伊藤金逸博士)
◆毎月の支部研修会で、各指導師、学院生、一般会員が「テルミー体験」を発表することによって、テルミーの素晴らしさを体験しています。
そのテルミー体験の感動を「曲梶支部講演会」(講師 西河潤医師)で発表してもらう予定になっています。詳しくは、後日、ブログに掲載します。

















