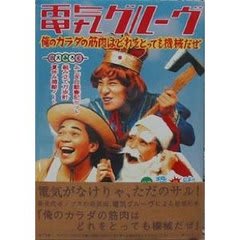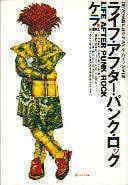久々に記事と記事の間が1ヶ月くらい開いた.
そりゃそうだ.
1月いっぱい,相当な繁忙期.
量産化に向けて図面描いたり大変な時期だった.
でも何とか量産に辿り着いた.
これから数ヶ月はゆっくりできそうなので,
備蓄の数ヶ月にしよう.
本日も19時半前には会社を出てる.
帰って来たら20時過ぎで,夕飯作って
食べてテレビをオンエアで観られる…
こんな生活が普通なのか…非常にうらやましい…。。。
日付が変わるのが普通の生活が1年半くらい続いたので,
このペースが非常に嬉しい.
今も,グループ魂の「だだだ」をヘビーローテーション
しながら,平日にブログなんぞ書けてるじゃないか.
しかし,この生活も春までだ.
次の担当業務がペンディングになって,
「お,異動のチャンスか?」
なんて思いきや,俊足で2012年と2013年発売の
商品の担当であることを部長から伝えられた.
谷がねえなあ~…。。。
てことで,そんな頭をリラックスさせてくれるのが,
「こどもの発想。」 天久聖一 著 (アスペクト)
http://bakadrill.heteml.jp/pc/2011/01/post-27.html
爆笑!!
本を読んでここまで爆笑できるものは非常に少ない.
コロコロコミック(小学館)に,かつて連載され,小学生たちに絶大な人気と
異様な支持を得た「コロコロバカデミー」が一冊の本になったものだ.
「百点以上の0点を取ろう!」というテーマのもとに始められたこのコーナーには
「まちがえて答えましょう」という伝説的な設問のもと,
小学生たちの天才的なひらめきに満ちた作品に溢れており,
この本の密度たるや凄まじく,頭がクラクラしてくる面白さだ.
問題「小説家・夏目漱石の代表作をひとつ、まちがえて答えなさい」
解答「原始人と再会」「ハゲだらけの町」「かめ200円」…
問題「”シンデレラ”がお城に忘れて来たものは何ですか?まちがえて答えなさい」
解答「わらじ」「はなくそコレクション」「汚れた体操服」「電話番号と住所の書いた紙」…
この天才的な解答を見て震えたw
小学生の自由な発想は芸人の「ボケましょう」的な大喜利を
遥かに越えた素敵なサムシングがある.
問題「(織田信長の肖像画に対して)右の人物にあなたの考えたニックネームを付けなさい」
解答「あけちみつひでに殺されたバカ」
100点!!スバラシイ!!
この本はオススメ!
そりゃそうだ.
1月いっぱい,相当な繁忙期.
量産化に向けて図面描いたり大変な時期だった.
でも何とか量産に辿り着いた.
これから数ヶ月はゆっくりできそうなので,
備蓄の数ヶ月にしよう.
本日も19時半前には会社を出てる.
帰って来たら20時過ぎで,夕飯作って
食べてテレビをオンエアで観られる…
こんな生活が普通なのか…非常にうらやましい…。。。
日付が変わるのが普通の生活が1年半くらい続いたので,
このペースが非常に嬉しい.
今も,グループ魂の「だだだ」をヘビーローテーション
しながら,平日にブログなんぞ書けてるじゃないか.
しかし,この生活も春までだ.
次の担当業務がペンディングになって,
「お,異動のチャンスか?」
なんて思いきや,俊足で2012年と2013年発売の
商品の担当であることを部長から伝えられた.
谷がねえなあ~…。。。
てことで,そんな頭をリラックスさせてくれるのが,
「こどもの発想。」 天久聖一 著 (アスペクト)
http://bakadrill.heteml.jp/pc/2011/01/post-27.html
爆笑!!
本を読んでここまで爆笑できるものは非常に少ない.
コロコロコミック(小学館)に,かつて連載され,小学生たちに絶大な人気と
異様な支持を得た「コロコロバカデミー」が一冊の本になったものだ.
「百点以上の0点を取ろう!」というテーマのもとに始められたこのコーナーには
「まちがえて答えましょう」という伝説的な設問のもと,
小学生たちの天才的なひらめきに満ちた作品に溢れており,
この本の密度たるや凄まじく,頭がクラクラしてくる面白さだ.
問題「小説家・夏目漱石の代表作をひとつ、まちがえて答えなさい」
解答「原始人と再会」「ハゲだらけの町」「かめ200円」…
問題「”シンデレラ”がお城に忘れて来たものは何ですか?まちがえて答えなさい」
解答「わらじ」「はなくそコレクション」「汚れた体操服」「電話番号と住所の書いた紙」…
この天才的な解答を見て震えたw
小学生の自由な発想は芸人の「ボケましょう」的な大喜利を
遥かに越えた素敵なサムシングがある.
問題「(織田信長の肖像画に対して)右の人物にあなたの考えたニックネームを付けなさい」
解答「あけちみつひでに殺されたバカ」
100点!!スバラシイ!!
この本はオススメ!