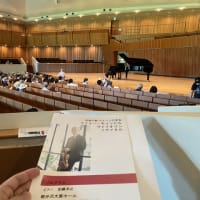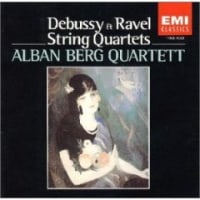今は外国人ポスドクなのであまり意識しませんでしたが、以前は結構考えたことが話題になっている記事があり、これを読んで自分の中で結論が出た気がします。 「なぜ上司は解決策を出したがるのか?」です。
私は研究者ですが、同じような状況をどちらの立場でも沢山経験しています。私の過去の上司は100%解決策を出さなければいけないという姿勢でした。現実的なディスカッションでなかったとしてもです。そして私が大学院生を相手にディスカッションするときは、希に自分に自信がある場合には確かに解決策を出そうとします。実験科学ではそれが明確に正解だと示される場合があり、それは研究者としてはとても痛快なことです。
しかしその話題に自信を持てない場合もあります。不用意な案を出してしまえばその大学院生はそれに従って多大な労力の無駄を強いられてしまうかもしれません。私の場合まだ年齢がそんなに離れていないのでそもそもディスカッションは友達モードですが、こういう場合は完全に対等な立場で意見を出すようにしています。責任逃れとも取れるのですが、結局実験科学は上手くいっても失敗してもやった本人が一番責任をとるので本人が自主的にやらなければ意味がないと思えるからです。私にとっては、ディスカッションを通じて本人がいい解決策を見つけて、次の実験をうきうきしながらやってくれるようなときが最高です。つまり私の理想は変な言い方をすれば、上司としての解決策を出さなくて済むことですね。
多くの場合、私はそこまで自信が無いので後者の場合がほとんどですが、問題は大ボスが納得しないことで、もっとしっかり指導しろとお叱りを受けることもあります。難しいです。
そして今、留学してみるとこちらでは相手がたとえ歳の離れた超有名科学者であってもファーストネームで呼び合いますし、ディスカッションは基本的に対等です。論文をまだ一報も出していないような大学院生がとんでもなく生意気に意見を主張していたりします。ディスカッションは論理的でそもそも日本で言うような上下関係は存在しないように思えるので、今回の議論の対象にすらならないかもしれません。
私は研究者ですが、同じような状況をどちらの立場でも沢山経験しています。私の過去の上司は100%解決策を出さなければいけないという姿勢でした。現実的なディスカッションでなかったとしてもです。そして私が大学院生を相手にディスカッションするときは、希に自分に自信がある場合には確かに解決策を出そうとします。実験科学ではそれが明確に正解だと示される場合があり、それは研究者としてはとても痛快なことです。
しかしその話題に自信を持てない場合もあります。不用意な案を出してしまえばその大学院生はそれに従って多大な労力の無駄を強いられてしまうかもしれません。私の場合まだ年齢がそんなに離れていないのでそもそもディスカッションは友達モードですが、こういう場合は完全に対等な立場で意見を出すようにしています。責任逃れとも取れるのですが、結局実験科学は上手くいっても失敗してもやった本人が一番責任をとるので本人が自主的にやらなければ意味がないと思えるからです。私にとっては、ディスカッションを通じて本人がいい解決策を見つけて、次の実験をうきうきしながらやってくれるようなときが最高です。つまり私の理想は変な言い方をすれば、上司としての解決策を出さなくて済むことですね。
多くの場合、私はそこまで自信が無いので後者の場合がほとんどですが、問題は大ボスが納得しないことで、もっとしっかり指導しろとお叱りを受けることもあります。難しいです。
そして今、留学してみるとこちらでは相手がたとえ歳の離れた超有名科学者であってもファーストネームで呼び合いますし、ディスカッションは基本的に対等です。論文をまだ一報も出していないような大学院生がとんでもなく生意気に意見を主張していたりします。ディスカッションは論理的でそもそも日本で言うような上下関係は存在しないように思えるので、今回の議論の対象にすらならないかもしれません。