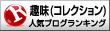<将棋マニュアル(講師用)>
脳科学応用した講師用将棋マニュアルは将棋仲間からのアドバイスを頂きながら完成できました。
※今回は、今迄の市販本の分析には述べられていない部分をとりあげて掲載します。
将棋の基本原理は、「数、多ければ勝つ」です。
しかし、この他に習うのが「位」「捌き」「寄せは速度」があります。
この基本原理との結びつきが有段者でも理解しがたい面があります。
講師用マニュアルの作成にあたり発想転換を試み独自の表を作成しました。
☟エクセルで関連性を一覧表にしたのですが、文字が小さいので捕捉します。

<位>
「位」は分かりにくいのですが、二枚落ち定跡の二歩突っ切りが理解し易いようです。
- 並べた状態から歩を1手突き出すと「位」が確保されます。
- このくらいは駒組を有利に進めたり、戦いの拠点になります。
- 特に、4四、6六など盤面にある星(黒丸)の位は重要になります。指し手に行き詰まったらこの星のを眺めると、糸口が見えることが多々あります。
「位」は物理の位置エネルギーと類似性があり、何もしていないように見えても「位」そのものに位置の持つエネルギーがあると考えることが出来ます。
☟二枚落ちで下手の4五歩の位とりを嫌う場合に上手が用いる乱戦模様の指し方です。(この金上がりに対応できますと二枚落ちは卒業です)

☝この定跡が4五の位の重要性を暗示しています。
また、4四(6六)の地点が急所になる例として矢倉崩し定跡が理解し易いです。
<捌き>
抽象的な説明が多いようです。
- 捌きには駒の交換を伴うことが多いと考察されます。
- 駒の交換は駒の損得を考えながら行います。(数の原理)
- 駒交換の最大の特徴は、交換した駒が「駒台」にのることです。
- 盤上の駒は動かし方のルールに従った以外の「指し手」は出来ないのです。
- 駒台の駒(持ち駒という)は、禁じ手以外は何処にでも「打つ」ことが出来ます。
- 捌きで交換した駒は、その駒の価値以外に自由に移動できる「ワープ能力」を付加価値として得たと考える事が出来ます。
- この自由に移動できる「付加価値」を得たことを最大限に活用した方が優勢になると考えることが出来ます。
- 蛇足ながら盤上の駒を動かす場合は「指す」といい、駒台の持ち駒は「打つ」と言います。
<寄せは速度>
将棋の勝敗は「先に詰ませた方が勝ち」であり、勝敗には時間要素が存在すると理解できます。
- 序盤および中盤までは「数」が概ね支配しています。
- しかし、勝敗は速度で決まりますので、途中で詰ませるために必要な駒の価値と「速度との等価交換」が行われると考えることが出来ます。
- 詰みに至るまでの工程を「寄せ」といい、最も早い寄せの構想に必要な駒を駒の損得を度外視して速度との等価交換で確保します。
- 速度は単位が(m/s)ですので単位当たりの移動量になります。将棋の移動量は交互に1回で1手ですので、詰ます迄の手数が速度と考えることが出来ます。
<80期名人戦から>web記事から転用
「駒得は裏切らない」。多くの棋士が支持する森下卓九段の名言だが、今期の渡辺はその逆を行き、駒を損する間に優位を築く指し回しで、たびたび控室の棋士を驚かせた。
第1局では、あえて香車を相手に与える代わりに攻撃態勢を築いて快勝。第4局でも同様に香車を取らせ、大駒の飛車まで取られる間に自玉を捕まりにくい中段に逃がした。実戦例のない形だったが、渡辺にとっては「この形ならこう指すものという認識」と、独自の“定跡”の範囲だった。第5局の対局前日、斎藤は「第4局は局面を誘導しているつもりでいたが、その先も名人の研究範囲だった」と嘆息していた。
※現在の将棋は、寄せだけでなく序盤・中盤から「等価交換手法」を用いている様に思える記事内容です。渡辺名人の新しい感覚はAI応用の研究から生じたのではと推測されます。
今から藤井5冠と渡辺名人との対局実現が楽しみです。
<追記>
講師用マニュアルは、「心得編」と「技術編」分けて作成しました。
心得編の抜粋(参考文献:横峯吉文氏の語録)
- 小学生を対象とした脳科学応用の将棋指導者の心得をまとめたものである。
- 「天が子供に与えた才能を引き出し、育むのが指導者の役目」と心得ること。
- 子供に共通する4つのスイッチ(特徴)を理解し、これを実践する。
A: 競争が好き
B: 真似をする
C: 難しいことは嫌いで、簡単だと飽きる
D: 認めて貰いたい親からも他人からも(特に子供は渇望している事を理解する)。
A: 生存競争に勝つための本能的なものと理解される。
B: 真似る⇒まねぶ⇒学ぶと派生する。好奇心から成長意欲へと繋がる(繋げる手助け)。
C: 少しだけ難しいことの積み重ねから成功体験の積み重ねへとつなげる。
D: 最も重要な要素と理解される。(大人も同様だと感じている)
- 出来ることは楽しい、楽しいことは自ら練習する。練習すると更に上達するこの連鎖反応が大切である。(ドーパミンの増加、脳が心地よく感じる)
- 子供には「多くを教えてはならない」最小限度のことで気付きを引き出すことを心掛ける。
※全ての分野の講師に要求される重要な要素は、「あの」「えー」などの無駄な「癖言葉」を入れないで話せる様に心掛けて訓練をすることである。