
11月の初めに、ほぼ大分をぐるりと周る旅をした。
2016年以来だから、7年ぶりになる。
その中で、印象に残った「歴タビ」をいくつか、まとめておきたい。

(大分駅前の宗麟公)
本日は大友宗麟(義鎮ヨシシゲ 1530-1587)。
大友氏のルーツは鎌倉時代にまでさかのぼる。
初代・能直(ヨシナオ)は、我が相模(神奈川)の出身、
鎌倉幕府の御家人で、豊後の守護に任じられたのが始まりだ。
大友氏は、その後、400年22代にわたり豊後を治める。
名門中の名門なのだ。
宗麟は、その第21代当主であり、
最盛期には豊後だけでなく6カ国を支配した。

(大分駅前で見つけたタクシーにも宗麟公♫)
宣教師ルイス・フロイス(1532-1597)は、
宗麟を「Bungo(豊後)王」と呼び、
「日本の戦国大名の中で、もっとも考え深く、人徳があり、
あらゆる才能に優れている」と、ヨーロッパのイエズス会に報告している。
フロイスは、宗麟のお膝元・府内(大分)で活動し、
その姿を間近に見ていただけに、かなり的確な人物評のはずだ。
キリスト教を保護し、南蛮貿易を積極的に行う「豊後王」、
それが宗麟のイメージとして定着したのも、ここからだろう。
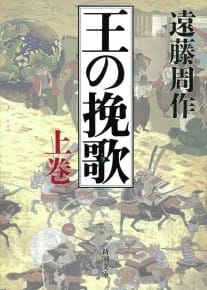
けれど・・・
遠藤周作『王の挽歌』(新潮文庫)は、
「豊後王」の意外な一面を丹念に描く。
その中での宗麟は芸術への造詣が深く、
武人と言うよりは文人気質であり、
一生を通じ、「屋形」として生きる自分を問い続ける。
身内も家臣も誰も信じられない。
やがて宣教師フランシスコ・ザビエルとの邂逅に光を見いだす。
戦乱の世を生き抜きつつ、
最晩年は切支丹として安らかに人生を終えた人だった。
もちろん『王の挽歌』は歴史書ではないが、
わたしも歴史は素人、
フィクションであれ、歴史を身近に感じられれば、それでよい。
何より、宗麟が切支丹保護をしたことが、
領国経営を困難にした、そのすさまじさ!
これを知ったことは大きかった。
てっきり肥前の有馬家のように、平和な切支丹の土地かと思っていた。
(有馬家だっていろいろあっただろうけれど)

(宮下英樹『センゴク権兵衛』<講談社>の宗麟公)
宗麟の豊後の場合、宇佐神宮を筆頭とする神官勢力の存在が
領国内で大きかったからだろう。
彼の最初の妻は国東半島の神官の娘でもある。
『王の挽歌』では、国東との関係を築くために
宗麟自ら政略結婚を選んだものの、
神官の娘としての妻の誇りと気の強さに辟易としている。
(後に離婚)
また、領内の家臣の不満に、毛利、龍造寺、島津などの各氏が
つけこんだことも、大きい。
確かに、宗麟は切支丹を保護し、司祭館や今で言う病院も
造らせてはいるが、
彼自身が切支丹の受洗をするのは府内を去り、
臼杵へ移ってからのことである。

さて、今回の旅、大分市内で楽しみにしていたのが、
「南蛮BVUGO交流館」である。
2018(平成30)年開館の、この施設では、
大友宗麟の時代に、日本有数の国際貿易都市となった
「府内のまち」が体感できる。
もともと、ここは、大友氏の居館「大友館(やかた)」の跡である。
大友氏歴代の拠点として整備された館は、
戦後期時代の居館としては、屈指の規模を誇ったという。
庭園には人工的に水を流す滝まで設えてたそうで、
織田信長の岐阜城みたいではないか。
館は、1573(天正元)年、宗麟が嫡男・義統(ヨシムネ)に
家督を譲る際に大改修され、
1586(天正14)年の島津氏の豊後侵攻により廃絶している。

今の大分駅から車で10分ほど。
駅はさておき、
大分川の流れから、ほんの数百メートルのところだ。
当時は水運も使えた好立地だったのだろう。

無料で見学できる交流館では、大きな画面で歴史や
発掘の様子を知ることができる。
展示も見やすい。(↑)
さらに、隣接する発掘現場には、大友館の調査が今も続けられ、
VRで当時の姿を推定復元し、面影を偲ぶことができる。

圧巻なのは、先にも触れた信長並みの、
人工の滝をも設えた「大友氏館跡庭園」だ。

滝だけではない。
東西67m、南北30mという戦国時代の大名館では最大級の池をもち、
庭園全体の規模は5000㎡に及ぶ。
しかも池の東西では異なる景色をもつ、独自性があったという。
ここでは発掘調査で見つかった遺跡を保存しつつ、
当時の景色や空間を体感できるよう趣向を凝らして
復元整備したそうだ。
出土した景石(庭の要所に置く自然石)は、レプリカを製作し、
それを配置。
出土した石は、レプリカを作った後、遺跡保護のため、
同じ場所の地下に埋め戻された。
ただし、保存状態の良かった景石は、実物を発掘した状態で
見ることができる。

しかも、庭園に植えられた樹木も再現されている。
池底に堆積した土を分析し、戦国時代の花粉や種子を特定、
それを植えたのだそうだ。
素晴らしすぎる!
実は、2016年に、ここを訪ねたときは、な~んにもなかった。
こんな感じ。

後ろに見える、いかにも仮設の建物が、
今の交流館の場所だろうか。
こんなに広い土地なのに、もったいないなぁと思ったものだ。
それが、今や・・・
スタッフのお話によると、
大友宗麟公生誕500年となる2030年に向け、
更に大友氏館跡の歴史公園整備を進めていくのだそうだ。

決めた。
2030年、もう一度、大友氏館を訪ねよう!
*********************
おつきあいいただき、どうもありがとうございます。
私のメモと南蛮BVUGO交流館でいただいた資料を
もとにまとめましたが、間違いや勘違いはあるかもしれません。
素人のことと、お許し下さいませ。
参考:
遠藤周作『王の挽歌』上下 新潮文庫
(書影は新潮社よりお借りしました)


























