(つづき)企業PRを生業とする我々にとって、
映像作品やイベントおける「構成台本」、
そして印刷物における「ページネーション」は、
建築物の「設計図」にあたる。
台本はお客さまとの意識を一枚岩にすると同時に、
監督からスタッフへの強固な意思の表明であり、
スタッフの力への請求書でもある。
今回はなぜ
「PR作品の台本がスタッフの力への請求書なのか」
を考えてみよう。
言うまでもなくPR作品はお客さまからお金をいただき、
お客さまの思いを形にするものだ。
けっして思いつきで好き放題できるわけではない。
時には妥協も辞さない。
ではなんでもかんでもお客さまの意見を
取り入れているのかというとそうではない。
そんなことをしてしまうと作品として
バラバラ、ツキハギだらけになる。
そもそも言ったなりならプロを雇う意味がない。
お客さまの意見は尊重し、
熱い思いを形にしてあげなければならない。
そして形にするためにこそ、根底には引き下がらない強さがいる。
それは監督だけでなくスタッフ全員が認識しておかねばならない。
ただし、その引き際やまとめ方はスタッフ個々で異なる。
そのため台本を書く段階でスタッフの顔を思い浮かべながら、
書かなければ現場でワガママばかりが突出して、
ニッチもサッチいかなくなる。
皆が前に向かって走れるよう台本には
スタッフへの愛が込めらていなければならならない。
例えばAカメラマンは「望遠が好きだ」とわかっていれば、
せめてワンカット位は見せ場を作っておく。
これだけでカメラマンのテンションは3ポイントは上がる。
ただしあんまり見せ場を作ると
時間内に撮影が終わらないので、さじ加減が必要となる。
また、たいていのスタッフはドラマ仕立てになると急に燃え上がる。
撮影部は特機(クレーン.移動車.ステディカムなど)を投入したがるし、
照明部も白の発泡スチロール板(カポック)にバウンドさせた間接照明やら
鏡を使ったり、蛍光灯ライトやHMIという強力なライトを使ったりと
準備時間とレンタル経費がかかるオンパレードになる。
スタッフの作りたい魂に火がつくと、予算は一気に炎上してしまう。
しかもギャラよりも作りたい魂が優先するからタチが悪い。
プロデューサーは台本の一行一行にヒヤヒヤするので
プロデューサーへの思いやりも台本にはいる。

グリフィスの持つ特機のひとつ(グリフィスHPより写真は拝借)
こんなのが1台あると現場はなぜか燃える
社長の上竹氏とは映画「森の向こう側」でご一緒した
ドラマ仕立てに対してスタッフに不人気なのが
ドキュメンタリー仕立ての作品だ。
私はドキュメンタリー系監督の巨匠なので
スタッフ人選には毎回苦慮する。
台本の真意を読み取れるスタッフが少ないのだ。
そもそも監督の私でさえ現場で何が起こるかわからないのに
台本にするなんてほとんど不可能!
従って台本はスタッフへのラブレターとなってしまう。
「こんな感じの作品にしたい」「人の動きではなく考え方を撮りたい」
「カメラは俯瞰位置でいつも客観的に」とか、
全く意味不明の指示書になる。
しかしこれを読む人が読むと、
私の描いている形にしてくれるのだからスタッフってスゴい。
期待をあらかじめ人選で予感し、
あえて台本には果敢な注文を盛り込み、
スタッフ力を発揮してもらう。
これこそが、ドキュメンタリーに長けた監督の台本であり、
仕事の仕方なのだ。
予算ありき、条件ありき、人間関係ありきの過酷なPR映像が、
スポンサーの言いなりで骨抜きにならないよう、
監督は作品作りに心血を注がねばならない。
しかもドキュメンタリーは日々状況が変わる。
時には白が黒になることもある。
それを「面白い」と取るか、「やっとれるかえ!」と取るか
監督はスタッフが嬉々として仕事ができる環境を作らねばならない。
時には振り返って状況を1から説明することも
「楽しさ」として演出しなければならない。
そのための第一歩として
スタッフへの力の請求書(コンセプト=ラブレター)を
どう形にするかが、私は大切だと思う。
コンセプトから出てきた撮影台本は、台本とは名ばかりで
スケジュールに毛の生えたようなものだ。
すべてはコンセプト=ラブレターが原点になる。
続いてはやっとの思いで終わらせた
(時には気楽に臨機応変な)「撮影」を締めくくる、
私の本領発揮の場でもある「編集」で結実する
ナレーション原稿についてだが、お後もよろしいようで…
ナレーション原稿への台本進化論はまた明日のココロなのだ。
といいつつ、今日から松山出張のため、今週は以上終わりです。
(つづく)
映像作品やイベントおける「構成台本」、
そして印刷物における「ページネーション」は、
建築物の「設計図」にあたる。
台本はお客さまとの意識を一枚岩にすると同時に、
監督からスタッフへの強固な意思の表明であり、
スタッフの力への請求書でもある。
今回はなぜ
「PR作品の台本がスタッフの力への請求書なのか」
を考えてみよう。
言うまでもなくPR作品はお客さまからお金をいただき、
お客さまの思いを形にするものだ。
けっして思いつきで好き放題できるわけではない。
時には妥協も辞さない。
ではなんでもかんでもお客さまの意見を
取り入れているのかというとそうではない。
そんなことをしてしまうと作品として
バラバラ、ツキハギだらけになる。
そもそも言ったなりならプロを雇う意味がない。
お客さまの意見は尊重し、
熱い思いを形にしてあげなければならない。
そして形にするためにこそ、根底には引き下がらない強さがいる。
それは監督だけでなくスタッフ全員が認識しておかねばならない。
ただし、その引き際やまとめ方はスタッフ個々で異なる。
そのため台本を書く段階でスタッフの顔を思い浮かべながら、
書かなければ現場でワガママばかりが突出して、
ニッチもサッチいかなくなる。
皆が前に向かって走れるよう台本には
スタッフへの愛が込めらていなければならならない。
例えばAカメラマンは「望遠が好きだ」とわかっていれば、
せめてワンカット位は見せ場を作っておく。
これだけでカメラマンのテンションは3ポイントは上がる。
ただしあんまり見せ場を作ると
時間内に撮影が終わらないので、さじ加減が必要となる。
また、たいていのスタッフはドラマ仕立てになると急に燃え上がる。
撮影部は特機(クレーン.移動車.ステディカムなど)を投入したがるし、
照明部も白の発泡スチロール板(カポック)にバウンドさせた間接照明やら
鏡を使ったり、蛍光灯ライトやHMIという強力なライトを使ったりと
準備時間とレンタル経費がかかるオンパレードになる。
スタッフの作りたい魂に火がつくと、予算は一気に炎上してしまう。
しかもギャラよりも作りたい魂が優先するからタチが悪い。
プロデューサーは台本の一行一行にヒヤヒヤするので
プロデューサーへの思いやりも台本にはいる。

グリフィスの持つ特機のひとつ(グリフィスHPより写真は拝借)
こんなのが1台あると現場はなぜか燃える
社長の上竹氏とは映画「森の向こう側」でご一緒した
ドラマ仕立てに対してスタッフに不人気なのが
ドキュメンタリー仕立ての作品だ。
私はドキュメンタリー系監督の巨匠なので
スタッフ人選には毎回苦慮する。
台本の真意を読み取れるスタッフが少ないのだ。
そもそも監督の私でさえ現場で何が起こるかわからないのに
台本にするなんてほとんど不可能!
従って台本はスタッフへのラブレターとなってしまう。
「こんな感じの作品にしたい」「人の動きではなく考え方を撮りたい」
「カメラは俯瞰位置でいつも客観的に」とか、
全く意味不明の指示書になる。
しかしこれを読む人が読むと、
私の描いている形にしてくれるのだからスタッフってスゴい。
期待をあらかじめ人選で予感し、
あえて台本には果敢な注文を盛り込み、
スタッフ力を発揮してもらう。
これこそが、ドキュメンタリーに長けた監督の台本であり、
仕事の仕方なのだ。
予算ありき、条件ありき、人間関係ありきの過酷なPR映像が、
スポンサーの言いなりで骨抜きにならないよう、
監督は作品作りに心血を注がねばならない。
しかもドキュメンタリーは日々状況が変わる。
時には白が黒になることもある。
それを「面白い」と取るか、「やっとれるかえ!」と取るか
監督はスタッフが嬉々として仕事ができる環境を作らねばならない。
時には振り返って状況を1から説明することも
「楽しさ」として演出しなければならない。
そのための第一歩として
スタッフへの力の請求書(コンセプト=ラブレター)を
どう形にするかが、私は大切だと思う。
コンセプトから出てきた撮影台本は、台本とは名ばかりで
スケジュールに毛の生えたようなものだ。
すべてはコンセプト=ラブレターが原点になる。
続いてはやっとの思いで終わらせた
(時には気楽に臨機応変な)「撮影」を締めくくる、
私の本領発揮の場でもある「編集」で結実する
ナレーション原稿についてだが、お後もよろしいようで…
ナレーション原稿への台本進化論はまた明日のココロなのだ。
といいつつ、今日から松山出張のため、今週は以上終わりです。
(つづく)



















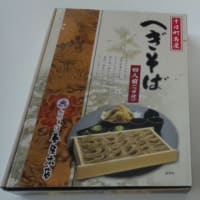
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます