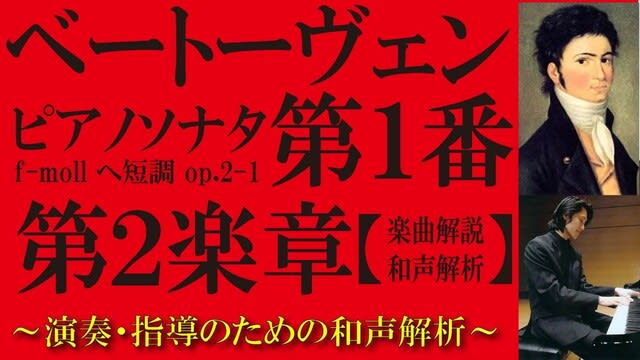
【楽曲解説・和声分析】
L.v.Beethoven《Klaviersonate Nr.1 f-moll op.2-1》〈II Adagio〉
若かりし25歳頃のベートーヴェンが書いた
美しい緩徐楽章です。
やはりロミオとジュリエット然り!?
優しいベートーヴェンの恋愛観が垣間見られるような
音楽とも解釈されました。
音の妙技とともに
お愉しみいただけたらと思います♪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【楽曲解説・和声分析】ベートーヴェン《ピアノソナタ第1番 op.2-1》〈第2楽章 Adagio〉
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↓ 時間をクリックすると表題毎にスキップできます
0:00~ ベートーヴェン《ピアノソナタ第1番 f-moll ヘ短調 op.2-1》〈第2楽章 Adagio〉
0:28~ Adagioゆっくりの三拍子、♭1つのF-Durへ長調
0:49~ 冒頭、【反復音】ゆえにペダルが無いと音が切れてしまう、【ペダル不可欠】 必要不可欠なペダルの場所を徹底的に探すベートーヴェン研究、 真面目で充実したベートーヴェン演奏のために
1:32~ 1小節③拍目、左手の反復音のためにペダル不可欠
2:33~ 1小節①拍目、装飾音「ターン」C.P.E.バッハ曰く【Doppelschlag二重打音】の弾き方
3:22~ 7小節②拍目裏、十六分音符Laの真上に書かれている【Doppelschlag二重打音】の場合(5音弾くのは間違い)
4:19~ 【Doppelschlag二重打音】音と音の間に書かれてある場合、9, 11, 13, 16, 18, 20小節等
5:05~ 【Doppelschlag二重打音】弾くタイミングは、五連符として、その最初の音をタイで結ぶように
6:08~ 1小節②拍目、【前打音】は左手②拍目と同時に弾く、するとReとDoの7度のぶつかり不協和音が美しく響く、
7:16~ 【前打音】の歌い方、(エレキギターのチョーキング奏法のような感じ!?)
9:08~ これすなわち【倚音】の魅力、和音から外れている不協和音を大事に、そして響きの中に収めていく、緊張と緩和の美学、その現実
10:09~ 【II,IV,VI和声解析法】、1小節②拍目、左手Reは第VI音、右手Si♭は第IV音、〔サブドミナント系〕の音に盛り上がり
10:48~ 〔サブドミナント〕、凄く美しい音楽を奏でたい、25歳の若いベートーヴェンの強い意欲、〈1楽章〉の激情と打って変わった〈2楽章〉の柔和で甘美な音楽性
12:39~ 2小節、〔D46〕という大事な和音とともに「拍感」が得られる
13:53~ 2小節②拍目裏、左手の八分休符まで音をピッタリ伸ばしておく注意(←演奏が充実するコツ)
15:13~ 3小節、十六分休符に注意、左手の四分音符を聴く、ペダルを使わないと音が切れてしまうからペダル不可欠
16:41~ ②拍目からAlt声部の四分音符にも注意
18:10~ 4小節②拍目、反復音があるけど、フレーズ終わりだからペダルを使わずに、一瞬の間がフレーズ感を表現できる
19:19~ 音の長さ「音価」にとことん注意し、「ペダルを少なめに」ベートーヴェンを弾く(アルペジオの時はペダルを沢山使う!?)
20:38~ 6小節①拍目、「サブドミナント」が大事
21:21~ 6~7小節は「ヘミオラ」?
21:39~ 6小節③拍目、〔T〕だけど〔倚音〕もあり!盛り上がっている
23:04~ 7小節①拍目も〔S〕と〔倚音〕で大事
23:42~ ②拍目の〔D64〕も大事、スラーも書かれている
24:49~ 8小節、左手に反復音があるからペダル不可欠 敢えてタイが無い!?反復音があるゆえにペダルの使用をベートーヴェンが促している!?
26:13~ 9小節、右手は〔倚音〕大事に弾いて減衰、楽譜のクレッシェンドは左手のため?
27:26~ 10小節、〔刺繡音〕濁る不協和音の美しさ
28:14~ 13小節、冒頭よりオクターヴ上のメロディは〔女声、Sop.〕のよう、冒頭は〔男声〕
29:49~ 9小節でクレッシェンドした伴奏に対する12小節の〔pp〕
31:36~ 12小節、スラーが終わっているから〔半終止〕、〔D→T〕はいつも〔全終止〕とは限らない
33:12~ 14小節、〔S〕で〔倚音〕、③拍目はrinforzatoの〔デュエット〕、愛の物語!?
36:14~ 15小節は〔カデンツ〕、16小節は〔倚和音〕から〔全終止〕、ペダル無しで演奏可能、減衰のコツ
37:45~ 15小節③拍目、Laはd-mollの第V音となり転調、Sol♯は〔増4度ドッペルドミナント〕
39:11~ 16小節~、四分音符を伸ばしておくためには最後にペダルを踏まないといけない、【ペダル踏み加減の問題】
41:23~ 左手の十六分休符にも注意
42:28~ 16小節~の和声
42:55~ ③拍目〔デュエット〕、オクターヴ反復音のためにもペダル不可欠
44:50~ 19小節、Sop.だけの答え、全終止
45:24~ 21小節、①拍目裏のSi♮でC-Durに転調、Sop.のReは全終止のようでも伴奏が半終止
48:31~ ③拍目から〔Duetto〕、25歳のベートーヴェンは、まだモジャモジャの髪型ではない(モジャモジャは1813年以降、不滅の恋人への手紙の後)、若い青年の恋愛観・結婚願望、1楽章は『ロミオとジュリエット』みたいに解釈できた
51:11~ 22小節、スラー頭は〔倚音〕3つとも大事に盛り上がりつつ
52:38~ 23小節、Sop.に〔倚音〕、②拍目の左手La♭は〔短6度〕暗い表情の男声
55:05~ 24小節、装飾音は拍と一緒に(前に出さず)
56:53~ 25小節、〔S〕、③拍目は〔II〕、26小節は〔D46〕
57:31~ 26小節②拍目~、【ポルタ―ト】は大事に歌う(《op.13第2楽章》《op.110第1楽章》)
59:21~ 27小節~、音量はもう「pp」ではない(たっぷりの音量)、指使い
1:00:55~ ③拍目、3声の和音レガートには【ペダル不可欠】
1:02:26~ ①拍目裏はフレーズ終わりにつき、反復音があってもペダル無し
1:04:16~ 29小節①拍目裏、装飾音〔ドッペルシュラーク〕の弾き方に注意
1:05:10~ 28小節③拍目、「5(短)→4(長)」の指使いで自然な減衰
1:06:20~ ①拍目、〔倚音〕、ベートーヴェンも同じ指使い(クラシック音楽の醍醐味)
1:07:36~ 29小節②拍目~〔倚音〕的、クレッシェンドして30小節「fp」へ
1:08:56~ 「sfp」と「fp」の弾き分け方
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:10:30 ~ 32小節、〔再現部〕
1:11:13~ 31小節、F-Durに転調、「sf」は転調の予感
1:12:28~ 左手にフィンガーペダルを使うか!?ヴィオラの声部のようにするか!?
1:14:34~ 34小節、スタッカートの後で一瞬にペダルを踏む、右手①拍目は四分音符ではない
1:15:57~ 35小節②拍目裏、大事な【ポルタ―ト】の後に36小節~アルペジオの素敵な音楽
1:16:23~ アルペジオの場合、ハープのように音価以上に音が伸びる、フィンガーペダルかペダルを使用か
1:19:02~ ペダル使用は中毒性あり!?
1:20:57~ チェルニー著『ベートーヴェン全ピアノ作品の正しい奏法』より37小節~について助言
1:22:46~ 39小節③拍目、ppではなく(ppに賞味期限あり)、左手の音階にも意味あり?
1:24:37~ 40小節はクレッシェンド無し、だけど9小節のクレッシェンド有りの音楽性を踏襲
1:25:53~ 39小節②拍目裏、〔反復音〕ゆえに〔全終止〕が意識される!? ベートーヴェンにおける【反復音の秘密】とはいかに!?
1:28:15~ 38小節~
1:28:45~ 45小節③拍目は「sf」、14小節では「finf.」
1:29:59~ 46小節③拍目は「pp」、15小節では無し
1:31:27~ 47小節②拍目裏、〔男声〕
1:31:57~ 【形式についての考察】〔再現部〕においては、短調d-mollの部分が省略されて、すぐ〔第2テーマ的〕な部分に。この曲の形式は? 31小節のみが〔展開部〕とは言えないから〔ソナタ形式〕と言えない…
1:32:50~ 28小節は「sfp」と30小節に「fp」、53小節は「fp」と55小節に「sf」
1:34:10~ 59小節から〔Coda〕
1:35:00~ 23小節はSop.がハ長調(へ長調の属調)、48小節は男声がへ長調(主調)ゆえに〔第2テーマ(的)〕、左手は〔内面の声〕?
1:37:24~ 49小節においては〔装飾音〕無し、24小節には有り、音域の差ゆえに?
1:38:15~ 51小節③拍目、左手は四分音符、26小節では八分音符と八分休符、右手はポルタ―トの〔pp〕、左手の四分音符を保つために途中から右手で置き換え
1:42:07~ 52小節~
1:42:37~ 54小節①拍目、まずは【ペダル無し】で練習、その後【味付け程度のペダル】
1:46:22~ 54小節②拍目~、左右で音がいよいよぶつかる
1:46:36~ 56小節①拍目、ペダルが無いと乾いて聞こえる…【アルペジオにペダル不可欠】
1:47:52~ 57小節②拍目、この曲の〔ポルタ―ト〕はペダル無しで指で?
1:48:04~ ③拍目、左手の和音を途中から右手で取ることでペダル無しでのレガートが可能、5本指全てを使ってレガートにする工夫
1:49:34~ 58小節②拍目、装飾音〔ドッペルシュラーク〕の位置が『ベーレンライター版』においてのみ違う、『ウィーン原典版』『ヘンレ版』『ペータース版Claudio Arrau校訂』との比較
1:50:26~ Claudio Arrauの解釈によると〔ドッペルシュラーク〕は上から始まる装飾音(ポルタ―ト無し)
1:52:40~ 『ベーレンライター版』の校定報告Janathan Del Mal氏によると、『初版』はハッキリこのように
1:54:17~ 《ピアノソナタop.2》は《自筆譜》は紛失…
1:55:22~ 59小節②拍目裏の〔ドッペルシュラーク〕は音符の上に書かれている
1:56:31~ 56小節②拍目の休符でペダルをはなす
1:57:02~ 57小節②拍目、終わりの音であり始まりの音でもある、二つのスラーをベートーヴェンが重ねて書くのは珍らしい
1:57:44~ 59小節③拍目、左手Re♭は第VI↓音、短調から借りて来た暗めの音、「<>」はespressivoと同義、右手Doは〔倚音〕
1:59:46~ 60小節、左手は〔変終止〕のようだけど、右手に導音があるから〔全終止〕
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼ベートーヴェン【ピアノソナタ全32曲 楽曲和声解析】動画一覧▼ https://www.youtube.com/playlist?list...
☆ 瀬川玄 Gen Segawa (@pianistGS) · Twitter▼ https://twitter.com/pianistGS






















いつか、瀬川先生のベートーベンを生で聴けたら❤️と思っております❤️
三大ソナタをコンサートで聴きたいと。
ところで。
もし可能なら、c.p.バッハの「ソルフェジエット」の講義をよろしくお願いいたします‼️