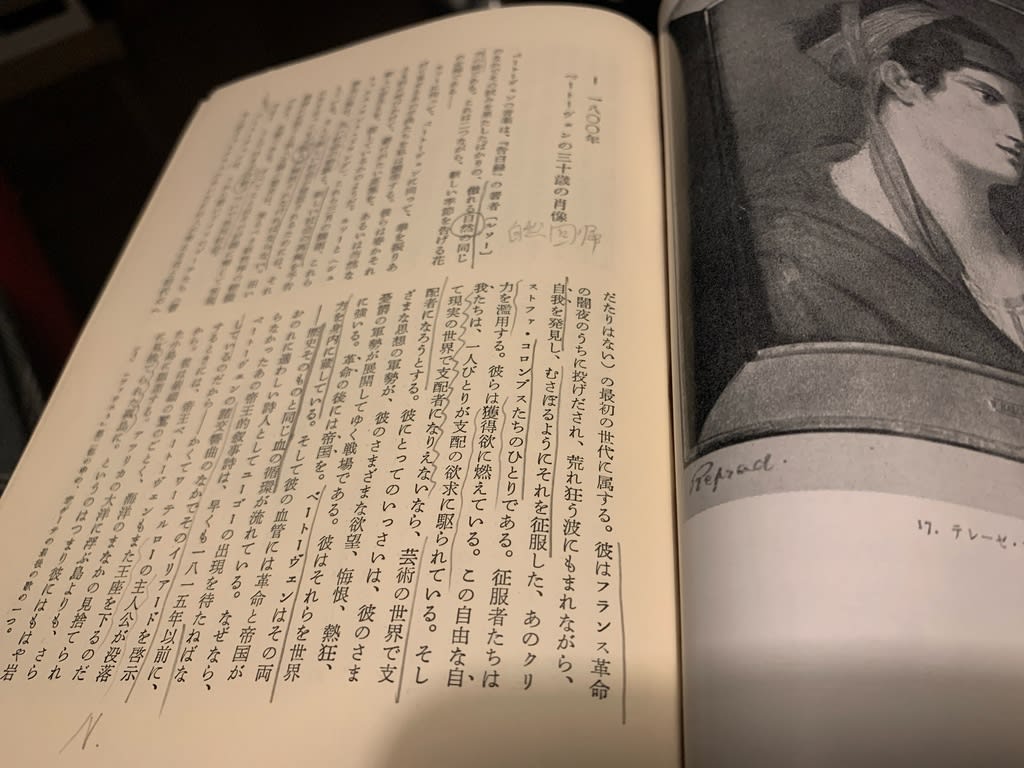
ベートーヴェンは、これら若いドイツのゲーテたち(彼らと老リュウケウスのあいだには人が考えるほど時代のへだたりはない)の最初の世代に属する。彼はフランス革命の闇夜のうちに投げだされ、荒れ狂う波にもまれながら、「自我」を発見し、むさぼるようにそれを征服した、あのクリストファ・コロンブスたちのひとりである。征服者たちは力を濫用する。彼らは獲得欲に燃えている。この自由な「自我」たちは、一人びとりが支配の欲求に駆られている。そして現実の世界で支配者になりえないなら、芸術の世界で支配者になろうとする。彼にとってのいっさいは、彼のさまざまな思想の軍勢が、彼のさまざまな欲望、悔恨、熱狂、憂鬱の軍勢が展開してゆく戦場である。彼はそれを世界に強いる。「革命」の後には「帝国」を。ベートーヴェンはその両方を身内に蔵している。そして彼の血管には革命と帝国がーー歴史そのものと同じ血の循環が流れている。なぜなら、おのれに適わしい詩人としてユーゴーの出現を待たねばならなかったあの帝王的叙事詩は、早くも1815年以前に、ベートーヴェンの諸交響曲のなかでそのイリアードを啓示しているのだからーーかくてワーテルローの主人公が没落するときには、帝王ベートーヴェンもまた玉座を下るのだから。彼は巌頭の鷲のごとく、海洋のまなかに見捨てられた小島に隠遁する。アフリカの大洋に浮かぶ島よりも、さらに見捨てられた孤島に。というのはつまり彼にはもはや岩に砕ける波の音すら聞こえないからだ。彼は幽閉されている。そしてその静寂のなかから、あの最後の十年間の「自我」の歌声が起って来る。それはもはや以前と同じ「自我」ではない。彼は人間たちの帝国を捨て、彼の神と共にいるのである。
(9)



















