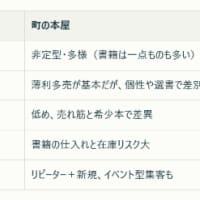ときに「正規の日本語として正しいのか?」と評されることのある特異語「困った(御方です)」は連体詞らしいです。
この用法は
・「難問を抱えてて困った人」みたいに「--ている人」という言い換えも互換できるタイプでもありませんし、
・「保育園探しで困った人」みたいに過去を表す用法でもない、同じ連体修飾の中でも少し毛色の違ったタイプであります。(特殊な連体修飾)
連体詞と呼ぶにはそれなりの理由がありそうで、
似たような構造の語として「おめでたい人」というのがありまして、これは先程の前2者のような状態性質のものに典型的に当てはめることはできませんが
典型用法の「困った」に比べて「困れず・困るとき・困れば」のような活用展開も可能な含みのあるものにはなり得ない特殊な「困った」であるということ(つまり活用が限られているということ)が認められます。
それに加えて名詞を修飾限定していくうちに本義からはなれて特殊化された語彙に変化していくという歴史的・経時的な移ろいが見られるということであります。
「おめでたい」もめでたいという額面通りの意味からずれが生じて皮肉ったニュアンスに特殊化されていますし「困った」にしてももっぱらそういう扱いの人というように性質づけに変容が起こっています。
このように専業化していくということによって活用ラインナップ空間から切り離されていく再構成のプロセスを加味すると連体詞ととらえる事にもうなづけるものがあります。
ここで三枝令子(2011)「感情を表す動詞「困る」が示すテンス・アスペクト」の論文中に重要な記述がありましたので引用してみます。
(引用)--
動作動詞の場合には、「作る時」「作る人」「作った時」「作った人」と、ル形、タ形とも接続が可能だが、
「困る」では、「困る人」「困る時」とは言えず、その感情が発動された「困った」によってはじめて「とき」「人」を修飾できる。
また、「困った人」には二通りの意味がありえる。
(18) 就職に困った人が相談に来た。
(19) 彼は、人の気持ちが読めない困った人だ。
すなわち「人」が「困った」の主格である場合と、対象の場合である。
後者の「外の関係」の場合には、「困った」が形容詞的役割を担うので、「困った会社」「困ったお客」のように独立して使うことが可能である。
--(引用終わり)
…ここで重要な視点が出てきますね。「困る」という動詞のもつ個別的な語彙はおいておくとしまして、被修飾名詞に到達するまでの焦点のとるべき道・ルートがまったく異なるということ甚だしいという新鮮な驚きであります。これは分裂といっていいくらいの事態であります。
「内の関係」「外の関係」の説明は後述するとしまして、まず以下の例をご覧ください。
・トイレに行けないコマーシャル
・クレジット情報入力しそうな人でした
これらの文には2通りの解釈があります。
ひとつは荒唐無稽で、コマーシャル君という概念人格が尿意を催し、行きたくても行けずに煩悶するという解釈です。もちろんこんなのはありませんね。
腑に落ちる解釈の方はコマーシャルを見ている我々視聴者がお茶の間においてトイレに行くのを忘れてしまうくらいの見どころあるコマーシャルだというのがどうやら順当であります。
どうやら第三者視点が持ち込まれていることに差異があるのでしょうか?もう少し解きほぐしてみます。
「クレジット情報入力しそうな人でした」こちらは眼前の人が風貌や話しぶりなどからの推測で「なにかクレジット情報を扱う」まがいのことを日常的にやっていそうな感じだと言ったところでしょうか。
しかしピンポイントでこんなニッチな連想を想起する、人への形容というのはあまり自然ではありません。
おそらく、何らかのオペレーターや営業担当者が入力業務をしておりそこでのお客様振り返りの話題のときに職場ででてきたフレーズと解釈するほうが現実的です。
第三者視点というのをキーワードにしてみたものの…うーん、いろいろWebで関連をあたってみましたが上手い言い回しがない…例えていうなら第三者というより「場」とのリンケージに着眼点がありそうな予感がします。
昨日食べた大福、あした来そうな人みたいに素直な連体修飾では被修飾名詞をより詳しく規定してやろう、属性を付加してやろうとの力学がはたらいております。
属性は内在しておりここで付加された新たな属性情報はその個物の内部情報として獲得します。
翻って「トイレに行けないコマーシャル」はどうでしょうか?
なんでしたら「食えない視聴者」「筆の進まない週末」「いらない子」なんてのでもいいです。
これらは素材をあれこれデコレーションするのとは違う別の観点、話し手の発話時の感情が示されている…話者観点コンテクストの介入というのが重要なキーになっているものだと推測します。
とまあ自分流の解釈に拘泥し続けるのも見苦しいので本来の筋に戻ってこの論文中にでてきた「内の関係」「外の関係」についてさらっとおさらいしておこうかと思います。
寺村秀夫によれば、日本語の連体修飾節構造は、修飾語と被修飾節との間に格関係が成立する「内の関係」と、
そのような関係が成立しない「外の関係」とに分類される…としています。
次のAは「内の関係」の例であり、Bは「外の関係」の例である。
A. 秋刀魚を焼く男 (男-焼く:主述関係)
B. 秋刀魚を焼く匂い (匂い-焼く:「主語-述語」関係も「連用修飾語-述語」関係も見いだせない)
これらを主語を頭にもってきて格関係のある別の文に書き換えができるか試みてみます。
A. 男が秋刀魚を焼く
B. (その)匂い □ 秋刀魚を焼く
となりAはガ格で転換できますがBには適切な格助詞をあてはめることができず非文となってしまいます。
つまりBの文ではどんな格関係も成り立たないものであります。この違いを区別し名称が与えられています。それが
Aは「内の関係」の連体修飾成分
Bは「外の関係」の連体修飾成分
ということであります。
ちなみに、被修飾名詞=修飾される側の名詞のことを「底」(てい)と呼びます。
一概には言えませんが、「内の関係」のときと「外の関係」で使われるときの底の語彙的振る舞い・性質にはある種の傾向が認められており、
「内の関係」のときの底の名詞は具体性の高い名詞が(写真、カレー、プレゼント)、
「外の関係」のときの底の名詞は抽象性の高い名詞がくる(噂、匂い、傾向、記憶、残り)
…ですが文脈によっては想定どおりにいかない例もままありますので参考程度にとどめておいてくださいね。
さて「外の関係」というものにつきましては以前過去記事で触れた「文末名詞」や「人魚構文」と着眼点に通底するものがあると勝手に受け取っているのでありますが、
たとえば被修飾名詞へのかかり方などにしましても描写で規定していくのではなくて先行する修飾成分を内容として編集的に組み入れる、またその結果としての底への結節という文法的・統語的編入に落ち着くという体をなすところが英語の関係代名詞みたいでトリッキーで趣き深いと感じる由でもあります。
ただちょっと疑問なところなのではありますが
「気のきいた言い回し」などにみられるフレーズを内/外の関係判定テストにかけてみたとき、杓子定規に当てはめて格関係で文転換できるかやってみますと
⇔言い回しが気のきいている(*)
となりちょっと違和感があるのでこれは格関係成り立たずBの「外の関係」構文である、と判定してしまうのはいささか早計であるかと思っています。
これをちょっといじれば
⇔言い回しが気がきいている(○)
となりイディオム中の細かな助詞を微調整してやれば格関係成り立つのでAの「内の構文」と判定できなくもない事態ではないのか(もちろん本来はBの外の構文の胸算用ではありますが)
…という不都合が出てきてしまいます。
用言部分が1チャンクの動詞ではなく助詞の種々付随するイディオムフレーズのときには連体修飾のとらえかたも精緻化が求められているのではないか?という疑問です。
まあそこまで追求するのは他のタスクもありますし余裕があったら深掘りしてみたい課題とさせていただきます。やはり日本語文法は沼ですね~アセアセ
なお今回の記事は迷いましたが連体修飾は形容詞カテゴリーの規定語とも深く関連するという観点からカテゴリ:「形容詞研究」に分類しましたのであしからずご了承ください。
以上、「予約の取れない大工」じゃなかった「うだつのあがらないブロガー」ぴとてつがお送りした言語トピックでした。