皇位継承の在り方につき、筆者は、女系容認に傾きつつある。ただ、そのように自覚すればするで、男系男子についての未練のようなものを感じてしまう。
この未練とは、一体何なのであろうか。
そこで、今回は、男系男子論について、改めて考えてみることにした。
そもそも、男系男子ということに、どのような意味があるのだろうか。
この点については、既存の議論では十分に解明されていないようであり、推測するしかないのであるが、以下のように考えることができよう。
まず、世襲制というものが存在する社会においては、何故に世襲制が人々に支持されるのであろうか。
それは、君主たる者の特徴を、最も多く受け継いでいるのが、その子であるという考え方によるのであろう。太古において、人々に遺伝の知識は無かったにせよ、子が親に似るということは、ごく自然に認識されていたであろうし、また、遺伝ということのほか、親と子が共に暮らすことにより受け継がれる後天的な資質ということも重要であったろう。
そして、この世のあらゆるものが、世代から世代へと、親から子に受け継がれるものであろうという意識が強い社会においては、君主たる者の特徴を最も受け継いでいるはずの子にこそ、その資格の継承が認められることとなったであろう。
ここで、男系男子ということについては、先天的資質が男系によって多く受け継がれるという観念によるものであったかもしれない。
また、あるいは、後継者を多く確保するという必要性から、一夫多妻制が採用され、その結果、血の継承における女性の個性が希薄化したということもあったかもしれない。
以上については、今までに何度か述べてきたことである。
さらに、ほかの理由としては、政争を生き抜くためといった実際上の要請もあったであろう。
ただ、このように考えてみると、これら、男系男子でなければならないとする要因については、現在、かなり軽減されてきていると言えないだろうか。
まず、親から子への特徴の継承という点では、男系だけに限る必然性はあるまい。Y染色体に着目する議論もあるが、Y染色体自身の遺伝情報というものはかなり乏しいものであり、特徴の継承という点では意味はないものである。また、太古の人々にY染色体の知識があるはずはなく、太古より受け継がれてきた男系男子の意味の解明ということとは、無関係の議論であろう。
また、現在の皇室では、側室は認められなくなっており、このことは今後も維持されるであろうから、一夫多妻制における女性の没個性化という事情はなくなっている。
さらに、天皇の地位に関しては、象徴天皇制ということが確立しており、政争の渦中において対応をせまられるということも無くなったと言える。
このように考えてみると、男系男子でなければならないとする根拠は、かなり弱くなったと言えるのではないだろうか。
ただ、そうであるからといって、簡単に男系男子に意味がないと言えるかとなると、どうもそういうことにはならないようである。
冒頭に述べた筆者の未練ということも、ここに関係している。
改めて、「現在」の男系男子論を見てみると分かると思うのだが、そこには、男系男子ということがどのように始まったのか、男系男子にどのような意味があるのかということは論じられていない。論者の多くは、そういうことは問題にしていないようなのだ。論じられているのは、もっぱら、男系男子が125代続いてきたという歴史的な重みの強調である。
これは、一見、怠惰な研究姿勢の表れのように見えなくもないが、実は、ここにこそ、現在の男系男子論の本質が表れている。それは、すなわち、皇室というご存在の意義、皇室と日本人との関係ということとは、次元の異なる価値観に基づくものであるということである。
なぜならば、男系男子ということが125代続いてきたという歴史的な重みであるが、それは、後代において、歴史が積み重なったことによって生まれた価値だからであり、後代という視点に立った価値だからである。
この価値を何よりも重視するというのは、例えれば、美というものに対する一種の執着のようなものであろうか。
このように書くとあまり大したことのない話のようであるが、これは、なかなか手強く恐ろしいものであると思う。
功利主義的な観点、また人権思想から批判することは簡単である。ただ、それらによっていくら批判しても、ビクともしないのである。
もともと、美というものの価値、人がそれに惹かれるということに、理由はないからである。
それ故に、手強い。
また、その恐ろしさというのは、必ずしも人間的な価値を志向していないということである。むしろ、逆に、人間的な価値というものを自らに奉仕させることを求めるという特質があるようである。分かり易く言えば、それに払う人々の犠牲が多ければ多いほど、その価値が高まってしまうという特質があるということである。かつての女性天皇たちが如何に自らの人生を犠牲にして男系を守ってきたかということについて、男系男子論者により、美しい話として紹介されることがあるが、それはまさにこのことを裏付けていよう。
そして、恐ろしければ捨ててしまえばよいのであろうが、人間の宿命的な性質として、そのような美というものへの執着は捨てきることもできないのであろう。
これは、いい加減に扱えば、手痛いしっぺ返しを受けることになる。しっぺ返しで済めばいいが、致命的なダメージになる可能性もあり得る。例えば、日本という国の価値が損なわれてしまったという絶望感の蔓延ということである。国家の在り方について何も考えていないような者には、あまり影響はないかもしれないが、真剣に考える者において、国家の運営を担うような者の間において、そのような絶望感が広まるとすれば、深刻である。
このような、伝統の積み重なりの美しさに対する執着心の性質にかんがみて、国家の安定的な運営という観点から、男系男子を維持するべきという立論は、十分成り立つであろう。
男系男子論者といってもピンきりであるが、小堀桂一郎氏の論には、このことが自覚されているように感じられる。氏の主張する「道理」ということ、そして、「道理」の担い手は、皇室ではなくて、力ある賢明な臣下であるという認識、また、氏が、一般の国民ではなく政治家をその主張の相手先としている点など、まさにこのことの表れではないか。
したがって、女系容認に踏み切るのであれば、どうしても、それなりの覚悟が必要となるのである。まずは、男系男子で続いてきたことの伝統の重みを踏まえなければなるまい。そして、その伝統の重みに見合うだけの価値というものを見出し、それを踏まえる必要があるだろう。それは結局、皇室というご存在の意義、皇室と日本人との関係の本質を見極めるということにほかならないはずである。
この未練とは、一体何なのであろうか。
そこで、今回は、男系男子論について、改めて考えてみることにした。
そもそも、男系男子ということに、どのような意味があるのだろうか。
この点については、既存の議論では十分に解明されていないようであり、推測するしかないのであるが、以下のように考えることができよう。
まず、世襲制というものが存在する社会においては、何故に世襲制が人々に支持されるのであろうか。
それは、君主たる者の特徴を、最も多く受け継いでいるのが、その子であるという考え方によるのであろう。太古において、人々に遺伝の知識は無かったにせよ、子が親に似るということは、ごく自然に認識されていたであろうし、また、遺伝ということのほか、親と子が共に暮らすことにより受け継がれる後天的な資質ということも重要であったろう。
そして、この世のあらゆるものが、世代から世代へと、親から子に受け継がれるものであろうという意識が強い社会においては、君主たる者の特徴を最も受け継いでいるはずの子にこそ、その資格の継承が認められることとなったであろう。
ここで、男系男子ということについては、先天的資質が男系によって多く受け継がれるという観念によるものであったかもしれない。
また、あるいは、後継者を多く確保するという必要性から、一夫多妻制が採用され、その結果、血の継承における女性の個性が希薄化したということもあったかもしれない。
以上については、今までに何度か述べてきたことである。
さらに、ほかの理由としては、政争を生き抜くためといった実際上の要請もあったであろう。
ただ、このように考えてみると、これら、男系男子でなければならないとする要因については、現在、かなり軽減されてきていると言えないだろうか。
まず、親から子への特徴の継承という点では、男系だけに限る必然性はあるまい。Y染色体に着目する議論もあるが、Y染色体自身の遺伝情報というものはかなり乏しいものであり、特徴の継承という点では意味はないものである。また、太古の人々にY染色体の知識があるはずはなく、太古より受け継がれてきた男系男子の意味の解明ということとは、無関係の議論であろう。
また、現在の皇室では、側室は認められなくなっており、このことは今後も維持されるであろうから、一夫多妻制における女性の没個性化という事情はなくなっている。
さらに、天皇の地位に関しては、象徴天皇制ということが確立しており、政争の渦中において対応をせまられるということも無くなったと言える。
このように考えてみると、男系男子でなければならないとする根拠は、かなり弱くなったと言えるのではないだろうか。
ただ、そうであるからといって、簡単に男系男子に意味がないと言えるかとなると、どうもそういうことにはならないようである。
冒頭に述べた筆者の未練ということも、ここに関係している。
改めて、「現在」の男系男子論を見てみると分かると思うのだが、そこには、男系男子ということがどのように始まったのか、男系男子にどのような意味があるのかということは論じられていない。論者の多くは、そういうことは問題にしていないようなのだ。論じられているのは、もっぱら、男系男子が125代続いてきたという歴史的な重みの強調である。
これは、一見、怠惰な研究姿勢の表れのように見えなくもないが、実は、ここにこそ、現在の男系男子論の本質が表れている。それは、すなわち、皇室というご存在の意義、皇室と日本人との関係ということとは、次元の異なる価値観に基づくものであるということである。
なぜならば、男系男子ということが125代続いてきたという歴史的な重みであるが、それは、後代において、歴史が積み重なったことによって生まれた価値だからであり、後代という視点に立った価値だからである。
この価値を何よりも重視するというのは、例えれば、美というものに対する一種の執着のようなものであろうか。
このように書くとあまり大したことのない話のようであるが、これは、なかなか手強く恐ろしいものであると思う。
功利主義的な観点、また人権思想から批判することは簡単である。ただ、それらによっていくら批判しても、ビクともしないのである。
もともと、美というものの価値、人がそれに惹かれるということに、理由はないからである。
それ故に、手強い。
また、その恐ろしさというのは、必ずしも人間的な価値を志向していないということである。むしろ、逆に、人間的な価値というものを自らに奉仕させることを求めるという特質があるようである。分かり易く言えば、それに払う人々の犠牲が多ければ多いほど、その価値が高まってしまうという特質があるということである。かつての女性天皇たちが如何に自らの人生を犠牲にして男系を守ってきたかということについて、男系男子論者により、美しい話として紹介されることがあるが、それはまさにこのことを裏付けていよう。
そして、恐ろしければ捨ててしまえばよいのであろうが、人間の宿命的な性質として、そのような美というものへの執着は捨てきることもできないのであろう。
これは、いい加減に扱えば、手痛いしっぺ返しを受けることになる。しっぺ返しで済めばいいが、致命的なダメージになる可能性もあり得る。例えば、日本という国の価値が損なわれてしまったという絶望感の蔓延ということである。国家の在り方について何も考えていないような者には、あまり影響はないかもしれないが、真剣に考える者において、国家の運営を担うような者の間において、そのような絶望感が広まるとすれば、深刻である。
このような、伝統の積み重なりの美しさに対する執着心の性質にかんがみて、国家の安定的な運営という観点から、男系男子を維持するべきという立論は、十分成り立つであろう。
男系男子論者といってもピンきりであるが、小堀桂一郎氏の論には、このことが自覚されているように感じられる。氏の主張する「道理」ということ、そして、「道理」の担い手は、皇室ではなくて、力ある賢明な臣下であるという認識、また、氏が、一般の国民ではなく政治家をその主張の相手先としている点など、まさにこのことの表れではないか。
したがって、女系容認に踏み切るのであれば、どうしても、それなりの覚悟が必要となるのである。まずは、男系男子で続いてきたことの伝統の重みを踏まえなければなるまい。そして、その伝統の重みに見合うだけの価値というものを見出し、それを踏まえる必要があるだろう。それは結局、皇室というご存在の意義、皇室と日本人との関係の本質を見極めるということにほかならないはずである。













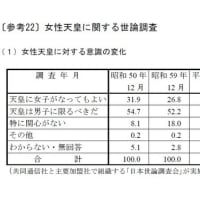







まあ、それは置いといて、確かに男系重視派の人たちは、何故、男系なのか?という理由付けがイマイチなような気がします。もちろん、全く理由付けしていないとは思いませんが...伝統が伝統が、だから男系なのだ...ってのが多いような気がします。
これは私の考えなんですが、生物学的に見ると、今上天皇と中世や古代の天皇とは、何百分の一、何千分の一、何万部の一しか継承していないんですよね、男系女系の両方で見れば、当たり前のことですけど。よって、生物学的な血が繋がっているという面だけでは、皇位の継承の理由には、ならないような気がするんですよね。よって、愛子様と皇胤との確証がない一般人の方との間の子供(女系の子供)が、血が繋がっているから天皇になっても良いじゃない、ってのは違うと思うんです。私は、それが男系に拘る一つの理由だと思っているんです。
両親の系統で見れば、一見、歴史上、関係の無いように見える有名人同士が、血が繋がっているということがあります。例えば、悲運の武将の浅井長政を見れば、浅井家というのは滅亡してしまったのは有名ですけど、実は、男系女系での両方から血の継承を見ると、ありとあらゆる公家や武家が、浅井長政の子孫だったりする。徳川家康と明治天皇は全く関係無い様に思えますが、実は、明治天皇は徳川家康の子孫の一人でもある。
+--浅 井 氏 の 末 裔--+
http://www5e.biglobe.ne.jp/~togetsu/chacha/allazai.html
つまり、男系と女系の両方で、天皇の先祖を見れば、天皇から一般の農民まで殆ど全部が先祖になるかもしれません。
http://www.kct.ne.jp/~kshimizu/index.html
これでは、世襲制を基本とする皇位継承において、皇室の貴種性が保てないような気がするんです。だったら、世襲制じゃない大統領制で良いじゃないかと...
むろん、男系でだけで見ても、現在の一般人に多くの天皇の子孫がいるでしょうが、少なくとも、今上天皇陛下の先祖を遡るようなことをした場合に、男系だけで見ると、系図上、何代遡っても、一人の皇族や天皇に限定されるわけですが、男系女系の両方で天皇の先祖を見た場合、天皇の出自の概念が広がりすぎて崩壊してしまうように思うんです。
現在、皇室の方々やその周辺の方々が、どういうふうに思ってらっしゃるかは分かりませんが、ある高貴な方にメールしたら、はっきりとした解答はもらえませんでしたが、皇位継承は男系だけと思っているようです、おそらく。だからこそ、神社本庁が男系厳守を宣言したり、皇族や華族との繋がりが深い議員さんが男系厳守を言明されているんでしょう。
ちなみに、男系継承ではなく、ユダヤ人みたいに女系継承で皇位継承が行われていたら、当然、私は女系継承オンリーでの一系主義に拘っていたと思います。
しかし、人口は当時の方が少なかったであろうから、共通の先祖というものが、実は、かなりの数あったのであろうと思います。
このように考えると、高貴な家柄とか、由緒ある家系という概念というのは、確かに、怪しげになってしまいますね。
なぜ、いままで続いてきたシステムが男系男子であったのか、その理由が重要である、というご意見に賛同します。しかし、「男子限定」というそもそもPCでない規定の理由に関しておおっぴらに議論するのは鬱陶しい話につながるので避けられているのでしょう。そこらへんが傍から見ていてもどかしく感じたりもします。
思うに、皇室が変化する時というのは、社会の変化が皇室内部へ浸透した結果、自ずともたらされるものであると思います。例えば、華族からお嫁さんを迎える、というお約束を変えて華族でない名門のお嬢さんや高級官僚のお嬢さんをお迎えすることになったり、子弟を海外へ遊学させたり、というのは、もともとは皇室外の国民の意識と価値観の変化によるものだとおもうのです。
現在の国民の価値観からいって、男子限定、というのはありえないし、また逆に、イギリスのように男女完全平等、というのも現実として、なんとなくそぐわないと思います。だとすると、国民意識の投影である皇室の姿も、自然にこれに従うのではないかと僕は思います。
皇室の在り方については、国民の意識と価値観の変化の影響を、確かに受けるものなのでしょうね。
それは必ずしも同化とは異なるもので、むしろ理想を託されることもあるようにも思われますが、少なくとも日本人の心にしっくりと来るものであるべきなのでしょうね。
ただ、皇位継承の問題については、その選択肢を選ぶにしても、何となくすっきりとはしないことになるのではないかとも思われ、そういう意味で大きな問題であり、どうなるのだろうと、心配です。
結局は、なるようにしかならないのでしょうけれども、未来というのは、本当に予測しがたいですね。