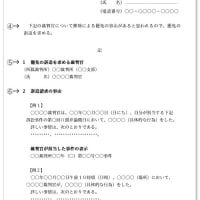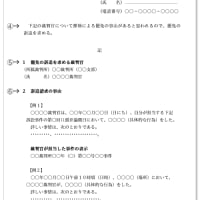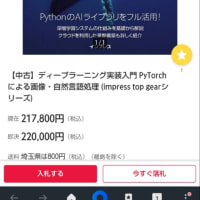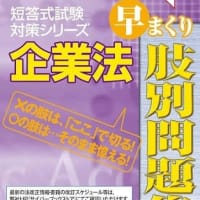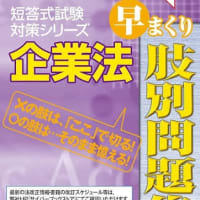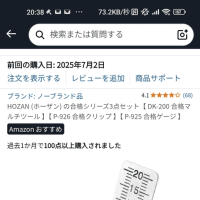以下は「TCP/IPプロトコル群におけるRFC 3168(Explicit Congestion Notification, ECN)」に関するネットワークスペシャリスト試験対策の選択式・穴埋め・誤文訂正問題(全10問)です。
■ 問題 1
RFC 3168が定義している主な技術はどれか。
- A. IPアドレスの自動割り当て
- B. 暗号通信の仕様
- C. 明示的輻輳通知(ECN)
- D. 再送制御方式
【正解】C 【解説】RFC 3168はExplicit Congestion Notification(ECN)を定義した文書である。 【穴埋め】RFC 3168は「明示的______通知(ECN)」を定義している。→ 輻輳 【誤文訂正】
- A:DHCPに関連
- B:TLS/SSLなど別RFC
- D:TCPの機能
■ 問題 2
ECNが有効な場合、ネットワークが輻輳していることを通知する手段はどれか。
- A. パケット破棄
- B. ヘッダのビット設定
- C. ARPブロードキャスト
- D. 再送要求
【正解】B 【解説】ECNはパケットを破棄せずにIPヘッダとTCPヘッダに特定のビットを設定することで通知する。 【穴埋め】ECNは「ヘッダの______設定」により通知される。→ ビット 【誤文訂正】
- A:従来のRED方式
- C:ARPは別機能
- D:TCPによる再送とは異なる
■ 問題 3
ECNの導入により期待される主な効果はどれか。
- A. 帯域幅の削減
- B. 通信の暗号化
- C. パケット損失の回避
- D. IPアドレスの増加
【正解】C 【解説】ECNは輻輳の早期通知によりパケット損失を回避し、ネットワーク効率を向上させる。 【穴埋め】ECNは「パケット______の回避」に寄与する。→ 損失 【誤文訂正】
- A:帯域そのものは変わらない
- B:暗号化とは無関係
- D:IPv6等に関連
■ 問題 4
RFC 3168に基づくECNの導入にあたって、対応が必要な機器はどれか。
- A. DNSサーバ
- B. ルータ
- C. メールサーバ
- D. DHCPサーバ
【正解】B 【解説】ECNはルータが輻輳を検出し、対応するビットをセットする必要がある。 【穴埋め】ECN対応には「______」の機能変更が必要である。→ ルータ 【誤文訂正】
- A/C/D:ECNと直接関係しない
■ 問題 5
IPヘッダのどのフィールドにECN用ビットが含まれているか。
- A. バージョン
- B. ヘッダ長
- C. Type of Service(ToS)
- D. フラグメントオフセット
【正解】C 【解説】ECNはIPヘッダのToS(後のDSフィールド)の下位ビットを利用する。 【穴埋め】ECNは「ToS(DS)フィールド」に「______ビット」を含む。→ 下位 【誤文訂正】
- A/B/D:ECN用ビットは含まれない
■ 問題 6
ECNが動作するには、通信の両端のホストがどのように設定されている必要があるか。
- A. 片方のみ対応
- B. どちらもECN非対応
- C. 両方がECN対応
- D. TCPのみ有効
【正解】C 【解説】ECNは送信元と受信先の両方が対応している必要がある。 【穴埋め】ECNは「通信の______」が対応している必要がある。→ 両端 【誤文訂正】
- A/B/D:機能しないか不完全
■ 問題 7
TCPヘッダでECN通知に使われるフラグはどれか。
- A. SYN/ACK
- B. ECE/CWR
- C. URG/FIN
- D. PSH/RST
【正解】B 【解説】ECEは輻輳通知の受信、CWRは輻輳情報の送信済み通知に使用。 【穴埋め】TCPヘッダにはECN用に「ECE」と「______」が定義されている。→ CWR 【誤文訂正】
- A/C/D:通常の制御フラグでありECNとは無関係
■ 問題 8
RFC 3168で定義されているECN対応の確認方法はどれか。
- A. TCPシーケンス番号の一致
- B. ECN対応フラグの交換
- C. DNS名前解決
- D. MTUサイズの自動調整
【正解】B 【解説】通信開始時にECN対応を示すフラグの交換が行われる。 【穴埋め】ECN対応は「ECNフラグの______」で確認される。→ 交換 【誤文訂正】
- A/C/D:ECNとは関係しない
■ 問題 9
ECNの有効性が特に期待される通信の特性はどれか。
- A. 低遅延を必要としない
- B. 再送が頻繁なUDP
- C. 輻輳制御が必要なTCP
- D. 一方向のみのデータ送信
【正解】C 【解説】TCPは輻輳制御を行うため、ECNの通知を利用できる。 【穴埋め】ECNは「______制御」を行うTCPで有効である。→ 輻輳 【誤文訂正】
- A/B/D:ECNとの関連性が薄い
■ 問題 10
RFC 3168が実装される以前のネットワーク輻輳制御の手法はどれか。
- A. ECN
- B. RED(Random Early Detection)
- C. OSPF
- D. IGMP
【正解】B 【解説】REDはパケット破棄によって輻輳を検出していた。 【穴埋め】REDはパケットを「______」ことで輻輳を通知する。→ 破棄 【誤文訂正】
- A:RFC 3168で導入された新技術
- C/D:ルーティングやマルチキャストのプロトコル
「TCP/IPプロトコル群におけるRFC 3168(Explicit Congestion Notification)」に関する問題10問(選択式・穴埋め・誤文訂正形式)を文書に追加しました。次にRFC 768(UDP)やRFC 791(IP)など他の関連文書をご希望であればお知らせください。