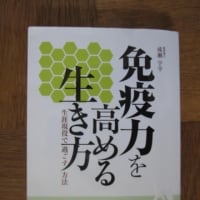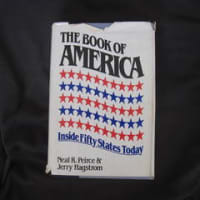折角私のブログにアリバイ証明のような法律学のカテゴリーを作ったので、本棚にある法律学の古い本について書きとめておこう。
我妻栄の「民法講義」(岩波書店)を並べて見た。
新訂前の民法講義Ⅰ民法総則 と同Ⅱ物権法はすでに書き記したが、それ以外に民法講義Ⅴの2債権各論中巻一が教科書として使ったもので私の本棚に残っているものである。あとは卒業してから買ったものである。
新訂民法総則Ⅰ(民法講義Ⅰ)(昭和5年第1刷、昭和40年新訂第1刷、昭和42年第5刷発行 全581ページ)
新訂担保物権法、(民法講義Ⅲ)(昭昭和11年第1刷、和43年新訂第1刷、昭和46年第3刷発行 全678ページ)
新訂債権総論(民法講義Ⅳ)(昭和15年第1刷、昭和39年新訂第1刷、昭和42年第5刷発行 全581ページ)
債権各論上巻(民法講義Ⅴ―1)(昭和29年第1刷 昭和47年第19刷 全217ページ)、
どれだけ丹念に読んだのかと聞かれるとちょっと苦しい。
何故発行の年を書いているかというと、おわかりであろう。ちょっと恥ずかしいが大学を卒業してからでも、ちゃんと法律学の本(教科書)の新訂版を買っておりました、というアリバイ証明のようなものである。
我妻教授が新訂版として最初に上梓した新訂債権総論(民法講義Ⅳ)の前書きを引用しておこう。
「新訂版の上梓に際して
民法講義1からⅦまでを書こうとする私の仕事は、わが国の道路舗装工事に似ている。終点まで完成する前に、初めの方が破損して用をなさなくなり、乏しい予算で、補修工事と新設工事の両面作戦をしなければならない。貫通遣路が完成するのはいつの日か。心細い限りである。
この債権総論の初版を書いたのは昭和十五年である。その時までは、総則・物権法.担保物権と仕事は比
較的順調に進んだ。ところがその後、わが国の経済政策は異常な進路をとり、おびただしい特別立法が制定され、これを債権各論の中にどのように織り込むべきか、全く見通しがつかなくなって私の仕事も進まなくなった。終戦を迎えて後も、この債権各論をとりまく周辺の立法の混乱は容易に沈静しない。
中略
この債権総論にだけ新訂版と肩書をつけることは、実質的には適当でない。しかし、とにかく戦後新たに組み直したものを更に改めた意味でこの肩書をつけることにした。
読者諸君は、この新訂版は、内容においても総則や物権法とやや調子が違うと感じられるであろう。私もそう思う。民法講義のそもそもの目的は大学の講義用テキストであった。それを一通り完成したら、さらに一層詳しいものを書くつもりであった。しかし、今日となっては、もはやその計画に従うことはできない。
私の心の中にあるいろいろの野心がその時その時に私を動かして、一貫した調子を持ち続けることを妨げているらしい。わが国の道路補修工事が、時には穴を埋めるだけであったり、時には一部分のやり直しであったり、時には調子の違ったコンクリートやアスファルトエ事であるのと似ている。
ともあれ、学者的生命の続く限り、一貫した本式の舗装工事の完成を最終の目的として、たゆまない歩みを続けるつもりである。昭和三十九年一月校正を終る日 我妻栄」
この新訂版債権総論の発行後上記のとおり、債権総論および担保物権法の新訂版を出しておられる。
先日、大学の図書館に久し振りに行って見た。大学祭の準備でにぎわっている中、図書館の中には静かに法律学の本を読んでいる学生も多かった。見るともなしに学生が読んでいる本を見ると、昔のように民法は我妻栄教授の民法という風景ではなかった。今や誰もが内田貴教授の民法の教科書を読んでいるようであった。私も数年前に買って持っているが、最近の教科書の何とわかりやすく、面白く書いていることか。ふんだんに例題や判例をのせて実にわかりやすく書いてある。
我妻教授はそういう努力をされなかったかというと決してそうではない。講義は面白かったようであるし、また後に「民法案内」という実にわかりやすいシリーズを出しておられる。
これについてはまた書くことにしよう。
以上
我妻栄の「民法講義」(岩波書店)を並べて見た。
新訂前の民法講義Ⅰ民法総則 と同Ⅱ物権法はすでに書き記したが、それ以外に民法講義Ⅴの2債権各論中巻一が教科書として使ったもので私の本棚に残っているものである。あとは卒業してから買ったものである。
新訂民法総則Ⅰ(民法講義Ⅰ)(昭和5年第1刷、昭和40年新訂第1刷、昭和42年第5刷発行 全581ページ)
新訂担保物権法、(民法講義Ⅲ)(昭昭和11年第1刷、和43年新訂第1刷、昭和46年第3刷発行 全678ページ)
新訂債権総論(民法講義Ⅳ)(昭和15年第1刷、昭和39年新訂第1刷、昭和42年第5刷発行 全581ページ)
債権各論上巻(民法講義Ⅴ―1)(昭和29年第1刷 昭和47年第19刷 全217ページ)、
どれだけ丹念に読んだのかと聞かれるとちょっと苦しい。
何故発行の年を書いているかというと、おわかりであろう。ちょっと恥ずかしいが大学を卒業してからでも、ちゃんと法律学の本(教科書)の新訂版を買っておりました、というアリバイ証明のようなものである。
我妻教授が新訂版として最初に上梓した新訂債権総論(民法講義Ⅳ)の前書きを引用しておこう。
「新訂版の上梓に際して
民法講義1からⅦまでを書こうとする私の仕事は、わが国の道路舗装工事に似ている。終点まで完成する前に、初めの方が破損して用をなさなくなり、乏しい予算で、補修工事と新設工事の両面作戦をしなければならない。貫通遣路が完成するのはいつの日か。心細い限りである。
この債権総論の初版を書いたのは昭和十五年である。その時までは、総則・物権法.担保物権と仕事は比
較的順調に進んだ。ところがその後、わが国の経済政策は異常な進路をとり、おびただしい特別立法が制定され、これを債権各論の中にどのように織り込むべきか、全く見通しがつかなくなって私の仕事も進まなくなった。終戦を迎えて後も、この債権各論をとりまく周辺の立法の混乱は容易に沈静しない。
中略
この債権総論にだけ新訂版と肩書をつけることは、実質的には適当でない。しかし、とにかく戦後新たに組み直したものを更に改めた意味でこの肩書をつけることにした。
読者諸君は、この新訂版は、内容においても総則や物権法とやや調子が違うと感じられるであろう。私もそう思う。民法講義のそもそもの目的は大学の講義用テキストであった。それを一通り完成したら、さらに一層詳しいものを書くつもりであった。しかし、今日となっては、もはやその計画に従うことはできない。
私の心の中にあるいろいろの野心がその時その時に私を動かして、一貫した調子を持ち続けることを妨げているらしい。わが国の道路補修工事が、時には穴を埋めるだけであったり、時には一部分のやり直しであったり、時には調子の違ったコンクリートやアスファルトエ事であるのと似ている。
ともあれ、学者的生命の続く限り、一貫した本式の舗装工事の完成を最終の目的として、たゆまない歩みを続けるつもりである。昭和三十九年一月校正を終る日 我妻栄」
この新訂版債権総論の発行後上記のとおり、債権総論および担保物権法の新訂版を出しておられる。
先日、大学の図書館に久し振りに行って見た。大学祭の準備でにぎわっている中、図書館の中には静かに法律学の本を読んでいる学生も多かった。見るともなしに学生が読んでいる本を見ると、昔のように民法は我妻栄教授の民法という風景ではなかった。今や誰もが内田貴教授の民法の教科書を読んでいるようであった。私も数年前に買って持っているが、最近の教科書の何とわかりやすく、面白く書いていることか。ふんだんに例題や判例をのせて実にわかりやすく書いてある。
我妻教授はそういう努力をされなかったかというと決してそうではない。講義は面白かったようであるし、また後に「民法案内」という実にわかりやすいシリーズを出しておられる。
これについてはまた書くことにしよう。
以上