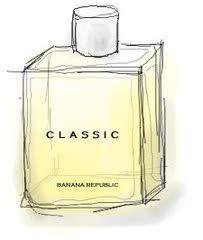つれて逃げてよ
ついておいでよ
夕暮れの雨が降る 矢切の渡し
親のこころに背いてまでも
恋に生きたいふたりです
ご存知、演歌の名曲「矢切の渡し」、
つい最近なんだけど、
この曲をちあきなおみさんが「演歌の花道」で歌っている姿を見て、
(いや、YouTubeってほんとすごいっスね)
それ以来この「♪つれて逃げてよ~」が
この頭から離れなくなってしまって、
ジムでもインターバルの最中に、
思わず口ずさんでしまったりと、
なかなか困ったワタクシなんですけど。
正直言うと、
今までは「こんな辛気臭い歌はちょっと…いやだ」
なんて思ってたですよ、この曲。
それがさぁ、やっぱりちあき姐さんはすごいや。
あの独特の低いボーカルに狂気一歩手前の情景をかまされたら、
このワタクシなんぞひとたまりもありませんでしたね。
もうこの自分自身が、
すっかり「親のこころに背いて駆け落ちするんだ」
ってな気持ちになってしまいましたので、
はい、本日「矢切の渡し」で江戸川を渡りに行って来ました。
これで本当に駆け落ちの相手なんかがいればね
それはまたものすごくかっこいいんだろうけれども、
こんな物好きに付き合ってくれる人なんて
そうはいませんよ。
もちろんひとりで行って来ましたよ、柴又。
実は、うちから柴又までは、
だいたい30分くらいあれば着いてしまうので、
今回も特別新鮮な感じはしないと言えばしないかな。
でも、この「矢切の渡し」に乗るのは今日が初めてなので、
かなり期待しながらの出発となりました。
押上駅から京成電車で高砂まで出たら、
今度は金町行きに乗り換えてひと駅で柴又でございやす。
京成電車に乗り込んだ時点ですでに庶民派の匂いを醸し出す
あの独特のいなたい雰囲気が好きなんだけど、
金町行きの支線に乗り換えたとたん、
買い物かごを抱えたおばちゃんや、
太い縦縞スーツを着た親父なんかが電車内で
くつろいでいたりなんかするものだから、
もうこちらの気分も「男はつらいよ」の映画の中に
入り込んだ気分で盛り上がってまいります。
柴又の駅を出てすぐのところにある、
安っぽい黄色のテント看板のコーヒーショップ
その名も「さくら(ハートマーク)」で
地元のおばちゃんと並んでコーヒーを
ものすごく飲みたかったんだけれども、
本日の目的は「矢切の渡し」。
江戸川の川原でトイレ我慢するのはたまらないので、
このさくらさんのコーヒーは帰る時までお預けであります。
ワタクシはカフェインと言うやつにめっぽう敏感で、
コーヒーを飲み終わる前にはもう尿意を催しますのでね。
そこから柴又帝釈天までの参道には
あの「とらや」をはじめ、名物の草だんご屋が
それこそ軒を連ねて客を待ってるんだけれども、
この草だんごって、確かに美味しいとは思うけども、
いかんせんなかなかにイイ値段の代物なんだよね。
お土産にするにはまぁコレくらいの大きさだろ、
って言うくらいの、広げた大人の手のひらより
ちょっと大きいくらいの箱でもう2千円とかするんだよ。
オラには買えねぇ。
値段ももちろんだけれども、
それよりも、
買ったひと箱全部ペロリと食べてしまいそうで。。。(笑)
帝釈天の帝釈堂が見えて来ると思うのが、
門の影からあの源公が竹箒を持ってひょっこり現われ、
そして帝釈堂の奥からは御前様が説教のひとつでも
たれそうな顔でこちらに向って歩いて来る。
そんなことは映画の中だけしかない事は当たり前なんだけど、
ふとそんな思いに駆られるほどに、
今でも柴又はあの映画そのままの
風情がそっくりそのまま息づいているんだよね。
町も人も、とにかくのどか。
雑多な東京下町の懐の深さに見とれてしまいますよ。
その帝釈天から江戸川の堤防へ向って10分ほど歩くと、
いよいよ本日のメインイベント「矢切の渡し」。
シロツメグサが群生する川原は午後の陽が当たって、
もうため息の出るくらいに平和な風景。
おまけに渡しの桟橋のすぐ隣では
地元の小学生の草野球大会が開かれていて、
これではちょっとばかし、
人目を忍んで駆け落ちする雰囲気ではないですよ。(笑)
で、これまたいなたい桟橋で船が出るのを待つんだけど、
風に波打つ川面が無性になんていうかこの日本人魂ってやつを
揺さぶってくれたりなんかしちゃうわけですよ。
ここに来るまでずっとちあき姐さんの「矢切の渡し」を
聴き続けていたので、なんだかもうすでに涙が出そうな感じ。


対岸の矢切から人を乗せて、
渡し船がようやくこちら柴又の桟橋に帰ってくる。
ここでとても嬉しい事発見。
事前に調べた限りでは、
この「矢切の渡し」は個人経営の渡し船だそうで、
船賃は片道100円。
基本は手漕ぎなんだけど、
川風が強くて波があるときや、
観光客が多くて順番待ちだったり、
また一日ずっと船を漕いでいると疲れるのか、
最後の方の時間になるとモーター船になってしまうそうで。
でも、今日は人もまばらで川風も静か、
それでお見事手漕ぎ船にての渡しとなりました。
うひょ~、すっごく、素敵♪
もう、乗船の頃には興奮してドッキドキものだったよ~。
で、船は桟橋を離れて揺ら揺らと道行きの旅へと繰り出します。(笑)

船はおよそ10分ほどで対岸の矢切の桟橋に着きます。
今渡ってきた江戸川を挟んで、こちらは千葉県松戸市、
柴又側と違って、周りには何にもなくて、
観光客相手のお土産やおでんなどを売る屋台店が一軒あるのみ。
おまけにその屋台の経営者は船の船頭さん。
お父さんが柴又側へ行っている間の店番は、
小学生くらいの男の子、おそらく息子さんだよね。
いいなぁ、こういうの。
川を挟んで家族で渡し船の経営なんてね。
ウラヤマシでございますです。
こちらへ渡ってからようやく、
船に乗る前、柴又の桟橋から遠くに見えていた
旗の正体がわかりました。
この旗が揚がっているのが、
渡し船の営業中の印なんだって。
ほぉ~、そうなのか~。
と、ワタクシ妙に気に入ってしまいます。

見すてないでね
捨てはしないよ
北風が泣いて吹く 矢切の渡し
噂かなしい 柴又すてて
舟にまかせる さだめです
それははたして、恋情なのか愛情なのか。
演歌というジャンルが描き出す世界観は、
今の時代、場所が場所なら、
それは時として、差別、男尊女卑、セクハラ、パワハラ、
とかなりひどい状況を思い浮かべてしまうんだけれども、
それでも、フィクションの世界と言えども、
演歌の世界観がこうも情というものを、
ひたひたと炙り出すのは何とも不思議と言うか、
やはり快感に近いものがありますな。
この歌が描く心情の風景、
人目を忍んで船に乗り駆け落ちをするふたり。
その事を追体験するということではなくて、
(っていうか、そんなこと無理だしね。)
そっくりそのままとは言わないまでも、
一応は歌のモデルとなっている場所に自分を置く事で、
演歌の世界で泣きの世界に仕立てあげられる
この歌を聞いた自分の中でこころのひだが
ざわざわと蠢(うごめ)く意味を確かめてみたかったんだよね。
夕暮れの川風が船を揺らして、
遠くで薄暗い雲が流れて、
船頭さんの漕ぐ艪(ろ)の音が、
ほんとうにギッチラ ギッチラ ギッチラコっていうこと、
船に乗る誰もが黙っているので、
揺れる船の軋(きし)む乾いた音が
この足元に響くこと。
日本の湿った情緒の奥に根付く、
決して陽を見ることのないエロス。
それはどんな色合いをしていて
どんな匂いを放っているのか。
若輩ものの自分ではてんでわかりませんけど、
それでも薄っすらと感じるそのエロスってやつ。
それはゆっくりと口の中で溶けてゆく
甘味な飴玉のようでありました。

帰りの船には地元の人たちも乗り込んでいたので、
(まぁ、それが本来の渡し船ですが)
船もかなり重く船頭さんも本腰を入れて漕ぐ、漕ぐ。
ギッチラ ギッチラ ギッチラコ~
これで、本当に身も焦がれるほどに好きな相手と
この川を渡る事が出来たなら、
それはどんなにいいものだろうか。
などと、僕はひとりにんまりと考えていました。
この船に乗る事が出来る最大人数は31人って
船の中に書いてあったんだけれども、
そんなには好きな人っていうのはいないなぁ。
でも今冷静に数えてみて、
んー、ひとり、ふたり、三人、四人、。。。
っていうのは冗談なんだけれども、
でもね、本気で恋焦がれるその相手と共にいつの日か、
また、この「矢切の渡し」で再び川を渡りたいなぁ。
なーんてね、柄にもなく考えたりしたわけです。
でも、その頃には
矢切桟橋の屋台で留守番をしていた
あの息子さんが船頭になってたりしてね。
っていうか、
自分はいつまでしぶとくがんばるんだよ。
って話ですわ。
どこへ行くのよ
知らぬ土地だよ
揺れながら艪が咽ぶ 矢切の渡し
息を殺して 身を寄せながら
明日へ漕ぎだす 別れです
矢切の渡し 作詞・石本美由起 作曲・船村徹