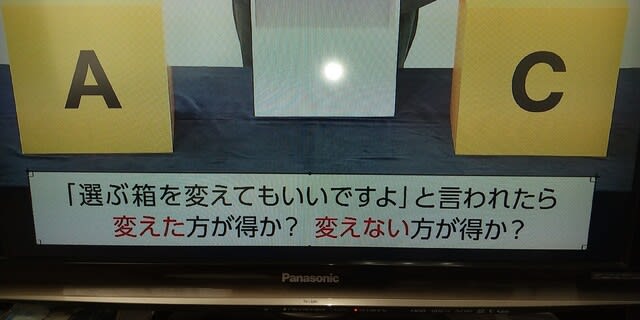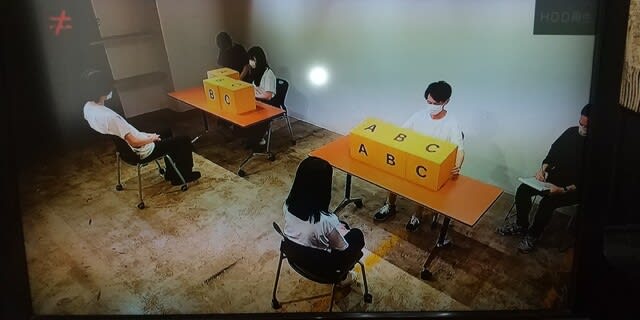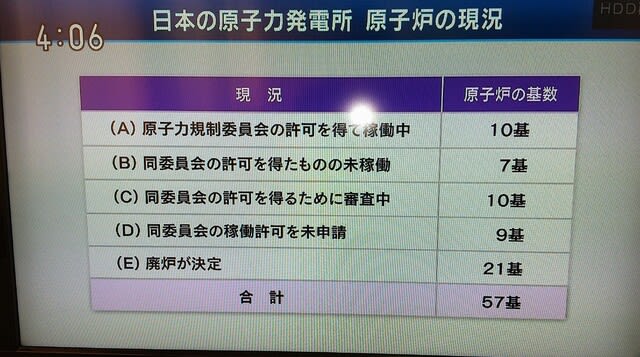「強い円」はどこへ行ったのか 唐鎌大輔著 日経 2022年9月8日第1刷発行 を読んだ。以下はそのダイジェストと感想である。

著者はみずほ銀行のアナリストであり、50年ぶりの円安の原因を中長期的視点から分析する。それによると、現在の円安は
①成長率、
②金利、
③需給
の三つの面から見て一定の正当性があるとする。①②については全く異論がない。面白いのは ③の需給関係についての分析である。
円はこれまで「安全資産」とされ、何か危機が起きるたびに買われてきた。財政赤字であるにもかかわらず円が「安全資産」とされた最大の理由は、日本が「世界最大の対外純資産国」だからである。いざとなれば対外資産を売ることができる。だから円は安心だとされてきた。
短期的な需給に関しては第一に、最近、証券投資より直接投資の方が上回っている点が注目される。なぜなら証券投資に比べて直接投資はすぐには売却が難しく、それがドル売りにつながらないからである。
第二に、日本の国際収支構造に変化が起きている可能性もあると著者は指摘する。これまで日本はいわゆる「成熟した債権国」であった。現在貿易黒字こそ失われてはいるものの、それを補って余りある第一次所得収支の黒字があり、こうした経常収支の黒字が円買いを支えてきた。
ところが、ここにきて変化の兆しがみられるという。すなわち、第一次所得収支は黒字であるものの、資源高から貿易赤字が膨らんで経常収支が赤字になるいわゆる「債権取り崩し国」にシフトしつつあるというのである。まだ明確に移行したとは言えないが、そうした可能性についても視野に入れておく必要があるという。
もっとも面白かったのは「キャピタルフライト」に関する分析である。現在、岸田内閣は盛んに「貯蓄から投資へ」というキャンペーンを張っている。しかし、この政策は危険がいっぱいだという。
たしかに2000兆円に及ぶ家計の金融資産が株式市場や債券市場に流れ込めば、金融市場は活況を呈する。しかし、貯蓄されたお金が日本の金融市場に流れる保証は一つもない。むしろ成長率の高い海外に流れ出す可能性が高い。
もしそうなれば二つの問題が起きる。
第一に、家計がキャピタルフライトを行えば、円安は一気に加速する。いま日本にとって一番怖いのは、家計が日本の将来について悲観的になり、一気にキャピタルフライトを起こすことである。実際、私の周りにはそうした視点からドル買いをしている人が何人もいる。私自身も円で持っていることのリスクを避けるために、資産の一部はドルや金に交換している。もし同じ行動を日本の多くの人が取り始めたら、円は一気に暴落する。
第二に、「貯蓄から投資へ」が実現すると、日本国債はいったい誰が買うのかという問題が生じる。現在、国債を買っているのはほとんどが金融機関であり、その原資となっているのは国民の貯蓄である。それがなくなれば国債の買い手は不在になる。岸田首相はこの点をどう考えているのだろうか? ぜひ問うてみたい。
黒田日銀総裁は、円安は日本にとって益するところが大きいという。間違いである。円安が国益であるはずがない。そもそも円の価値には二つある。国内的な価値と対外的な価値である。国内的価値とはすなわちインフレを起こさないということであり、対外的な価値とは為替レートで示される価値である。
日本に閉じこもっている間は国内的な価値だけを見ていればよいが、グローバルな視点に立てば対外的な価値を守ることも重要だ。円安にすれば輸出企業の利益が自動的に増える。自動的に増えるから努力をしなくなる。それが企業の体力を弱める。まるで麻薬と同じだ。
日銀は目先の利益にとらわれることなく、長期的な視点から通貨価値の安定を図る義務がある。政府からの独立性を失った今の日銀にそれを求めるのは無理かもしれないが。