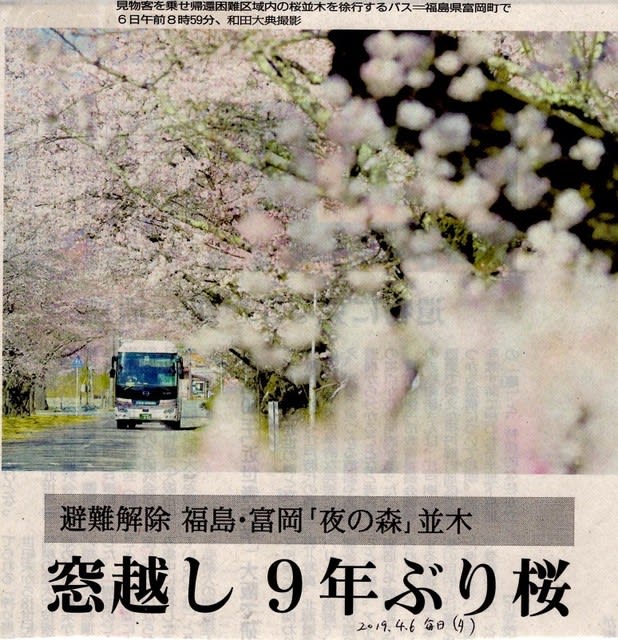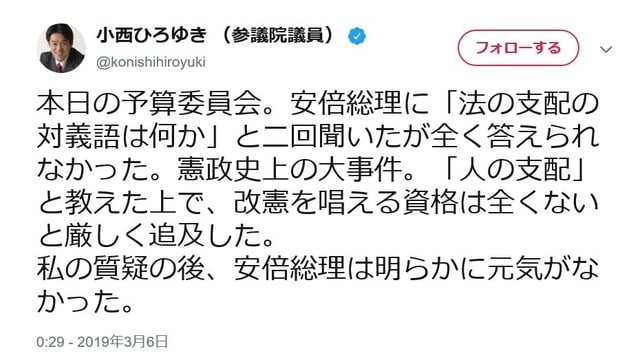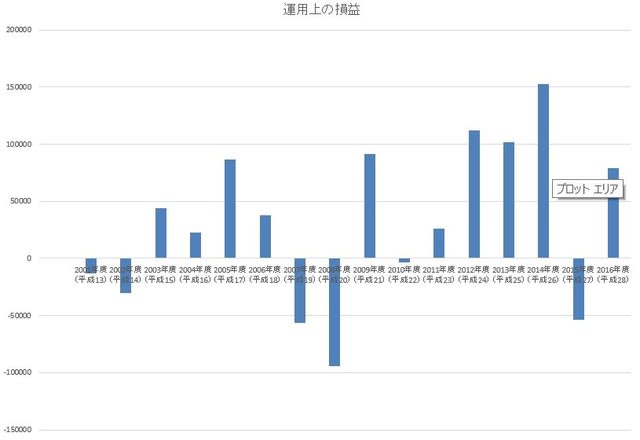橋下徹氏が新しい本を出した。そこには沖縄の発展と米軍基地問題を解決するための政治的ロードマップが記されている。事の善悪は別にして、とにかく面白い。
沖縄を発展させるために、沖縄は「東洋一の観光リゾート」を目指すべきだという。その方向性さえ了解されるならば、あとはどのように実現させるかのプロセスの問題となる。そのためには
1.とりあえず辺野古への米軍基地移設を認める。
2.返還された普天間480ヘクタールに、カジノを含む統合型リゾート(IR)を誘致し、海外から富裕層を集める。
3.観光客をわんさか集めるために沖縄を経済特区にし、消費税をゼロ(または限りなくそれに近い率)にする(一国二制度)。沖縄は本土が嫌がる基地負担を引き受けているのだから、それくらいのことを政府に要求するのは当然だ。
4.人が集まるようになったら、その人たちが沖縄全体にお金を落とすように、沖縄南北鉄道を建設しアクセスをよくする。いまある高速道路の上にモノレールを走らせれば、2000億円もあればできる。
5.沖縄の魅力を高めるための街づくりを実施し、京都、ローマ、パリ、ベネチアなどのような他にはない特色を持たせる。そのためには、現在交付されている年間3000億円の沖縄振興補助金を、上に述べたようなビジョンに向けて投資する。
それだけではない。より本質的には沖縄が引き受けている米軍基地を、本土もフィフティ・フィフティに引き受けるような仕掛けも必要である。そのためにはどうするべきか。それはここでは書くまい。本書はケンカ上手な政治家橋下徹氏の面目躍如の力作である。
沖縄を発展させるために、沖縄は「東洋一の観光リゾート」を目指すべきだという。その方向性さえ了解されるならば、あとはどのように実現させるかのプロセスの問題となる。そのためには
1.とりあえず辺野古への米軍基地移設を認める。
2.返還された普天間480ヘクタールに、カジノを含む統合型リゾート(IR)を誘致し、海外から富裕層を集める。
3.観光客をわんさか集めるために沖縄を経済特区にし、消費税をゼロ(または限りなくそれに近い率)にする(一国二制度)。沖縄は本土が嫌がる基地負担を引き受けているのだから、それくらいのことを政府に要求するのは当然だ。
4.人が集まるようになったら、その人たちが沖縄全体にお金を落とすように、沖縄南北鉄道を建設しアクセスをよくする。いまある高速道路の上にモノレールを走らせれば、2000億円もあればできる。
5.沖縄の魅力を高めるための街づくりを実施し、京都、ローマ、パリ、ベネチアなどのような他にはない特色を持たせる。そのためには、現在交付されている年間3000億円の沖縄振興補助金を、上に述べたようなビジョンに向けて投資する。
それだけではない。より本質的には沖縄が引き受けている米軍基地を、本土もフィフティ・フィフティに引き受けるような仕掛けも必要である。そのためにはどうするべきか。それはここでは書くまい。本書はケンカ上手な政治家橋下徹氏の面目躍如の力作である。