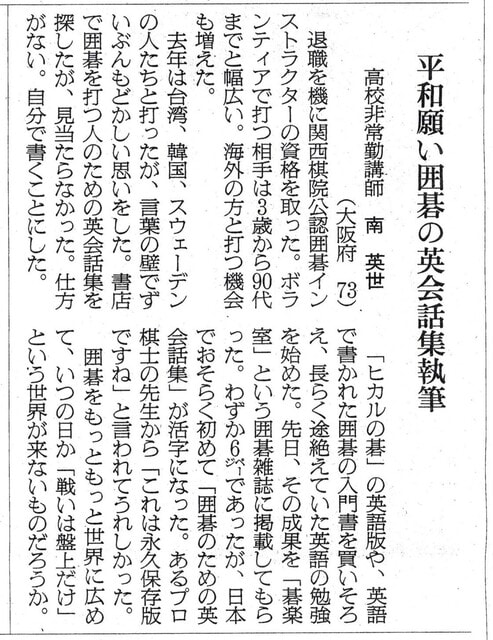テストの採点方法に変化が起きている。いまやコンピュータによる自動採点の時代になったようだ。現在、社会科職員室で従来のように手作業で採点しているのは私一人である。他の先生方は大阪府が導入した自動採点ソフトを使っている。
手順は
① 回収した答案をスキャナーで読み取らせる。
② コンピュータによって自動で〇×がつけられる。
③ 先生方はそれらの答案をパソコンの画面に映し出して点検する。
④ 点検が終わって〇×が付いた答案(答案原本ではない)を印刷し、生徒に返却する。
採点のために先生方が赤ペンを持つ必要はない。パソコンの画面とにらめっこするだけである。初めて職員室の全員がパソコンの画面を見つめながら点検している姿を見た時は衝撃を受けた。「時代が変わったな―」と。ただし、生徒の字は乱雑だから、まだ人間の眼で確認する必要があるらしい。
一方、私はと言えば相変わらず書かすことにこだわり続けている。教員になりたての頃から1問100点の論述を課してきた。そのうち1問50点の論述と通常の客観テストの2本立てにするようになったが、ともかく書かせることにこだわり続けてきた。
こだわった理由は簡単である。「わかる」ということは「他人に説明できること」だと思うからである。点としての知識ではなく、点と点を結び付けて一つのストーリーとして理解してほしいからである。さらに言えば、授業を聞く態度をそのように変えたいからでもある。
今回(6月)の中間考査の答案を採点していて、生徒の書く力(=考える力)がますます弱くなっていると感じた。大学共通テストに続いて普段の定期考査までコンピュータ採点になったら、この先一体どうなるのか。
そこで、時代の流れに抗うことに決めた。
「10月の期末考査は1問=50点の大きなテーマを2問出題する。1問は知識を問い、もう1問は思考を問う。字数制限はない」
と宣言した。
今学校現場は多忙である。しかし、多忙を理由にテスト問題の採点のやりやすさを優先するのは違うのではないか。論文試験の採点は神経をすり減らすが、書かせるスキルを身につけさせることはその後の人生の大きな財産になる。普段の授業を通して生徒に何を伝えたいのか。入試問題さえ解ければそれでいいのか。教育の根本が問われている。採点の労を厭っている場合ではない。時代の流れに抗うこんな教員が一人くらいいてもいいのではないか。