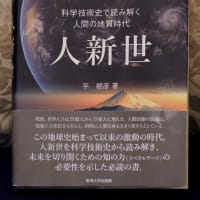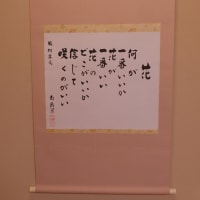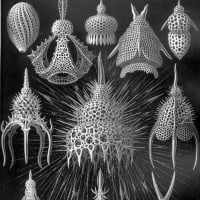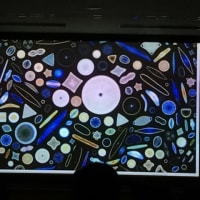東京ではコロナウイルス感染が身近にせまっているという危機感が出てきました。この災禍の影で、本日政府から、ひっそりと重大な人事が発表されました。
日本医療研究開発機構(AMED)の新理事長に末松誠・現理事長は再任されず、三島良直氏(70)が就任することに決まったという発表です。
三島氏は東京工業大学の学長経験者ですから、おそらく人物として大変優れた方なのだろうと思います。三島氏に直接お会いしたことはないですので、私は氏について何か言う立場にはありません。しかし、三島氏の専門は材料工学であり、医学分野での評価はまったく未知数です。
対して、医学が専門で、NIH(米国)やNHS(イギリス)など、世界の医学研究の予算配分機関のトップたちと個人的なつながりをもって連携し、日本の省庁間の壁を超えて基礎から応用まで一気通貫の医療研究改革をしようと努力し、現下のコロナウイルス禍にあっては直接政治に働きかけ、精力的に対応してきた末松誠理事長(62)。
今後、AMEDの司令塔である健康・医療戦略室は、AMEDをどのようにしようとしているのでしょうか。医学が専門ではない新理事長をトップに据えることで、各省庁(文科、厚労、経産、総務)から出てきた予算をそのままAMEDに執行させることが、より容易にできるようになるかもしれません。しかし、それならAMEDが設立される前の状況とさして変わらず、「患者さんに一日も早く医療研究の成果を届ける」ことも「医療研究の成果で日本の経済を活性化させる」ことも不可能であることは、すでに歴史が証明しています。
あるいは、AMEDの司令塔である健康・医療戦略室が、これからは各省庁の情報を元に確固とした戦略を立てられるようになり、それに応じて細かな予算配分までを自分たちで決め、AMEDが予算執行すればいいと考えているのかもしれません。しかし、それにはごく少人数で構成される健康・医療戦略室が、個々の研究や政策に対して適切な指導力を発揮できるだけの神様級の認知能力や科学的創造力を持つ必要があります。
そんなことは誰がやっても到底不可能なのです。ですから、研究者、官僚、企業人、みんなの知恵を持ち寄る必要があるのです。そこに、医学や医療の専門家を含む600人の職員を擁する予算配分機関としてのAMEDの存在意義があるのではないでしょうか。
AMEDの真価は、予算配分に無駄や重複がないように区分けするのと同時に、研究者の自由な発想を生かして、省庁や分野の壁を超えて柔軟に予算をマージネーションさせるという、相反する2つの要素を専門知識に基づいて融合させ、実行することにこそ発揮されるべきです。そうでないと、真に価値ある研究成果が生まれないからです。また、現場をよく知る人たちが自分たちの頭で考え、責任を持って予算執行するからこそ、最後まで本気の仕事ができ、意味のある成果に結びつくのです。
それには、「異質性と自治が守られた魅力的な組織のなかで、透明性のある自由な議論によって物事を公平に決めていくプロセス、組織運営が欠かせない」と末松理事長は訴えました。
もしも、これからAMEDが本来の役割を果たせなくなった場合、その影響は私たち日本国民の一人一人の将来の医療の質に及ぶものと思います。その原因はAMED側にあるのではなく、政府による今回の決定がその元凶なのだということを、記憶しておかなければなりません。