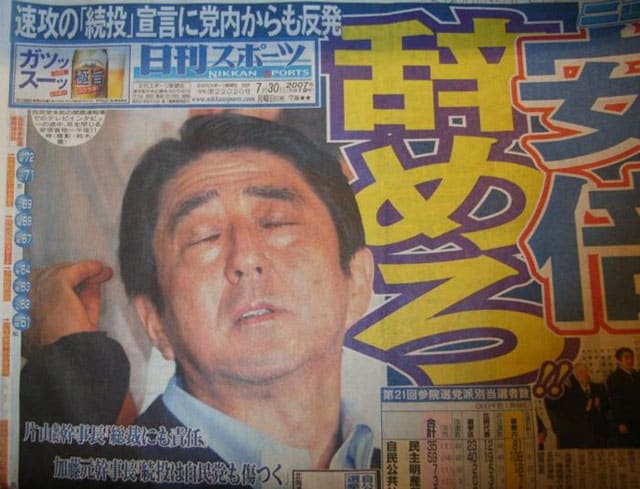こんなこと書くブログではないんですけど。
明日は投票に行きましょう。
「行っても結果は変わらないし」とか「自分には関係ないし」というような若者の声がよく報道されます。
僕が思うに、前者は正しいけど後者は間違っています。
結果を変えようなんて、現実的には無理です。自分の望んだ候補者を当選させようなんてことは、考えなくていいと思います。
しかし、投票率が変わると政治家の考えが確実に変わります。
トータルの投票率が30パーセント、40パーセントであれば、偉い政治家は組織票だけで当選できるので、党内でのご機嫌伺いだけしていればいいんです。一般市民の声なんて聞く必要がありません。
しかし、これが70パーセント、80パーセントとなれば、彼らも組織票だけでは当選できなくなる恐れが出てくるので、普段の支持者以外の声にも耳を傾けざるをえません。
1票を積み重ねれば、投票率は確実に上げることができます。
あと、世代別の投票率というのが今の時代とても重要だと思います。
今の社会保障が年寄りに手厚く若者に薄いのは、政治家が若者をなめているからです。
人数も少ない上、都合のいいことに「自分には関係ない」と言って投票に行かない人が多いので、
若者の声なんて聞かなくても自分たちは政治家を続けられると思っているからです。
逆に年寄りは、人数も多いしみんな投票に行く。この人たちの機嫌を損ねたら議員を続けられないから、誰が当選したとしても年寄りの声は聞くほかないのです。
これが、もし10代20代の投票率が90パーセントなんていうことになったら、どこが与党になったとしても、若い世代に一目置いてその意見を大事にしますし、
「保育園落ちた日本死ね」なんて発言が社会問題になったときに総理大臣は「匿名なので確認のしようがない」なんて木で鼻をくくったようなことは言えません。
政治家の考え方が変わり、社会は確実に変わりますよ。
投票したい人がいないからとか考えなくていいです。白票でも無効票でもいいと思います。
投票は僕たちのこの社会での発言力そのものです。
散歩がてら、明日は投票に行きましょう。
明日は投票に行きましょう。
「行っても結果は変わらないし」とか「自分には関係ないし」というような若者の声がよく報道されます。
僕が思うに、前者は正しいけど後者は間違っています。
結果を変えようなんて、現実的には無理です。自分の望んだ候補者を当選させようなんてことは、考えなくていいと思います。
しかし、投票率が変わると政治家の考えが確実に変わります。
トータルの投票率が30パーセント、40パーセントであれば、偉い政治家は組織票だけで当選できるので、党内でのご機嫌伺いだけしていればいいんです。一般市民の声なんて聞く必要がありません。
しかし、これが70パーセント、80パーセントとなれば、彼らも組織票だけでは当選できなくなる恐れが出てくるので、普段の支持者以外の声にも耳を傾けざるをえません。
1票を積み重ねれば、投票率は確実に上げることができます。
あと、世代別の投票率というのが今の時代とても重要だと思います。
今の社会保障が年寄りに手厚く若者に薄いのは、政治家が若者をなめているからです。
人数も少ない上、都合のいいことに「自分には関係ない」と言って投票に行かない人が多いので、
若者の声なんて聞かなくても自分たちは政治家を続けられると思っているからです。
逆に年寄りは、人数も多いしみんな投票に行く。この人たちの機嫌を損ねたら議員を続けられないから、誰が当選したとしても年寄りの声は聞くほかないのです。
これが、もし10代20代の投票率が90パーセントなんていうことになったら、どこが与党になったとしても、若い世代に一目置いてその意見を大事にしますし、
「保育園落ちた日本死ね」なんて発言が社会問題になったときに総理大臣は「匿名なので確認のしようがない」なんて木で鼻をくくったようなことは言えません。
政治家の考え方が変わり、社会は確実に変わりますよ。
投票したい人がいないからとか考えなくていいです。白票でも無効票でもいいと思います。
投票は僕たちのこの社会での発言力そのものです。
散歩がてら、明日は投票に行きましょう。