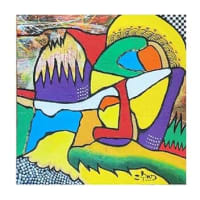NTT廃止議論のxでのバトルはお互い至極真っ当だが国益と自国主義を最大優先して議論を前に進めて欲しい。GDPで2位、かつてJAPAN as no1を経験した日本になんとか戻りたい。1985年当時の日本はGDPランキング2位で世界GDPの12% を占めていた。3位ドイツは5パーセントを占めてぶっちぎりの2位だった。
競争で携帯電話料金が下がったかは疑問の余地がある。競争は極めて大事なのは言うまでも無いが、何よりIOWNを引っ提げて頼もしい予感を抱かせるNTTも世界の巨人に返り咲いて欲しい。つまり国民は競争と世界の巨人に返り咲きの双方が欲しいのだ。そして現実の生活からはNTTが世界の巨人に返り咲く方が生活レベルに直結するのではないか。
これがNTT民営化後に通信3社(NTT、KDDI、SB)を経験したわたしの本音だ。それが結果的には日本の通信事業を底上げし国民の生活を向上させることにつながると考えている。だからNTT法がすでに40年近く経ち、現実に間尺に合わないので世界と戦いづらいと訴えるので有れば聞いてあげればいいじゃないかと思う。NTT法は大きな役割を担ったが世界情勢と国内競争状態を確立してすでにその役割を終えたのだ。
ただし、大きな課題は依然として残りきちんと整理しておかないとやはり禍根を残す。それは地域インフラのボトルネック問題だがそれこそが唯一の残された課題だと割り切って本音で議論したらどうか。
他の議論である外資、安全保障は競合も同じ課題に直面する、だから競合と争う議論ではなく同じ共通課題であるとして方向性を見出せば良い。
ユニバーサルサービスも今はすでに競合との共通課題だ。横綱になった競合はユニバーサルサービスの責務も災害対策もNTTと同様の責務を持つのは当然であると考える。
業務範囲問題はもその淵源は地域インフラのボトルネック問題だから、議論の焦点にはならない。
真の課題が絞れないと最大、唯一の問題である地域インフラのボトルネックに焦点が合わない、現に両陣営は解決案を示していない、そのため自民党PTが出した2025 年NTT法廃止案の実施に 押し切られる可能性が高い。
今最も欠けてるのが国民目線の議論だ。Xではポジショントークの応酬に見える。国民資産論だ、いやそうじゃないといった議論に施設設置負担金まで返せなどと言う場外乱闘まで加わり混乱状態だがこれは国民目線の議論では無いと思う。
わたしはかつて経験した民営化当時のGDP2位に戻ってほしいと子や孫の世代のために切に思う。NTTの衰退と日本の衰退は偶然かどうかは明らかでは無いし特に半導体産業の衰退との因果関係は学者の詳細な研究にまつしかないが強いNTTの不在が少なからず影響していると感じている。
グローバリズムの匙加減を誤ってNTTの活力を奪ってしまった感もあるが、それが競合を生み出し大いなる活性化と繁栄をもたらした。それの功罪、是非を議論していても現実の経済は復興しない。まずNTTが力を発揮しきれないと言うNTT法の枷を外してあげようじゃないか、枷を外して不都合な点を合意できるレベルに持っていこうではないかと言うのが1990年代以降にNTT再編成問題等でNTTと論争してきた一人としての偽らざる心境だ。
改めて言うが地域インフラ・ボトルネック問題以外は共通課題だからNTT法廃止議論はこの問題に絞ればよい。そして建設的な提案を両陣営が出しあえば良い。
いきなり結論から言うと地域インフラの資産論の誤りを正すことだと思う。そこから新たな解決策が生まれてくる。大事な事は地域インフラは国民資産でもなければNTT資産でもない、双方が共有する不可分資産だとの認識を持つことだ。わたしは1990年代より論争に加わってきたがこの認識に立って議論した記憶がない。つまりこのことは誰も認識していなかった。
この認識は電波とのアナロジーで容易に考えつく。基地局は携帯事業者の資産だが電波は国あるいは国民の資産であり、そして電波インフラはこの有形・無形の資産が混じり合って不可分の資産となる。同様にとう道などの地域インフラも道路占有権と一体になって初めて有形・無形の資産が混じり合って不可分の資産となる。
競合他社が地域インフラは国民の資産だと主張することはかつて孫正義氏も主張し、のちに光の道構想ではひっ込めた主張で現時点では心情的、情緒的な主張に聞こえる。しかし不可分の資産であると言う主張なら通る。
この認識に立って現実的な解はどうなるだろう。次の二つがわたしの考える案だがかつての光の道構想に比べると段違いに現実味を帯びてくるのではないか。何より資産の譲渡や巨額の経費が新たに発生しない、いわば長期増分費用方式でよく言われる「観念」としての整理が主だからだ。(かつて審議会委員を務めた醍醐東大教授・当時がよく使われていたのを記憶している)
地域インフラの管理は設備を持たない独立保守管理会社か、それが現実に難しければ米国の州公益委員会方式をまねて公益資産である道路占有権を梃子にNTT地域インフラを管理する機関を作る。
この二つのうち現実的な方を選択すれば良い。後者の場合、道路占有権は国土交通省が本来の主管庁だが自治体を管理する総務省も関与していると思われるので通信政策に馴染みがあってよりふさわしい総務省管轄が望ましい。もちろん両省の調整が必要だが。米国の州公益委員会方式を徹底的に研究する必要もあるだろう。だから数年の検討期間を必要とするが道筋を提示すれば競合の危惧はおさまるのではないか。
総務省管轄で米国の州公益委員会的な組織を作るとなると電気通信事業法の改正を持って地域インフラの無形資産部分を料金面で適正に管理できることになる。そして新たな伝送路の自前化要請にも審査が可能になる。現存の紛争処理委員会の類似の機関がイメージできるが参考になるだろう。
以上がNTT法廃止議論を眺めていて試行錯誤の上に辿り着いたわたしの今後に期待する展開だ。
大事な事は地域インフラは国民資産でもなければNTT資産でもない共有の不可分資産だと認識を行うことだ。資産論を抜きにした公益論だけで攻めると米国でも憲法違反の議論で反対されたケースもあり、競合から見ても将来が不安だろう。
NTTと国民の共有の不可分資産だと認識すれば競合は国民の不可分資産だと胸を張って不当な扱いは財産権の侵害など憲法違反だとも訴えることができるかもしれないが専門家でないのでなんとも言えない、しかしより安定性の強い権利意識を持つことができる。
地域インフラの無形資産部分を電波のように国が保有しているのだからその認識に立って管理すると言う方がより安定性のある規制が可能になる。
日本の携帯電話料金の最近の動向では、一部の料金が再び上昇しています。以下に具体的な数値を示します。
- ソフトバンクは「ワイモバイル」の大容量プランの月間データ通信量を25GBから30GBに引き上げ、セット割引を適用しない場合の月額料金を4,158円から5,115円に上昇させました。これにより、1GBあたりの料金は従来のプランよりも約3%程度高くなる見込みです 。
- 同様に、小容量プランでは、月間データ通信量が3GBから4GBに増加し、月額料金が2,178円から2,365円に引き上げられる見込みです 。
- KDDIも「UQモバイル」で料金プランを見直し、セット割引を適用しない場合、一部のプランで1GBあたりの料金が約10%増加しました 。
- NTTドコモも新しいプラン「irumo」を導入し、光回線等とのバンドル割引を利用しない場合、月額料金は3GBプランで2,167円となります 。
これらの変更は、政府主導の価格引き下げ政策の影響で、NTTドコモの20GBプランの通信料金が以前と比べて約60%減少した後のものです。2019年時点で、東京の20GBデータプランは8,175円でしたが、2021年度には2,972円に大幅に低下しました 関連ブログはここからどうぞ。