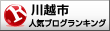中に石の鳥居と社殿が見えた。

石の鳥居には、額は掛っていない。

少し高くなった所にこじんまりとした社殿が建っている。

屋根を見上げると、一番上に竜の像があった。
浮き彫りのような平べったい像だが、かなり迫力がある。

社殿に近づき上を見ると、額には「瘡守社」と書いてある。

拝殿の後ろに本殿があり、両側から見ることができる。
社は溶岩で出来た基壇の上に祀られている。

下の両側に石灯籠があり、その中央細長い周囲の欠けた石が立てかけてある。
その表面には「瘡守社」と浮き彫りされている。
かなり厚みのある石だが、元はどこにあったのだろうか。

その石の脇や、その上の段に小さな狐の像が置かれている。
どうやら稲荷神社のようだ。

「埼玉ふるさと散歩《川越市》」(新井博 さきたま双書)には
「福田屋書店に沿って左に入ると、瘡守稲荷がある。毎年六月が例祭で、おできやふきでものに霊験があるという。」
と書かれている。
「瘡守」なので「疱瘡」にも霊験があると思うが、「疱瘡」はもう用がないので、コロナに宗旨替えしてもらえないものだろか。