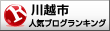「R16 二重人格だから埼玉はおもしろい」 荻野嘉彦 まつやま書房 2008年
ネットと実物の違いを身体で理解する
もちろん川越は「菓子屋横丁」だけではない。
「蔵造りの町並み」をはじめ、「時の鐘」「喜多院」など見どころいっぱいだ。所持金がなくなったおかげで、「喜多院」までも歩くことになった。
歩くことは思わぬ副産物があった。商業エリアも見ることができたのだ。
事前にネットで勉強してきた崇行くんは言う。
「川越って古い家ばかりだと思っていた」
ネットの川越と現実の川越が大きく異なることに驚いた様子。川越の町全体=「蔵造りの町並み」ではないことに気づいたのだ。
ネットが身近になった現代。しかし、ネットと実物が異なることはいくらでもある。崇行くんは川越を歩きながら、ネットと現実の違いを肌で感じていた。
ちょっと駄菓子屋論
菓子屋横丁は、魅力的な駄菓子が揃う、本格派の駄菓子屋である。
しかし、昭和50年代前半に私が通った駄菓子屋はちょっと違っていた。
川越の菓子屋横丁は本格派ゆえ、駄菓子以外の商品がほとんど見当たらないのだが、私が知る駄菓子屋は、駄菓子だけを売っていたのではなかった。
そこでは、ちょっとした日曜生活雑貨などが合わせて売られていた。特に学校近くの駄菓子屋では、子ども用の文房具が必須だったと思う。
ノートはコクヨ、ジャポニカ。鉛筆では三菱、コーリン。ほかにもシャープペンの芯、のり、画用紙、折り紙、原稿用紙などなど。数多くの文房具が置かれていた。
文房具は売れるから陳列するという位置づけの商品ではない。駄菓子屋の戦略的小道具と言う方が正しかった。
なにせ、学校帰りに駄菓子屋へ寄るのはご法度とされていた。
子どもは、駄菓子屋に寄るための口実が必要だった。
駄菓子屋に行く為の「言い訳」が文房具だった。
「勉強用のノートを買う」
これは魔法の言葉だった。子どもたちは、堂々と学校帰りに駄菓子屋に行くことができた。
当時の先生もまたそのあたりを心得ていた。
「ノートを買う」
こう言われれば、先生も「ダメだ」なんて言わなかった。
「駄菓子屋はダメ」と話していた先生であったが、本音はこんな話自体、野暮だと思っていたに違いない。だから、子ども的な抜け道を許してくれていたのだろう。
鉛筆を買うふりをして、駄菓子を買う。
鉛筆を抱き合わせで、駄菓子を買う。
駄菓子屋に文房具が置いてあったのは、一種の芸術であり、子どもと先生の間には「あうんの呼吸」があったような気がする。
駄菓子屋で世渡りのコツを勉強した。本音と建前の使い分けも教わった。おかげで、その後の人生で大いに役立たせてもらっている。
→川越雑記帳
最新の画像もっと見る
最近の「川越関連本」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- 川越散歩(527)
- 散歩写真(541)
- 川越の四季(花・木・自然)(758)
- 川越の桜(175)
- 川越動物誌(211)
- 庭の花・実(132)
- すき間に生きる(53)
- 空と雲(6)
- 行事・イベント(83)
- 碑文を読む(24)
- 文学碑を歩く(7)
- 説明板を読む(34)
- 伝説を歩く(12)
- 石仏・石像・狛犬(14)
- 伊佐沼(37)
- 時の鐘(13)
- 町まちの文字(43)
- マンホールのフタ(15)
- 街中アート(20)
- 火の見櫓の風景(44)
- ポストの風景(9)
- 街の時計(7)
- 三十六歌仙額(36)
- 案山子(かかし)(51)
- 川越駅西口(89)
- ふれあい拠点施設(60)
- 川越の端っこめぐり(138)
- 赤間川・新河岸川下り(112)
- 安比奈線(40)
- 街道を歩く(12)
- 落し物・忘れ物(15)
- 現代の妖怪(6)
- PCでお絵描き(6)
- ホームページ(3)
- 川越関連本(34)
- 小江戸川越検定試験(36)
- その他(14)
バックナンバー
人気記事