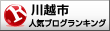五差路を右折し200㍍ほどいくと、前方に火の見櫓が見えた。
右側に民家に挟まれた狭い道の奥にお堂が見えた。

細い道を抜けると広くなり、正面に赤い屋根のお堂、右手に集落センターの建物があった。
集落センターでは何かの集まりがあり、多くの子供達の声が聞えた。
「もとは円正寺という寺で、天台宗仙波中院の末寺で清水山多聞院と号した。明治初期には小学校になったりしたが、無住になってからは村の集会所に使われた。境内にある堂宇は毘沙門堂で本尊の毘沙門天と円正寺の本尊聖観音が安置されている。」

「墓地には享保七年(1722)谷中村の者一二人が建てた庚申塔、谷中の念仏講中が建てた享保一二年(1727)の地蔵がある。」
毘沙門堂の右手奥が墓地で、その入口に地蔵と庚申塔があった。

側には地蔵堂もあり、帽子を被った六地蔵が並んでいた。