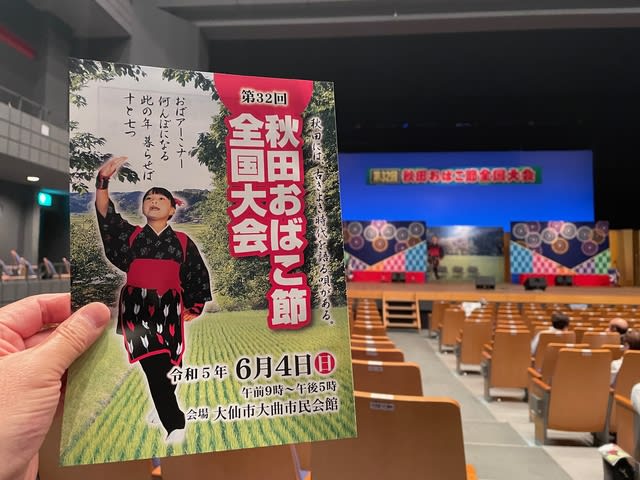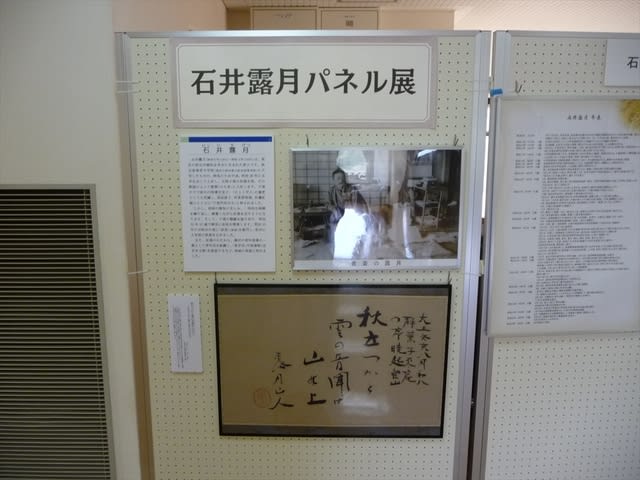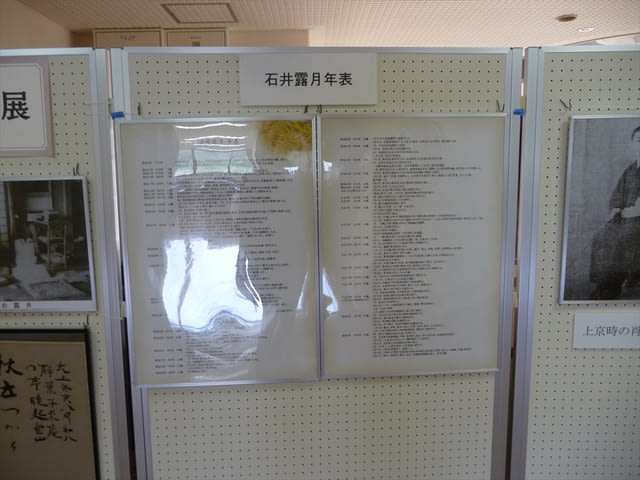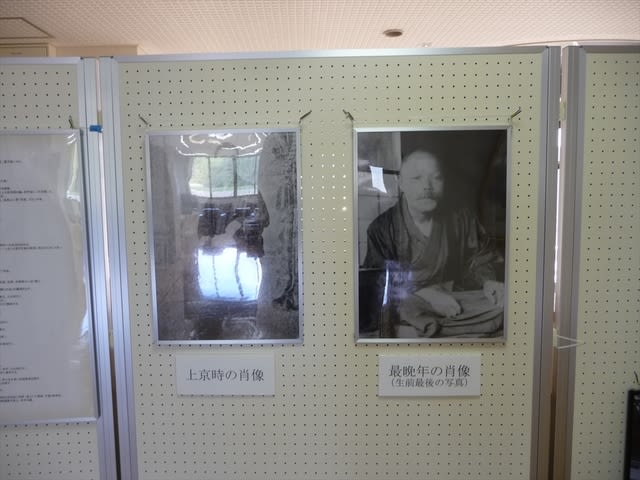2023年(令和5年)2月26日(日)

秋田市が主催する「農村の魅力体験ツアー企画第10弾!!」に参加しました。
テーマは「古民家で体験する冬の農村~自家製みそ焼きおにぎりと郷土のおやつ作り~」です。
秋田市役所前を午前9時15分に出発。

今日の行程をご紹介します。
秋田市役所→(秋田駅東口)→古民家commune→秋田市農山村地域活性化センター「さとぴあ」→(秋田駅東口)→秋田市役所
古民家communeでは、みご箒作りと釜ご飯と自家製味噌の焼きおにぎりをいただきます。
秋田市農山村地域活性化センター「さとぴあ」では、郷土のおやつ作り(バター餅、おやき)です。
最初の訪問地「古民家commune」に到着。

囲炉裏を囲んで、みご箒を作ります。

講師は、ここ古民家communeを主宰する遠山桂太郎さん。


温かいお茶が冷えた身体に沁みます。

今日作るのはこれ。
稲で作った箒ですが、デザインがかわいいです。キムカズにできるか不安な中、作業スタート。





あれやこれやでこんな感じで完成です。

今日の参加者の完成品を一堂に、皆さんお上手です。

つぎは、「釜ご飯と自家製味噌の焼きおにぎり」です。
釜で炊いたご飯。蓋を取った瞬間、香ばしいご飯の香りが広がりました。もうこの段階でめちゃくちゃ楽しみになります。

自家製の味噌。

参加者それぞれが握り飯を作り、囲炉裏で焼きます。

おかずも添えられました。秋田の伝統野菜「沼山大根」で作った品々。
沼山大根は、いぶりがっこの元祖と言われています。
一時は途絶えた沼山大根でしたが、講師の遠山さんをはじめ県内の若手農家3人がみごとに復活させたのです。

トン汁。やはり「沼山大根」を入れてくださっています。
どれもこれも、見るからに美味しさが伝わると思います。本当に美味しかったんです!

遠山さんが作っているお味噌。
2年熟成、3年熟成、4年熟成とそれぞれを味見をさせてくださいました。
それぞれ特徴があって、全然違います。

沼山大根のいぶりがっこにお味噌をお土産に買い求めました。

今日接待をしてくださった皆さんに見送られて次の場所へ移動。

まだまだ雪の残る河辺を後にして、下新城へ向かいます。

秋田市農山村地域活性化センター「さとぴあ」。




バター餅の原材料。

レシピもしっかりつけてくれています。

材料を入れて、混ぜ混ぜして、レンジでチンしてバターを溶かして、また混ぜ混ぜしました。
そして、タッパーに入れて冷やして完成です。
簡単な工程とは思いましたが、餅になるまでにかき混ぜる手が重くなり、相当な重労働となりました。汗


次に取組んだのが「おやき」です。

先生がもち米のあたりは相当準備してくださっていたので、ちょっと混ぜ混ぜして、その後はフライパンで焼き焼き。


「つるし雛飾り展」も開催中で、お雛様の音楽が館内に流れているさとぴあでした。

秋田市に住んでいて、なかなか接することのない体験をたくさんすることができた一日になりました。
何もないではなく、何かある。
ないのは気づいていないから。そう思って、もっと足もとを見つめて過ごそうと思います。