映画「ハーブ&ドロシー」を見てきました!
絵画などの作品を4800点買い集めた、NYに住む郵便局員(ハーブ)と図書館の司書(ドロシー)の夫婦のコレクターのドキュメント映画です。
是非とも見ていただきたい映画です♪
</object>
大阪の梅田スカイビルのシアターで放映中です!
大阪の梅田スカイビルのシアターでは、心にじんとくるミニシアター系の映画を沢山放映していますね!
来年1月はバスキアを見に行きたいと思います♪

ところで、ハーブ&ドロシーの映画で何を知ることが出来たのか、簡単に書いてみました(*^^* ゞ

ハーブ&ドロシーはアーティストを目指して絵を描いていたので、「作品の本質」、「作家の本質」を見ることができ、そこで『イイ』と思ったものを買ったり、もらったりしていたのだと思います
ハーブ&ドロシーのアパートの部屋に飾られていた作品は、作家の生気、エネルギー、感性、繊細さ、センスがダイレクトに伝わる作品が多く、手作り感が強く出ているものばかりでした
ハーブ&ドロシーはアーティストになりたかったからこそ、『オリジナルを生み出し極める難しさ、孤独との戦い、などアーティストの苦悩』がよくわかり、展覧会場や作家のアトリエを訪問しては、持ち帰ったり買っていたのは、『イイ』と思ったのもありますが、アーティストがそれにより心底喜びになることと、その事が作品を創る大きなエネルギーになることを知っていたし、ハーブ&ドロシー本人たちにとっても、リアルな喜びであり、生きる喜びなのだからだと思いました
ハーブ&ドロシーがアーティストのアトリエを訪問していくシーンを見ながら、それに気付いた時には、涙が込み上げて来てこらえるのが大変でした。
ハーブが若いときに美術の本をむさぼるように見ているシーンで気付きました。
美術が人を引き付けるのは、作品には『感情』が現れていて、それを『見た人の心にも、様々な感情が沸き立ち』、気付かないけど、それが快感であり、自然なことだからだと思いました。
作品を制作していると、制作している未完成の過程で、『美しい!』と思うことが、自分の作品だけでなく、他のアーティストの制作過程でも沢山あります。
その美を、ハーブ&ドロシーは知っているし、アトリエに直接行って、作家に直接会って話をして、作品を見て、自分の目と耳と知識で、『イイ』と思ったものを買ったり、もらったりしています。
感じ方が本物です
『人』と『作品』は別々に独立しているようで、実は『同じ』だし、直結してます
あの小さなアパートの中に、数々の作品たちが飾られ、日常生活のなかで常に、作家のエネルギーや発想や独創性を発している作品を見て日々過ごすって、そうとう一生懸命、人生を追求した生き方だと思います
作品は、単純に見て何かを感じて『イイ』と感動する楽しみかたもあれば、ハーブ&ドロシーのように『創作』自体をよく見て楽しむという楽しみかたもあると思います
一人の人間が、人生を賭して追求していく独創的な考えと発想、そしてその表現、それらがリアルであればある程、そうした作品に対して強く惹き付けられます
それがオーラとなって、作品が迫力を持ち、見る側に何かを感じさせてくれますし、感動させてくれるのだと思います
ハーブ&ドロシーは出会った作家、特に自分達が作品をコレクトした作家たちが成長していくのも、子供が成長するのと同じくらい大きな喜びだったでしょうし、育てる喜びもあったと思います
どのように変化し成長していくか、その内容も作家の数だけ多様であり、『知的喜び』もひとしおだったと思います
売らなかったのは、作品一つ一つが、子供と同じくらいかけがいがなく大切なものであり、可愛いものだったのかもしれません
作品は、作家にとって自分自身そのものです
もしかすると、ハーブ&ドロシーも自分自身と同じだったのでしょう
ところで、ナショナルギャラリーのように『作品を売らない』と規約にあれば、大切な作品を安心して寄与できますね
『自分の死後ずっと、ナショナルギャラリーにあり続け、大切に保管され続ける』とわかるのですから、こんな安心なことはありません
世界中の人々に、自分のコレクトした大切な作品が、これから未来の時代の人々に受け継がれ見られるなんて、死後も有意義な影響を人々に与え続けることができるなんて、自分自身が生き続けているのと同じようなことですよね
作家が死んでも作品は生き続け、未来の時代の人々に、自分の感性を感じてもらい、コミュニケーションがとれるのと似ています
作品として、その人は生き続けているという、画家のロマンを、2009年にグッゲンハイム美術館へ行ったときに、初めて感じました
ハーブ&ドロシーの場合、彼らが集めなければ誰も集めないし、多くの人の目に触れることが無かったような作品たちばかりで、それらがナショナルギャラリー等のしっかりとした美術館に入ったのだから、時代をまたにかけて、これから多くの人々の目に触れられるのですから、彼らが人に与えた影響力だけでなく、作品に与えた影響力は絶大
私は、絵が好きで、絵を描き続けていますが、創りてのみならず多くの人をひきつけるアートの本当の魅力を感じてはいますが、説明できる形、言葉の形で具体的にはまだ発見できていないので、これからも追求していきたいと思います
☆mikoto☆






























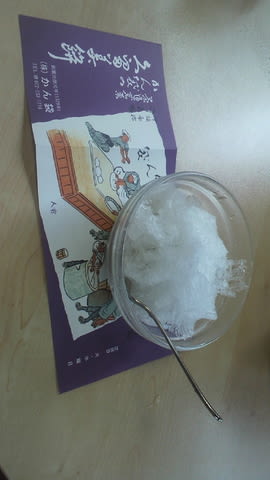































 参加してますノダ
参加してますノダ










 絵画に関することは、右の
絵画に関することは、右の 絵画
絵画 カテゴリーをクリックしてご覧ください
カテゴリーをクリックしてご覧ください





























