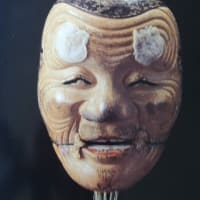お彼岸です。
我が家には仏壇が無く、線香と蝋燭を見るのはお彼岸で墓参セットを開く時です。
線香は仏事以外にも、遊びの時間に使われて来ました。
花街での遊びの時間を、線香1本の燃え尽きる時間(2時間)として、1本と呼んだ
様です。今でも芸者さんの花代は線香代と呼ばれ、1本2本と勘定すると聞いた事が
あります。
蝋燭は主に遊郭で使われていたようです。
客が上がると部屋の前に、ガラスの風防に入った蝋燭が吊り下げられる。
この蝋燭が燃え尽きるまでが遊びの時間だったようです。
3cm近くまで燃え尽きると、そろそろお客を追い出しに掛かる。が、慣れた客に
なると蝋が溶けて灯心がジリジリ鳴っても頑張るのもいたそうです。
相手をしたくないお客に出会うと、お女郎さん自ら蝋燭を短く切る事もあったとか。
昨日読んだ本からです。
墓参が終わると、線香は香炉に埋めて、蝋燭は灯りを消して(切りはしません)帰り
ます。防火の為です。
我が家には仏壇が無く、線香と蝋燭を見るのはお彼岸で墓参セットを開く時です。
線香は仏事以外にも、遊びの時間に使われて来ました。
花街での遊びの時間を、線香1本の燃え尽きる時間(2時間)として、1本と呼んだ
様です。今でも芸者さんの花代は線香代と呼ばれ、1本2本と勘定すると聞いた事が
あります。
蝋燭は主に遊郭で使われていたようです。
客が上がると部屋の前に、ガラスの風防に入った蝋燭が吊り下げられる。
この蝋燭が燃え尽きるまでが遊びの時間だったようです。
3cm近くまで燃え尽きると、そろそろお客を追い出しに掛かる。が、慣れた客に
なると蝋が溶けて灯心がジリジリ鳴っても頑張るのもいたそうです。
相手をしたくないお客に出会うと、お女郎さん自ら蝋燭を短く切る事もあったとか。
昨日読んだ本からです。
墓参が終わると、線香は香炉に埋めて、蝋燭は灯りを消して(切りはしません)帰り
ます。防火の為です。