
77回目の終戦記念日 大衆民主主義の課題
根付かせる意思と不断の努力が必要
日本総合研究所 寺島実郎会長
要点箇条書き---2022年8月15日 聖教新聞
1-
現代の民主主義は近年、欧米各国を中心に、
ポピュリズム(大衆迎合主義)に席巻されている。
最も大きな事例としては、
2016年、英国の国民投票でEU(欧州連合)離脱が決定したことと、
米国におけるドナルド・トランプ大統領の誕生。
2-
近年、日本の国政選挙の投票率は大抵50%台。
民主主義の根幹が揺らいでいる。
政治に対する期待が低下すると、
政治はますますポピュリズムに傾いていく。
消費税減税をはじめ、お得感のある政策を訴え、
国民の関心を引こうとする。
3-
世界中で民主主義の退潮傾向が危惧される中、
日本はどのような役割を果たせるのか?
国際社会の潮流は大きく変化している。
21世紀に入り、中国をはじめ新興国の台頭が著しく、
米国の国力・威信は相対的に低下している。
また、ウクライナ危機によって、
ロシアの弱体化は進む。
いわば、新たなパラダイム(枠組み)が動き始めている。
右肩下がりの経済が続く日本は今や埋没しかねない状況。
重要なのは、世界を広く知り、
立体的・多面的な視点から物事の本質を捉える「全体知」に立
つこと。
「自立自尊」の基軸を打ち立て、
世界の秩序、外交などを巡り新たな構想を描く、
アジアを代表する成熟した民主国家を目指すべき。
激動の時代だからこそ、
『全体知』をもつ優れたリーダーの登場が期待される。
4-
戦後民主主義が試練の時を迎える中、私たち一人一人が民主主義
を根付かせようとする主体的な意思を保ち続け、社会の意思決定
に参加することが大切。
「民主主義への不断の努力」が問われている。
---------以下本文--------------
きょう15日、77回目の終戦記念日を迎えました。
戦後、日本の民主主義は、どのように政治・社会を特徴づけてき
たのか。
長年、日本と国際社会の動向を見続けてきた一般財団法人・日本
総合研究所の寺島実郎会長に、大衆民主主義の現状や課題と併せ
て語ってもらいました。
(聞き手=光澤昭義記者)
「与えられた」国家体制
――1945年8月15日を境にして、日本は全く異なる国になりま
した。
戦前の軍国主義体制が否定されるとともに、「米国型の民主主
義」が導入されました。
それから77年を経て、「戦後の民主主義」には、どのような特
徴があると考えますか。
寺島実郎会長 戦後民主主義を考える時、最も重要な点として、
突然に「与えられた民主主義」であることが挙げられます。
欧米各国には、民主主義を手に入れるために、自らの血を流し、
勝ち取ってきた歴史があります。
しかし、日本では敗戦の状況下、戦勝国から急にもたらされた
という特異な民主化の歴史を歩んだわけです。
戦後の民主主義を巡る議論では、「与えられた」という限界は
あるにせよ、民主化の前進を重視すべきだという意見がある一
方、戦後の占領期に押し付けられた憲法や民主主義を屈辱に感
じる人々もいます。
中には、戦前の日本に回帰しようとする勢力もある。
日本に「民主主義が定着し、根付いているのか」という課題は
今も問われ続けているのです。
――明治時代の自由民権運動や大正デモクラシーのように、戦
前の日本にも民主化の動きがあったという議論もあります。
寺島 近代以降の日本の歴史を見れば、国会が開設された後の
1890年、初めて衆議院議員総選挙が実施された当時、選挙人は
25歳以上の男子で15円以上の直接国税を納めている者に限られ
ていました。
総務省統計局の資料によると、全人口に占める有権者の割合は、
わずか1・1%。1928年2月の衆院選では、納税額の制限が撤廃さ
れ、25歳以上の全ての男子に選挙権が与えられましたが、それ
でも全人口の約2割にすぎなかった。
敗戦の翌年(46年)の衆院選では、20歳以上の男女に選挙権が
認められ、その割合が約5割に。現在、18歳以上の男女に拡大さ
れ、2016年の参院選では83・7%が選挙権をもつに至りました。
有権者の推移を見ると、戦前から一転して、大衆民主主義が到
来したことがよく分かります。
――ご自身の人生は、戦後の民主主義とほぼ重なっています。
寺島 はい。私は1947年(昭和22年)生まれです。その年から
49年までの間に生まれた「団塊の世代(第1次ベビーブーム)」は、
日本人として初めて、小学校から戦後民主教育を受け、平等主義
が徹底される教育環境で育ちました。
米国とソ連の東西冷戦期、資本主義と社会主義の対立が激化する
中、私たちが大学に入る頃には、左翼思想に傾いた学生が多数に
及び、大学改革を求める学生運動の嵐がキャンパス内に吹き荒れ
ました。
計算も展望もない、未熟な運動は短期間のうちに収束し、その後、
日本は一気に高度成長の時代に突入します。
経済は右肩上がり。
社会人となった私たちの世代は“都市新中間層”として日本経済
を支え、「一億総中流」化の時代を迎えましたが、それまでの労
働者意識・階級意識がどんどん薄れ、大々的な社会革命や民主主
義の定着にはもはや関心がなくなっていきます。
そして、日々の生活だけを重視する「イマ・ココ・ワタシ」の価
値観が蔓延していきました。
未来に目を向けない風潮は今も、日本社会を覆っているといえます。
新たな危機招くSNS
――現代の民主主義は近年、欧米各国を中心に、ポピュリズム
(大衆迎合主義)に席巻されています。
最も大きな事例としては、2016年、英国の国民投票でEU(欧州連合)
離脱が決定したことと、米国におけるドナルド・トランプ大統領の
誕生が挙げられます。
寺島 ポピュリズムは、世界各国の民主主義が直面している問題の
一つです。
デモクラシーとは「民衆による支配」を意味します。
民衆による意思決定とポピュリズムの危うさは表裏一体であり、そ
れは、古代アテネの民主政の頃から指摘されてきました。
それに加えて、世界中で民主主義には新たな課題が生じていると考
えます。
トランプ大統領が誕生した選挙では、SNS上の情報が本当かウソか、
議論になりました。
デジタル革命によって、私たちを取り囲む情報環境は一変したのです。
――参議院議員選挙・投開票日(7月10日)の2日前、安倍晋三元首
相が応援演説中に銃撃され、死亡するという事件が起きました。
今回の事件についても「ネット社会が深く関係している」と、寺島
会長は指摘しています。
寺島 そうです。事件の直後、メディアでは「民主主義への挑戦」と
いった反応が目立ちました。
過去の政治家へのテロを例に挙げつつ「戦前の日本に戻してはならな
い」と語る識者もいますが、それでは問題の本質を見誤ってしまうで
しょう。
そもそも、犯人の動機は政治信条やイデオロギーを巡るものではなく、
特定の宗教団体に家庭を壊されたという個人的事情だと報じられてい
ます。
そこには、現代特有の社会的背景があると考えます。
――どのような危険を抱えているのでしょうか。
寺島 SNSの発達によって、今では誰もが発信者になり、情報の入手も
容易になった一方、SNSや検索エンジンのアルゴリズム(計算手順)の
世界では、誰もが自分の見たいものや知りたい情報だけを提示され続け、
特定の関心事ばかりに詳しくなっていきます。
アルゴリズムの世界に閉じ込められているのです。
今回の事件で言えば、ネット環境を通じ、凶器や火薬入手の情報を得て、
憎む相手の行動予定を特定していきました。
自分で情報を選択しているつもりが、いつの間にか、特定の意見や思想
に傾倒する自分になってしまう。
これを「エコーチェンバー(共鳴室)効果」と呼びます。
「自分が自分でなくなる情報環境」に陥り、AI(人工知能)やそれを使
う人々に考えることを任せてしまう「思考の外部化」が進行しているの
です。
人々の判断は歪められ、社会には分断が生まれる。
新しいタイプの「民主主義の危機」といえます。
政治への期待を高める
――近年、日本の国政選挙の投票率は大抵50%台です。
民主主義の根幹が揺らいでいるように映ります。
寺島 政治に対する期待が低下すると、政治はますますポピュリ
ズムに傾いていきます。
消費税減税をはじめ、お得感のある政策を訴え、国民の関心を引
こうとする。
また、若者の政治参加について、よく議論されていますが、それ
と同時に、高齢者層に対し、民主政治への期待を高めることも重
要です。
2050年ごろ、日本の人口は1億人を切るという試算があり、その時
には65歳以上の人口が約4割に上るといいます。
予想の数字ですが、高齢者人口が圧倒的に多くなることは間違いあ
りません。
「シルバー・デモクラシー」が今後、政治の焦点の一つになるで
しょう。
――世界中で民主主義の退潮傾向が危惧される中、日本はどのよう
な役割を果たせるのでしょうか。
寺島 国際社会の潮流は大きく変化しています。
21世紀に入り、中国をはじめ新興国の台頭が著しく、米国の国力・威
信は相対的に低下しています。
また、ウクライナ危機によって、ロシアの弱体化は進むでしょう。
いわば、新たなパラダイム(枠組み)が動き始めている。
右肩下がりの経済が続く日本は今や埋没しかねない状況です。
重要なのは、世界を広く知り、立体的・多面的な視点から物事の本質を
捉える「全体知」に立つこと。
「自立自尊」の基軸を打ち立て、世界の秩序、外交などを巡り新たな構
想を描く、アジアを代表する成熟した民主国家を目指すべきでしょう。
――日本国民には何が求められますか。
寺島 戦後民主主義が試練の時を迎える中、私たち一人一人が民主主義
を根付かせようとする主体的な意思を保ち続け、社会の意思決定に参加
することが大切です。
「民主主義への不断の努力」が問われていると考えます。
<取材メモ〉
「歴史を見ると、英国のチャーチル、ナチスドイツのヒトラーなど、良
くも悪くも指導者の影響が大きかった」と寺島会長。
「激動の時代だからこそ、『全体知』をもつ優れたリーダーの登場が期
待されます」と熱い口調で。
〈プロフィル〉
てらしま・じつろう 1947年、北海道生まれ。早稲田大学大学院政治
学研究科修士課程修了。三井物産入社後、ワシントン事務所長、常務執
行役員、三井物産戦略研究所所長などを経て、現職。
多摩大学学長も務める。著書に『人間と宗教あるいは日本人の心の基軸』
『日本再生の基軸 平成の晩鐘と令和の本質的課題』など多数。
TBS系列「サンデーモーニング」、TOKYO MX「寺島実郎の世界を知る力」
等に出演。










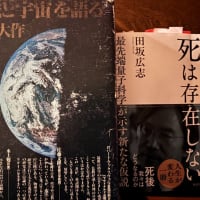









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます