サイフォンの科学史
昨日は台風が接近してくれたおかげで、朝は雨が強く降ったため傘さしていても濡れました<`ヘ´>今週末は天気悪いそうですね。せっかく散歩するのにいい感じの季節なのに残念です。散歩するなら皇居周辺か、御茶ノ水~神田~上野あたりが味わいがあって好きですね。中学生の時は椎名誠の「新橋烏森口青春篇」を何度も読んでいたので、椎名誠が描いた通りの新橋イメージを持っていたのですが、実際会社員になって行ってみるとなんだかだいぶ違って、なんというか酔っ払いのオッサンばっかり(笑)
午後会社のビルから外を見ると陽がさしているのに、外は雨が降っているのに気がつきました。ひょっとすると、と思って太陽を背にした方向を探すとありました!なかなか見事な大きな半円を描いている虹です。会社はカメラ付き携帯持ち込み不可ですので、残念ながら写真は撮れず。仕方ないので、ヤフーに記載されていた記事から画像を拝借しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131002-00000006-wordleaf-soci.view-000

網野善彦「日本の歴史をよみなおす」に虹に関する面白いことが書かれています。以下虹に関する記述を一部抜粋してみます。
・・・たとえば虹が立つと、かならずそこに市を立てなくてはならないという習慣が古くからありました。これは平安時代の貴族の記録にも出てきますし、室町時代にもまだその習慣の名残が残っているのです。たとえば藤原道長の邸宅のなかで虹が立ったので、そこに市を立てて交易を行っています。虹が立った場所など本当はわからないはずですけれども、ともかくそのようにしなければならなかったようです。勝俣さんは、虹の立つところに市を立てるのは、日本だけではなくて、ほかの民族にもそういう習慣があり、それは虹があの世とこの世、神の世界と俗界とのかけ橋なので、そこでは交易をおこなって神を喜ばさなくてはいけないという観念があったのではないか、といっておられます。そしてこれによってもわかるように市場は、神の世界と人間の世界、聖なる世界と俗界との境に設定される、と指摘しておられます。・・・
能楽でも「橋」のむこうからやってくるのはこの世ならざる者が多いですね。
またまた虹に関する余談ですが、ハワイ島などでは極々まれに月の光で虹がかかる時があるようです。rainbowではなくmoonbowと呼ばれるそうで、西條敏美「虹‐その文化と科学」で紹介されています。虹の話は色々と書きたいことがあるのですが、別の機会にでも書きたいと思います。
さて本日のお題ですが、仮説社より出版されている宮地祐司「サイフォンの科学史」が非常に面白かったです。先日紹介させていただいた、板倉聖宣「原子論の歴史 復活・確立」に引き続いての科学史ものです。この本はどちらかというと中・高校の理科・物理の先生向けの本ではありますが、サイフォン自体が身近にある現象ですので、理科に興味がある方は誰でも気軽に手に取ってもらいたいと思います。ちなみにサイフォンに関する的確な説明文章がウィキペディアに出ていましたので、引用しておきます。
サイフォン(siphon、ギリシア語で「チューブ、管」の意味)とは、隙間のない管を利用して、液体をある地点から目的地まで、途中出発地点より高い地点を通って導く装置であり、このメカニズムをサイフォンの原理と呼ぶ。
 図もウィキペディアより拝借しました。
図もウィキペディアより拝借しました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
さて著者である宮地祐司氏は小さいころからこのサイフォンが水をくみ上げる理由は「大気圧が原因だ」という説明を受けてきたそうですが(私もなんとなくそう思っていた節があります)広辞苑やオックスフォード英語大辞典などでも大気圧説が記載されているようです。ところが、どっこいサイフォン全体を容器の中にいれて真空ポンプで容器内を真空にしても、見事にサイフォンは動くことが実証されました。早々に著者は「正解」を書いてくれるので、読んでいる側もストレスがたまりません(笑)上図で右の配管と左の配管の長さが異なるのですが、この長さの差の重力位置エネルギーが駆動源としてはたらきまき、そして左側の水が切れずに上がっていく理由は水の凝縮力です。大気圧は上図の左右いずれの水にも働くので、打消しあって0です。
著者は水を鎖と見立てて「鎖モデル」によって非常に分かり易く動作原理を説明しています。さらにすごいのは、18世紀の文献を調べて、どうしてこのような間違い伝わって伝承されてきたのかを調べ上げています。なんと350年間間違え続けたというから驚きです。その中にはパスカルやボイルなど教科書にでてくるような科学者も間違いをおかしたことが説明されています。ここで詳細を取り上げても意味がないので記載しませんが、大気説を最初に提唱したのはパスカルだったようです。この著者が面白いのはこの失敗がなぜおきたのか?を考え、教育的な観点から役に立つ知恵を抽出できないかと考察しているところです。まさに最近広く認知されている「失敗学」と同じような考え方ですね。著者は教訓として4点あげています。
①論理的に考えたことは正しいという保証はない
②実験を繰り返していくことでしか、本当のことはわからない
③実験の背後にどういう仮説を持っているのかが決定的だ
④本当のことを明らかにするには、いろんな考え方をする人が必要だ
こんなの当たり前じゃん!と思う人ほど、この本を読んでほしいと思います。
読んだらクリックお願いします↓ ポイントが入り励みになります













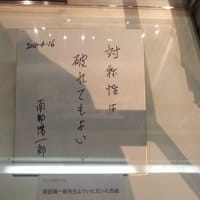



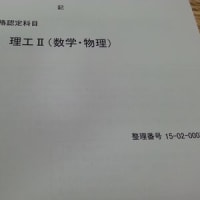
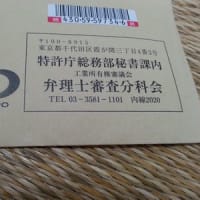


また大気圧説の誤りを広く知らしめたのはオーストラリアの物理学者Stephen Hughes 氏のようですが、彼の説明もまた間違っています。
残念なことに、ウェブ上にはまともな記事があまり見つかりませんが、基礎科学研究所・松田卓也氏の解説は唯一信用のおけるものです。