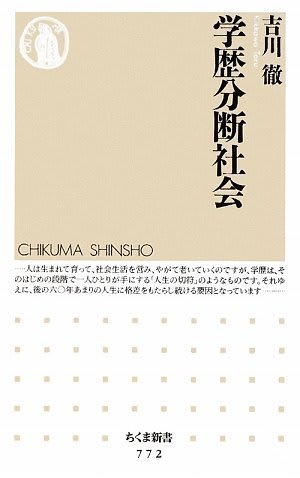
2009-05-24 14:58:13
偶像破壊の書。本書、吉川徹『学歴分断社会』(ちくま新書・2009年3月)を一読してそう感じました。著者の言う「格差論バブル」(p.7)とも言うべき、有象無象の格差社会論が猖獗を極めたこの社会の現状において、「格差は存在するのか」「格差が存在するとして、格差なるものの存在は悪いことなのか」、あるいは、「そもそも格差とはなにか」「格差が生じるメカニズム-格差の正体はなんなのか」というラディカルな問題設定から論を立上、而して、実証的データを丁寧に整理しつつそれらの問いに答えて行く本書は<偶像破壊=イデオロギー批判>の労作。そう言えると思いました。
本書の基本線は、①日本社会は高卒以下と大学・短大卒以上という「学歴分断線」(p.41, p.190)を境にして大きく二つの階層に分断されつつある、②その二つの階層は人口的にも「50:50」でほぼ等しく、かつ、その階層は再生産され「学歴分断社会」(p.50)として固定化しつつある(p.151)。
そして、③この階層分化の要因は各家庭の経済力の差では必ずしもなく、家庭が継承している文化的なものや家庭に憑依している学歴を巡る価値観の差であり(p.21, p.23, p.26, p.140ff)、而して、④この学歴分断社会化現象は政策的操作によって容易に変更できるものではなく、よって、学歴による階層の固定化を善悪の基準で評価することは適切ではない(p.27,p.38)。
ならば、⑤格差社会現象に対する社会的な施策も、(少なくとも当座は)不可避の学歴分断社会化という現実を見据えて、「ニート」や「ワーキングプアー」、そして、「派遣-業務委託」という就労形態を巡る不安定な労働環境等々の問題には、「中卒者をミニマムにする」等の対処療法の積み重ねで対応していくしかない。これはあまり愉快ではない現状認識ではあるが、現実を直視しないことがもたらすであろう悲劇に比べればこの認識を前提にする方が遥かにましである(pp.213-224)、というもの。
教育を巡る偶像破壊には前例があります。竹内洋氏の著作、例えば、『立身・苦学・出世』(講談社現代新書・1991年)、『立身出世主義』(NHK出版協会・1997年-世界思想社・2005年)が、「受験競争」は戦前から存在したし、戦前戦後一貫して「受験地獄」と呼ばれたネガティブな感情を受験生が抱いていたとは言えないことを示した実証的研究。
更には、苅谷剛彦氏の著作、例えば、『大衆教育社会のゆくえ』(中公新書・1995)、『階層化日本と教育危機』(有信堂・2001年)が、「子供達はみんなどの科目でも100点を取れるポテンシャルがある→現実にそうなっていないのは社会が歪んでいるからだ」という、日教組・全教が唱えていた、それこそ歪な妄想の<神通力>によってこの社会でそれまで一種タブー視されていた、(1)教育現場における子供達の能力差の存在、そして、(2)その能力差が必ずしも家庭の経済力の差に還元されるものではなく、むしろ、家庭の教育力や文化的蓄積の反映であり、(3)「学力-学歴」における格差は再生産され固定化している事実を明らかにしたこと。
そして、これらの事実を看過させてきたタブー。平等信仰ともいうべきこのイデオロギーこそが、(4)日本の教育現場を覆ってきた「能力主義的差別教育」批判の心性と、他方、学歴と能力の乖離に構造的原因があった時期をすぎても(高度経済成長の終焉を境に、能力はあるものの様々な理由で「大学・短大に行きたくても行けなかった層」が激減したにもかかわらず)「学歴社会-学歴主義」批判の心性をこの社会に蔓延させた要因であったこと。
畢竟、(5)「能力主義的差別教育」批判と「学歴社会-学歴主義」批判の心性は、より豊かでより安定した生活を勝ち取るために万人がより高い学歴を求め、万人が同じ条件のもと学歴を巡る競争に参加できる選抜制度と受け皿の教育機関の整備を推進し、かつ、学歴に従って職業・地位・威信が各自に配分されることを容認する意識が社会に遍く行き渡った「大衆教育社会」を裏面で支える、言わば<ヌエ的な心性>であることを苅谷氏の著作が提示したこと。これら竹内・苅谷両氏の著作は「偶像破壊」の名に恥じない。私はそう思っています(尚、苅谷氏の著作に関しては下記拙稿をご参照ください)。
・書評☆苅谷剛彦「大衆教育社会のゆくえ」
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/149f778fcddb7041f43a199bf390fb9e
本書の著者、吉川徹氏がいみじくも記している通り、世は正に「格差論バブル」の時代。この社会の森羅万象はすべて<格差>という概念装置で理解・説明できる、と。そのような感さえ漂っています。而して、私はこのような思想風景には既視感(dejavu)を覚える。それは、60年代後半に「疎外」と「実存」が、70年代には「物象化」と「構造」が、そして、80年代には「脱構築」と「構築主義」が一種演じていた役回りではなかったか、と。
けれども、カール・ポパーが書いているように、「あらゆることを説明できる概念はその内容において空虚」なのでしょう。実際、一世を風靡したこれらのジャーゴンを散りばめて展開された、例えば、所謂「ポスト=構造主義」が(当初から不人気だった英米はもとより、日本においても)ほとんど見る影もない現状を鑑みれば一層その感を深くせざるを得ません。
しかし、たとえ、その思想内容が空虚なものであるにせよ、「疎外」や「物象化」が「反米-反スタ」(反米-反スターリン:嫌米-嫌ソ連)という西側左翼知識人層の政治的主張のイデオロギー的反映であり、他方、「脱構築」や「構築主義」が社会主義の衰退と崩壊に直面した西側左翼知識人のリベラル派への衣替えに際してのイデオロギー的弁明であったこと、そして、個々の時代状況でそれらの概念装置がそれなりの政治的機能を果たしたことを踏まえるならば、更には、2007年の<7・29>参議院選挙において安倍自民党を地滑り的惨敗に追い込んだ格差社会論の実績を踏まえるならば、たとえ、「格差」の意味内容がいかに空虚なものであれそれがいまだに警戒すべき概念装置であることは間違いなと思います。
その意味でも、「階層意識の計量分析の専門家」(p.159)である著者が、本書において、学歴の切り口から「格差」の正体に迫り、而して、「格差」は善悪の此岸を越えた事象であることを実証したことは、「格差概念の空虚」のみならず「格差社会論の狡知」をも暴露したものである。畢竟、これが本書を偶像破壊的の一書と私が看做した所以です。
■概要
著者、吉川徹氏は計量社会学専攻の大阪大学大学院人間科学研究科の准教授。本書の目次は以下の通り、
はじめに
第1章:変貌する「学歴社会日本」
第2章:格差社会と階級・階層
第3章:階級・階層の「不都合な真実」
第4章:見過ごされてきた伏流水脈
第5章:学歴分断社会の姿
第6章:格差社会論の「一括変換」
第7章:逃れられない学歴格差社会
あとがき
主要参考文献
格差現象の「主成分=正体」は学歴である(pp.31-32)。この命題が本書の全体を貫く中心軸であり、他方、「学歴分断線」(p.41, p.190)の存在とそれによる「学歴分断社会」(p.50)としての日本というこの社会の現状認識が本書の主旋律と言ってよい。而して、「格差論バブル」に引き付けて本書の狙いを著者はこう述べています。
「学歴社会と格差社会の関係をうまく説明する理論が、まだあらわれていない」「「学歴社会」と「格差社会」は、ともに世の中の上下の序列を扱う論理であるはずなのに、なぜか接点をもって語られることがありません」「総中流がいわれていた30年前、日本人の半分近くは義務教育を終えてすぐに社会に出た人たちでした。ところが現在では、50歳以下の人たちの4割が大学や短大を出ているのです。いまの進学率が続いていくと【進学率は2007年度と2008年度で各々、53.7%と55.3%】、まもなく大卒層と高卒層の境界線が、日本社会をおおよそ半分に切り分ける状態になります。このことが、いまの格差社会の出来事の底流にあることは【学歴は原理上この社会のすべての構成員が保有する属性であり、他方、現在がいかに失業等々のリスクから誰も自由ではない「リスク化」の時代とはいえ、トータルでは、学歴と所得、学歴と雇用の安定に相関関係があることは否定できないのだから】、少し考えればだれにでも見通せるはずです」「つまり、格差社会の「主成分」は、上下に分断された日本人の学歴ではないかと考えるわけです」(pp.9-11)、と。
このような問題関心から著者は、本書第1章~第5章で、格差社会論の検討と学歴分断社会の説明(学歴分断社会成立とその社会内部での社会階層移動のメカニズムの説明)を行い、それらを前哨として第6章では数多の格差社会論の主張を学歴分断社会論のパラダイムに整合的に組み込む作業を行なう。而して、本書の掉尾を飾る第7章では、21世紀前半の日本に生きる我々が学歴分断社会と、謂わば<平和的共存>するための覚悟と方針が提示されています。尚、格差社会論との関連では次のような主張が記憶に残りました。
ガラスの天井
「大学全入時代を招く最も大きな要因は、大学に行きたいと望む高校生が半数程度しかいないということにあります」(p.17),「昨今の学歴社会は、親の学歴が・・・著しく高まってきたという点で、「子どもは親より学歴が高くなる(する)のは当たり前」と考えてきた昭和の学歴社会とは、まさに隔世の感があります」(p.20), 「このデータは「大学に行きたい(行かせたい)のに、やむを得ない事情で進学を断念せざるをえません」という高校生(とその親)が、この十数年の間に【1987年~2003年の間に】日本社会から消えていったということを示しています」(p.23),「結局大学進学率50%のところには、調整しなくても頭打ちになるような「ガラスの天井」がある」(p.26),「つまり、大卒/非大卒フィフティ・フィフティというのは、政策上の手を加えることで簡単に変えられるものではなく、現代日本社会のさまざまなものごとが、がっちりと組み合わさって生み出されている比率なのです。そしていまこの比率が親世代と子世代の間で受け継がれ、同じかたちで繰り返されているのです」(p.27)
豊かさ・格差・不平等
著者の語る通り、「「格差」として一括りにされがちな問題には、「豊かだが格差が大きく、不平等な社会」といった一筋縄ではいかない状態が、いくらでもありえる」(p.88)。蓋し、経済的な部面に限定したとしても、百花繚乱・千紫万紅「格差論バブル」を彩った数多の格差社会論のほとんどは「社会の豊かさの程度」「豊かさの分布=格差」「豊かさを求めての競争における不平等=格差を発生させる因果的なしくみ」の三者を混同するものだった。而して、それらは平等と自由のよりバランスのとれた社会の再構築という現下の日本社会が抱える課題に対してほとんど寄与できなかったと私は考えています(cf. pp.78-88)。
格差社会論批判
親世代と子世代の職業における階層の固定化なるものを<暴露>した佐藤俊樹『不平等社会日本』(中公新書・2000年)の主張は(佐藤氏が行なった各時代の40歳時点の職業の調査によっても)、高校進学率が30%の時代と90%を遥かに超えるようになった時代との比較、すなわち、高度経済成長が終焉を迎えるまでの工業化への過渡期(ホワイトカラー層が社会の少数派であった時代)と工業化が完成しポスト=工業化に入った時代(ホワイトカラー層が労働力人口の過半を遥かに超えている時代)の比較は無意味であり、よって、そう根拠のある主張ではなかったと思います。まして、(大部分の中小企業では実際にはそれは戦前戦後を通して根づいていなかったにせよ)雇用者-被雇用者双方の意識においても「終身雇用制」が崩壊したここ20年間における40歳時点の職業・所得を過去のそれらと比べることは全く意味がない。現在では佐藤氏自身がその主張を撤回していますが、著者は佐藤氏の格差社会論を念頭に置きつつ学歴分断社会論の見地からこう述べています。
「従来の【職業・所得・威信等に着目した親世代と子世代の】世代間移動の研究は、親世代でも子世代でも「正社員」をイメージしたものでした。しかし、こんにちの雇用の流動化は、社会調査によって明らかになる職業的地位を、うつろいゆく職歴の一瞬でとらえたものに変えてしまいます。ですから、分析のルールをどのように変えてみても、人生の到達点を捉えることは難しくなっているのです」(p.100)、と。
また、一時世の耳目を集めた山田昌弘『希望格差社会』の主張も、結局、景気変動と産業構造の調整の部面での労働力市場を巡る現象を「格差拡大」と解釈しただけの主観的な主張にすぎないことは現在では自明です。著者はお茶目な「スマイルマーク」を使用したモデル論でこの経緯を説明しています(pp.104-110)。すなわち、
この社会の全構成員を「上層」「下層」に二分すれば、社会階層の移動経路は数学的に(というか「場合の数」として)、「上・下」から「上・下」への移動であり「2×2」の4通りになる。他方、(甲)高度経済成長期の如く「親世代→子世代」の移行にかけて社会全体の経済のパイが拡大していた時代と、(乙)バブル経済崩壊以降の如く「親世代→子世代」の移行にかけてパイ自体が拡大せず可処分所得はむしろ減少する時代に分けて考えれば、社会階層移動により各クラスターの満足度は以下のようになる、と。
甲:パイ拡大の時代
○[上層→上層]階層がキープでき所得も上がり満足
○[上層→下層]階層は下がったけれど所得が上がり満足
◎[下層→上層]階層も所得もあがり大満足
○[下層→下層]所得が上がり満足
乙:パイ均衡の時代
△[上層→上層]階層はキープ、所得はそう変わらず普通
×[上層→下層]階層も所得も下がり不満
○[下層→上層]階層は上がったが所得はそう変わらず満足
△[下層→下層]所得がそう変わらず普通
畢竟、「読者は、みんなを幸せにするには結局、格差や不平等の是正ではなく、豊かさの向上が最も効果的な方策である(あったのだ)という当たり前の事実に、いまさらながら気付かれたと思います」(p.110)という指摘に希望格差社会論は包摂されているということでしょうか。
尚、著者は、「私自身も、社会の不平等がこれからもっと深刻になるという悲観的な見方はとっていません」(p.86)と明記していますが、富の社会的分布の度合を表す所謂「ジニ係数」の変化を根拠に日本社会における格差拡大を主張した橘木俊詔『日本の経済格差』(岩波新書・1998年)の主張は、大竹文雄『日本の不平等』(日本経済新聞社・2005年)によって(橘木氏が根拠としたジニ係数の変化は、日本社会の少子高齢化に伴う世帯所得の見せ掛けの分布の変化であるとして)実証的に否定、少なくとも、絶対のものではないことも現在では争いのない認識です(cf. pp.83-86)。
学歴伏流パラレル・モデル
工業化社会成立以降の社会(就中、ポスト=工業化社会において)教育は「富の世代間移転」の主要な形態であるとは現在では人口に膾炙している認識であろうと思います。著者もこのことを「学歴伏流パラレル・モデル」(p.125ff)という道具概念を用いて敷衍している。「【2005年実施のSSM調査によれば】親のうちどちらかが大卒であった場合、子どもが大学に進学する確率は68.8%ですが、両親ともに高卒層の場合は31.1%」「わたしたちは学校を終えると、その学歴を用いて職業に就き、学歴に応じた収入を得ます。ですから、順序としては、親より高い学歴を得たかどうかが18歳前後に確定し、その後、職業的な地位や豊かさについて、親よりも高い地位につけたのか、親より豊かな生活水準に至ったのかという世代間の関係が確定していくわけです」「私は【学歴が親においても子においてもパラレルに職業と経済力を規定する現象の水面下で、学歴における親子間の強い相関関係が時間軸にそって伏流する】このモデルを学歴伏流パラレル・モデルと呼んでいます」(pp.125-126)、と。
■特徴と核心
本書は、苅谷剛彦氏が戦後のこの社会におけるその成立のプロセスを復元した「大衆教育社会」(多くの人が高い教育を望んで長期にわたる教育を自ら引き受け、かつ、それが実際に制度的に保証されたことにより多くの家庭が学歴競争に参加する社会。而して、学歴による職業・地位・威信の分配を正当なものとする意識が社会全体に遍く広がった社会)の後日談。つまり、この15-20年余りの「大衆教育社会」の変容が本書の中心的内容と言える。その意味で本書は、『大衆教育社会のゆくえ』の違う個性による続編と言ってもよいかもしれない。そして、畢竟、本書のと核心は、それらが主に扱った「大衆教育社会」成立の前後の時期の差というよりも、苅谷氏と吉川氏の学歴格差状況を巡る評価の差異に収束するのではないか。そう私は考えます。
吉川氏はこう述べる。「インセンティブ・ディバイドは、苅谷剛彦氏が『階層化日本と教育危機』で述べた出身階層による高校生の意欲の格差のことです。希望格差は山田昌弘氏が『希望格差社会』などで展開した、若者たちの将来展望に階層差があるという指摘です」「この格差は自己責任で生じたものではなく、親の世代から引き継がれたものだとみる点でも【両者は】共通しています。さらに両者は、この意欲や希望の分断がもとになって、進学や職業キャリア形成についての格差が、さらに広がってしまうことに警鐘を鳴らしています」(p.166)
「苅谷氏が階層格差とみたものは、母親の学歴が高いかどうかという変数になっている」「70年代には母親の学歴によるこうした差が生じることはなかったが、90年代には母親学歴によるインセンティブ・ディバイドが生じはじめた」「母親学歴に注目してみると、70年代は大学・短大卒の母親が10人に1人しかいないなかで、多くの子どもたちが親を越えていき、およそ40%の大学・短大進学率が成立していた時代だったことがわかります。それが2000年前後には、母親の3人に1人が大学・短大を出ているなかで、子どもの大学進学率が50%弱という状態に変わっている」「ここには、学歴上昇家族が主力になって牽引していた大衆教育社会から、大卒再生産家族が主力になって牽引する学歴分断社会へという時代の変化をみることができます」(p.168)
「誤解を恐れずにいうならば、・・・親子ともども大学に進学しない世代間関係が繰り返されることも、かならずしも理不尽ではないということです。確かに親子とも高卒という人生は。階層の上下という見方をすると、下半分にとどまることを意味しますが、そこでの親子関係は多くの場合、安定しています。社会的に高い地位につく可能性は減りますが、その代わり、同じ生活の基盤を世代間で受け渡すことができるからです」「だとすれば、かれらが確信をもって選んだ人生を、学歴競争における「敗北」や大卒学歴からの「締め出し」だと一方的にみなすわけにはいきません」(pp.201-202)、と。
ここには、学歴格差はアプリオリに批判され是正されるべきだとする苅谷氏や山田氏の理論、あるいは、齋藤貴男『機会不平等』(文藝春秋・2000年)、『教育改革と新自由主義』(寺子屋新書・2004年)の如き、ヒューマンな言葉遣いの裏に高卒学歴以下の人々を見下した、単線経路でしか職業キャリアを評価できない傲岸不遜に対する本書の著者の明確な「NO!」が闡明されていると私は思います。而して、齋藤氏等は、大学進学率50%の「ガラスの天井」の現実を突きつけられた場合、あるいは、「それは作られた意識に基づくものであり、正しい情報を与えられればもっと多くの親子が大学に行かせたい/行きたいと思うはずだ」と答えるかもしれない。けれど、(仮想的な問答に大した意味はありませんが、)そのような言説は自己の視野狭窄を糊塗するための反証可能性のない独白にすぎないでしょう。
アイドルは科学者である・・・「渡辺麻友」は賢いのか可愛いのか、両方か?
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/1ae6adc4303ebd0c3c14aa40faa2a0e8
もう一つ私が本書の特徴と感じたのは、著者の「学校-学歴」に対するポジティブな認識です。例えば、「学校教育は、親から子への世代間の関係に対し、公的に定められた「フィルター」として介在することで、世襲制の社会にみられたような閉鎖的な関係を解消していくことをめざしていたのです」「いわば学歴は正規の格差生成装置」(pp.31-32),「学歴に基づく仕事の振り分けは、決していわれのない差別ではなく、「実績主義」【=メリットクラシー】といわれる正当な原則に基づいているのです。「学歴差別」という誤った表現をする人をときどきみかけますが、学歴は差を生み出すための公式な装置なのですから、学歴によって人生のチャンスが異なることについては、「差別」という言葉を使って民主主義的な配慮が求められることはないのです」(pp.39-40),「繰り返してきたとおり、学校は公式に認められた格差生成装置です。ですから、学歴分断線が日本人を上下に二分しているかぎり、わたしたちはその影響から逃れることはできないのです。経済的な意味での格差現象も、学歴分断線を反映させながら、しばらくは続いていくと考えるべきでしょう」(p.194)、と。
本書が提供している知見によって、ここ10年ほどこの社会で跋扈した格差社会論は、その主張のかなり本質的な部分に難点があることが露呈したと思います。けれども、安倍政権倒壊の遠因となった<格差社会意識>はこの社会にいまだに根強い。要は、論理としての格差社会論は破綻したけれど、情緒としての<格差社会意識>はこの社会を色濃く覆っている。これが「格差論バブル」が小休止した現在のこの社会の思想風景ではないでしょうか。而して、本書はその情緒としての<格差社会意識>をハーバマスの言う意味での公共圏での理性的討議が可能なイシューに変換する契機になるかもしれない。私はそう考えています。
第三の開国に臨んで考える――開発されるべき日本人の能力とはどのようなものか?
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/4d3ec6f45ce74b0646855a3c122af55f
コラム:「左翼」て何なの-教職員組合を例にとって
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/40427fd974fca7cde4ddaf33a42ced46
ソフトバンクホークス秋山幸二監督に見る<指導者の器>と保守主義の精神
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/ec277ba8d36bcd28834dcd0752624c7a





















