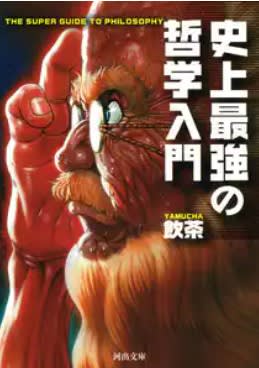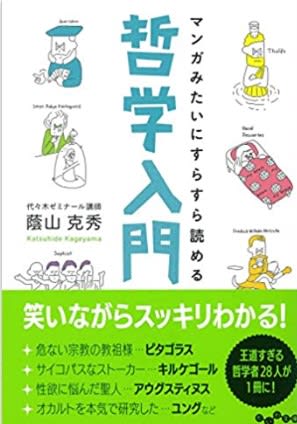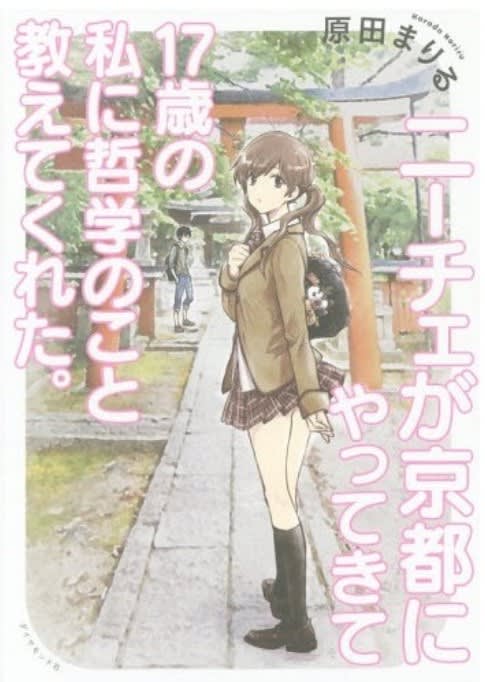「史上最強の哲学入門」飲茶
第二章は<国家の「真理」>たいへんわかりやすく、楽しく勉強させてもらった。自分なりにちょっとまとめて。
<2>国家の「真理」>
▼1. プラトン
― イデア論 本当のもの→本当の政治 アカデメイア(のちの大学)哲人王=哲人政治
―現代の理想の国家論へ連なる思想
▼2. アリストテレス
― 人間はポリス的(社会的)動物である。
― 3つの政治体制とその堕落、そして革命。
君主制 → 独裁 貴族性 → 寡頭(一部の特権階級)制 民主制 → 衆愚制
ー 各々腐敗 ⇒ 革命によって別の政治体制へ
▼3. ホッブズ
― 国家とは自己中心的な人間たちが互いに殺し合わないように自己保存のため作った組織
― リバイアサン 人間は自らリバイアサンという仮想的な怪物を作り出し、その怪物(国家、王)を恐れ服従することで 殺し合わすに生き延びてきた。この安全保障システムが国家の正体。
▼4. ルソー
― 人民主権=国家とは公共の利益を第一に考える民衆のための機関
▼5. アダム・スミス
― 経済学の父 「神の見えざる手」により社会全体の利益に
▼6. マルクス
― 共産主義 ⇒ 時代は、共産主義の終焉を見た
ー そして現在、資本主義も新たな終焉(?)をむかえるか。→新自由主義の時代
⇒ 労働の価値を見失った現代から新しい思想の構築が必要!
非常に厳しい環境の中にある現代の国家、あるいは、日本の国家。政治家が日々苦闘しているように見えるが、どの哲学、国家観をもとに最善を求めているのであろうか。コロナ禍のなかのばらまき政策、グローバル時代といわれた経済の停止、超格差の増大。革命前夜のような現代に我々はどのような国家を目指すべきだろうか、考えさせる<国家の「真理」>の章であった。
<主夫の作る夕食>
冷凍エビをじょうずに解凍して、オリーブオイルで調理してみました。簡単そうに見えてむずかしい。

<もと塾講師のちょっと復習>