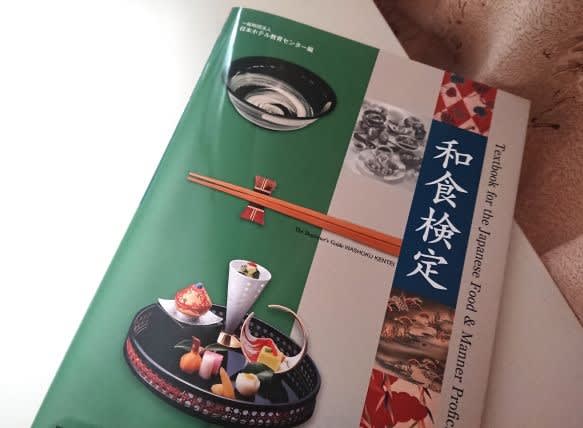こんにちは~♪美容家歴24年のSACHIKOです
和食・日本料理のマナーを学んでいきますと、もっと和食・日本料理を食べたい!という気持ちにさせてくれます。「和食って普段の食事で食べてるから…」と、さほど感動されない方も少なからずいらっしゃると思いますが、テーブルマナー(食卓作法)は、家での食事の仕方と同じではありません。また、家での食事の仕方そのままで日本料理店や和食店を利用していては、同席者に不愉快な思いを与えてしまっているかもしれませんよ。ぜひ、基本である3つの作法「箸の使い方」「器の扱い方」「懐紙の利用」をご紹介したいと思います。
【正しいお箸の使い方:上げ下げの所作】

普段は無造作に慣れ親しんでいるお箸だと思いますが、お箸の扱い方にも作法があります。それは「三手」という方法で箸を上げ下げする所作です。慣れればとっても簡単で、とっても美しい所作!ぜひ身につけていただきたいと思います♪
①右手で箸の中央を掴んで取り上げます
②左手を箸の下に添えます
③右手で後方に滑られて箸の下にくぐり、箸を正しく持つ
お箸を箸置き戻すときは、この逆の三手で戻します。いついかなる場所でも、和食をいただくときはこの三手でお箸を扱ってみてください。このお箸にかけるほんの少し時間が、心にゆとりをもたらしてくれて、目の前の料理にちゃんと向き合う姿勢ができます。

そしてお箸の動かし方は、上の箸だけを動かし下の箸は動かさないのが正しい使い方ですが、これこそ難しいのではないでしょうか。ぜひ、姿勢を正してお箸の動かし方もチェックしてみてください。
次にお箸の休ませ方ですが、箸置きに置く際に口に触れている箸先は、箸置きより3cmほど出して置くようにしましょう。箸置きは、もともとお膳に触れないようにという意味で用意されていますので、お箸を箸置きに置くときは、箸先を少し外に出して置きます。もし箸置きが無い場合は、箸袋で千代結びなどの簡単な箸置きを作って代用するといいです。←"エレ女"(エレガント女子)ならぜひやってね♪
<食事がおわったら…>
食事が終わったら、口につけた箸先をあらわにしておくのはNGマナー。懐紙で箸先を覆うか、または箸袋に戻し、袋の先を折っておけば「使用済み」のお箸であるという合図になりますし、とても清潔感がある終わり方ですから、最後の最後でガッカリなイメージを残さないためにも大事な所作です。
【正しい和食器の扱い方:蓋付きの椀】

洋食では食器は置いたまま食事をします(持つのはNG)が、和食では手に持てるサイズの器は持ち上げて食べるのが原則です。様々な器の中でも、蓋付きの椀を扱う作法をご紹介します。
①左手を椀に添え、右手の親指と人差し指で蓋の糸底(突起部分)の手前を持ち、残りの3本の指で糸底の奥側に添えます。
②蓋を少しずらして手前を上げ、中からもれる香りを楽しみます。
③「の」の字を書くように、蓋を半回しをしながら内側を上に向けて左手を添えます。
④右手を持ち換えて、椀の右奥に置きます。
⑤両手で椀を持ち上げてから箸を取り、椀種や具材をいただきます。
食べ終わったら、上記の逆の手順でお椀の蓋を元に戻します。そして、左上に少し移動させれば、食べ終わった合図になります。
【懐紙を使ってより美しい所作を身に付けよう】

日本料理に限らず、食事をするときにとても便利な懐紙。普段持ち歩いている人は少ないかもしれませんが、実はとっても使い勝手がいいんですよ。
ふところ(懐)に入れる紙と書いてあるように、昔の人は着物の懐に入れて持ち歩いていました。今でゆうところの、ハンカチやティッシュのようなもので、身だしなみの道具として使っていました。それ以外の用途として、メモ帳代わりにも使っていたようです。

和食のお店では、おしぼりはあってもナプキンが無いところもあります。そんな時に懐紙があれば、食事中に汚れた口元を拭いたりすることができます。また、食べ終わったあとの魚の骨を隠すなどして、お皿の上を美しい景色にすることができます。←"エレ女"(エレガント女子)ならぜひやってね♪
さらに、冷たい飲み物を注文したときに、時間が経つとグラスに結露ができてテーブルが塗れてしまうことってありますよね。そんな時に、懐紙をコースター代わりにすると、水気を吸い取ってくれるのでポタポタ水滴を落とさずにすみます。
一番使ってほしい時というのは、和食を食べるときに「手皿」はNGなので、懐紙で取り皿代わりにしていただけると、美しい所作で食事をしていただけます。和紙なので軽く、そしてしっかりとした形状を保てるので使い慣れていただくと、とても便利になりますよ。
・テーブルマナーを身につけたい
・どんなお店でも楽しく食事をしたい
・同伴者に恥をかかせたくない
・自分に自信をつけたい
・堂々と食事ができるようになりたい
という方、テーブルマナー講座に参加しませんか?
♥もっと和食が楽しくなる!日本料理店で学ぶ和食のテーブルマナー
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
遠慮なくお問い合わせください↓↓↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~










 ブロトピ:自分磨き日記~♪
ブロトピ:自分磨き日記~♪ ブロトピ:ブログ更新しました
ブロトピ:ブログ更新しました ブロトピ:食べ歩き・ランチ・お食事など食べ物関連はこちら!
ブロトピ:食べ歩き・ランチ・お食事など食べ物関連はこちら! ブロトピ:今日の生活・文化情報
ブロトピ:今日の生活・文化情報 ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新