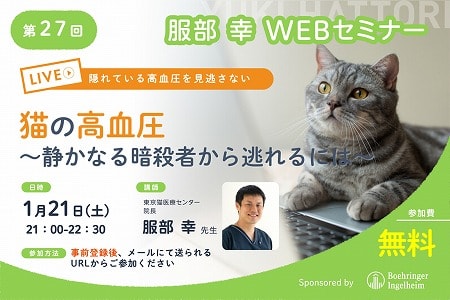昨日の夜は、服部幸先生のオンラインセミナーを聴講しました。
テーマは「猫の尿石症のすべて」
腎臓➡尿管➡膀胱➡尿路に関する疾患について。
猫の保険請求額では、
慢性腎臓病、膀胱炎が上位にありました。
それほど猫には多い疾患なんだと思います。
我が家では、
ずいぶん前に風ちゃんが尿石症になり、
膀胱内の砂状のものを洗い流す手術を受けたことがありました。
ピッチも何度か膀胱炎になったことがありました。
どちらも血尿が出て、尿検査でわかったのですが、
その時、猫の砂はおしっこでぬれても色がつかないものを使っていて
おしっこの後、白い砂にピンクの点を見つけて病院に行きました。
血尿と言っても量はいろいろだと思うので、
他になにか気になること(トイレに頻繁に行くとか)があれば、
是非チェックして、病院に行くことも大切だと思います。
また、食事を変えればいいものと、手術が必要になるものとあるので
そこも気をつけないといけないですね。
風ちゃんの尿石症は、今考えるとストラバイトじゃなくて、
シュウ酸カルシウムだったと思います。
なぜなら処方食で改善しなかったから…。
そして、手術後ご飯を療法食から普通のものに変えても再発せず、
現在に至っていますから。
一番は、水分を多く摂っておしっこを出すことじゃないかと思っています。
なので、我が家ではウェットフード中心にあげていますし、
水も日に何度か入れ替えてなるべく新鮮なものを飲めるようにしています。
水分は水に限らず、鶏肉のゆで汁や、ちゅ~るを水で薄めたものでもいいとのこと。
もちろん、風ちゃんだけでなく、みけちゃんも同じように気をつけています。
外の子はカリカリメインなので、今までもちゅ~るを水で薄めてあげてました。
ネコさんたち、腎臓に関わる病気は特に気をつけてあげたいですね。

猫に限らないと思いますが、
尿石症や結石は、おしっこが出なくなると
急激に症状が進行し、命にかかわることが多いので、
様子見もほどほどに…と思います。