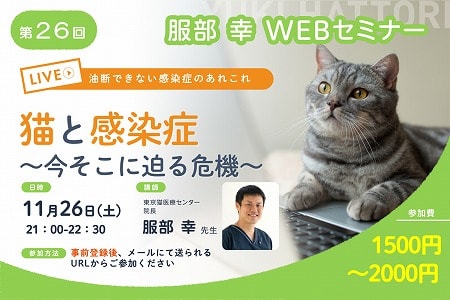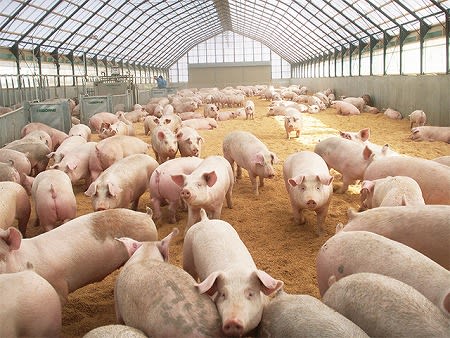今日の朝んぽは、湿度がすごく高くて
軽く歩くだけにしました。(4116歩)
今日は動物愛護管理センターの役割について
遠山 潤 氏(新潟県動物愛護センター センター長)のお話でした。
私は、横浜市動物適正飼育推進員なので、
一般の飼い主さんよりは愛護センターと関わりがあり、
センターのお仕事も活動の中で垣間見ることはあります。
社会全体のため、地域のため、ヒトのための業務で
人の幸せのために、動物も助ける、って感じでしょうか。
また、人と動物が互いに幸せに暮らせる社会
不適切な飼養による、不幸な動物を減らし、収容施設での
殺社分される動物を限りなく減らしていくこと。
譲渡を通じて適正な飼い主を増やす。
などなど。
最近では、犬を家の中で飼う人が多くなったので、
徘徊する犬はだいぶ減ったそうです。
狂犬病予防法により、犬はすぐに保護されます。
飼い主のいない猫については、TNR+Mが大分浸透してきたと思います。
現場にいても数はまぁ落ち着いているようです。
それよりも多頭飼育問題が多いとのことでした。
家の中で繁殖制限をしないで増やしてしまって
匂いや、不衛生な環境で
近隣に迷惑をかけていることも多いです。
そうなってしまう人は、
生後半年ほどで妊娠が可能になること、
交尾すればかならず妊娠すること、
一度に5~6匹ほど生まれること、
1年に2回以上?仔猫が生まれること…などを
知らないことが多いです。
また、相談する人がいなくてどうしていいかわからないうちに
増えてしまうということもあるようです。
同時にかわいそうと拾ってきて増やすケースもあると聞いています。
しかもこのような場所では、健康状態の悪い個体も多くなりますから
なにより、予防が大事ですよね。
我が家の近所でもそういうケースがあり、
ボランティアの方が捕獲し、手術のために病院に搬送し、
病気の子は治療し、仔猫は里親を探し…大変だったそうです。
~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~
という冊子が環境省から出されています。
多頭飼育の予防と予備軍とみられるところに対し社会福祉等と連携して
早期介入することを目指しています。
もし、近隣でそのようなおうちが見受けられたとき、
福祉や介護の方がそういうお宅を訪問したときにも、
ぜひ、地域の行政窓口(生活衛生課等畜犬登録などの係)にご相談ください。
猫を悪者にしないためには、皆さまの協力が必要です。
どうぞよろしくお願いします。
コブシの実