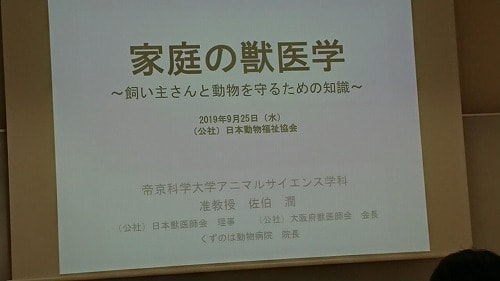7,8日2日間、CDSのお仲間たちと
シェルターメディシンセミナーに行ってきました。
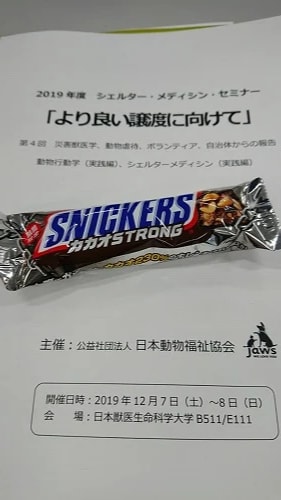
お菓子は協賛企業からの参加賞でした♪
シェルターメディシン(Shelter Medicine)とは…
「伴侶動物の群管理を目的とした獣医医療」です。
シェルターという特殊な環境で暮らす動物たちの「群」としての
健康管理、望ましい生活環境、気質の評価や行動学、
マッチング等現場で最も必要とされる情報を共有し、
それぞれの愛護センター、自治体(災害時同行避難してきたペットたち)、
保護団体やボランティアに関わる人たちが動物たちの福祉も踏まえ、
シェルターでの暮らしを考え、少しでも良い状態で譲渡するためできることを
考えるセミナーでした。
近隣または遠方から行政にかかわる方、愛護センターの方、
預かりボランティアや保護等ボランティアの方も多く参加されていました。
「群管理」の特異性から、感染症蔓延は絶対に避けたいことです。
この危険にさらされないために絶対にやらなければならないことは、
入り口に入る前に生ワクチン接種する。
極端な話、駐車場で接種するともおっしゃっていました。
それほど、「群管理」では病気の予防を徹底しなければならないそうです。
そう考えると、シェルターに収容することより、預かり先に移動させて
そこで「個」として管理することもリスク回避であるということでした。
いま、動愛法の改正に際して、数値基準の問題を提起されています。
シェルターでも、同様で収容場所の広さだけでなく、そこに収容できる
動物の数、お世話する人たちが適切に作業にかかる時間と人数など
動物福祉、完ぺきな作業の基準で計算していくと、
おのずとその施設の収容できる上限が定まってきます。
最近では、自治体の殺処分0のために、保護団体がパンクしそうということも
ニュースで見ます。
なんでもかんでも受け入れるのではなく、そこに携わる人たちと仕事量を
しっかりと算定し、それをするためには、選別も必要な時はあると思います。
「かわいそう」だけで本当に動物の福祉は守られているのか?
もう一度考えなくてはね。
シリーズを重ねるごとに内容はブラッシュアップされているそうです。
来年もシリーズで開催されるそうなので、また参加したいと思います。
★ ★ ★ ★ ★
私は、近隣で猫のTNR+M活動をしています。
今のところ預かりをお願いしている方には、
手術の日程調整をして1頭のみの預かりにしています。
駆虫は必須です。
「かわいそう」だからと家にそのまま置いてしまうことのないように
気をつけています。