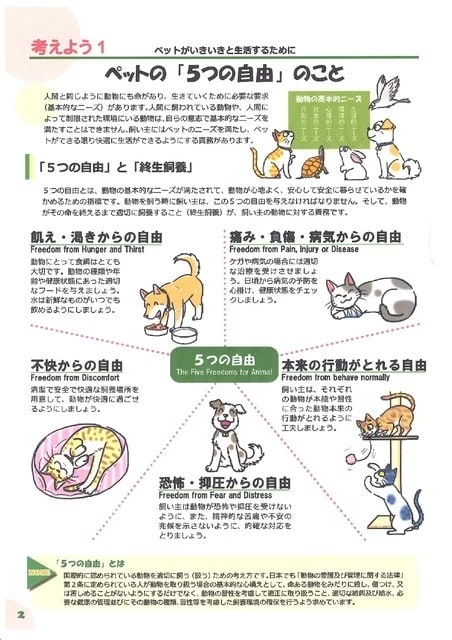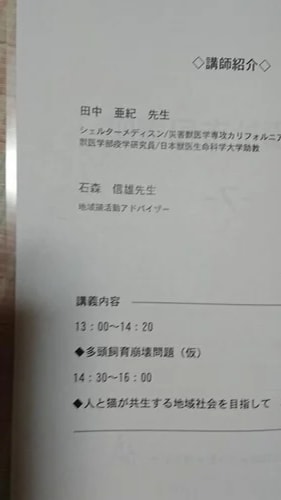今日は動物福祉市民講座 -7-に
CDSのお仲間の小麦のかぁちゃんと参加してきました。
①多頭飼育崩壊問題 田中亜紀先生
ホーダーにはいろいろなタイプがあり、特徴がある。
長期にわたってモニターする必要がある。(再常習率100%)
最近では、特に猫の多頭飼育崩壊がニュースになっていることが多く
なんでこんなになるまでほおっておいちゃったんだろう?と思っていましたが、
「ため込む」という病気や無知だったり相談できない、
まわりに味方になってくれる人がいない孤立だったりと
さまざまな問題があることがわかってきました。
やはりヒト相手なので接触するにも慎重さが必要ですね。
環境省でも、社会福祉との連携の施策を模索中ですが、
なるべく早くガイドラインができるといいなぁと思います。
②人と猫が共生する地域社会を目指して 石森信雄先生
石森先生は行政の方です。
そこでかかわったのら猫対策についてお話されました。
地域住民には・猫好き ・猫嫌い ・好きでも嫌いでもない人…がいて
特に猫好き ・猫嫌いの人がそれぞれの立場を主張しがちだが、
それをコーディネートして、・好きでも嫌いでもない人を
取り込んでいくことが大事。
そのための働きかけ方のお話がありました。
地域猫(飼い主のいない猫)を排除するのではなく、
のら猫トラブルを0を目指す=
個体数を減らし、住民の安心を提供することで
のら猫がいてもイライラしない街づくりを目指す。
この団地では、自治会や管理組合が役員の負担を増やしたくないという理由で
ペット不可を継続するという本末転倒な決定をしています。
また、のら猫についても取り合わないというふうに言われていて、
地域猫活動がしっかり組織だってできない状況です。
横浜市では、町内会や自治会が主導で地域猫活動をすることで
不妊去勢手術の優遇(愛護センターで無料で手術)が受けられます。
ただ、自治会の協力が得られないからと言って
のら猫が増えてしまっては地域住民もねこも幸せではないので、
私たちは粛々とできることを進めていきたいと思っています。
ちゃんと手術して毎日決まった時間にご飯を食べにくるミケちゃん。
TNR+Mです。TNRした後、Managementもしっかり♪
建物のところでご飯をあげているので、
階段の皆さんには告知済み。
ご飯の時間だけ入れ物を出し、終わったら回収。
もちろん外掃除などにはちゃんと参加。
良好な関係を持てるように気配りは必須です。
ねことお世話係の自分が嫌われないように、
後ろ指刺されないようにね(笑)