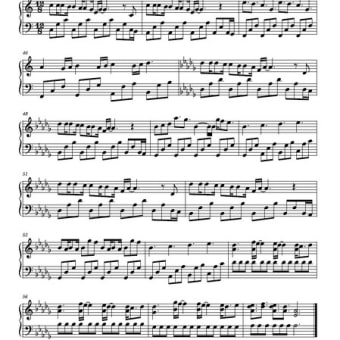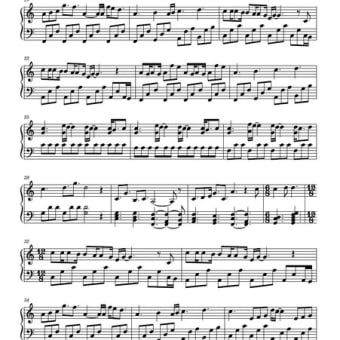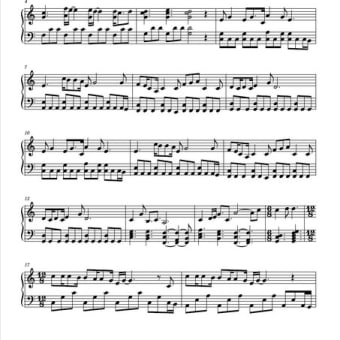・ブルーシートが青いのはなぜ?
・中華料理のテーブルが回るのはなぜ?
・遠くにあるものが小さく見えるのはなぜ?
ブルーシートの色が、
耐候性があり、安く調達可能ということで、
ポリバケツの色から発想された、
というのは面白かった。
中華料理の回転テーブルは、
チップの習慣が定着しなかった日本で、
セルフサービスのために生まれた
というのも、なかなか味わい深い。
しかし、あんなもの
よく発明したと思う。
最後の問題は物理だから、
問題そのものは面白くはなかったが、
解説ビデオの中で出てきた、
人や物が小さく見える写真が
ちょっと面白かった。
同じ平面上でも、小さく描くことで遠くにあるように見える
のが絵画の遠近法だが、逆に、同じ平面にない物も、
同じ平面にあるように見せると、小さく見える。
ウユニ湖で男性と女性が向き合って
女性が男性を見上げている写真は、
足元を見ると、女性のほうが遠くにいるのがわかるのだが、
女性が男性の手を見上げている部分を見ると
同じ位置にいるように見えるので、
女性が小人のように見える。
椅子の脚と座面が実は別の場所にある
というのもおもしろかった。
これらが面白く感じられるのは、
「同じ平面、距離にある」ということを
何を手掛かりに判断しているか、
ということと関係している。
普段、二つの眼で3次元を見ているときは、
両方の眼の視差を使って距離が測れるのだが、
どちらもある程度遠くにあって視差が小さいときや、
写真だと、視差の情報は使われなくて、
上にあるものを見ているのだから近くにあるはず、とか、
全体として椅子である、というような、
かなり高度な認識と、位置関係、距離の判断が
関連しているということだ。
このほかにも、働き方改革のコーナーの
アオアシカツオドリ(足の青さがセックスアピールとして進化)や、
コウロコフウチョウのダンスも面白かった。
最新の画像もっと見る
最近の「雑感」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事