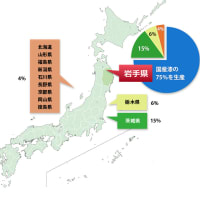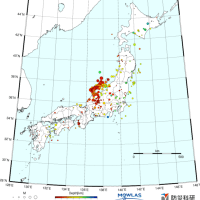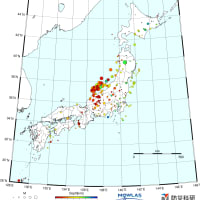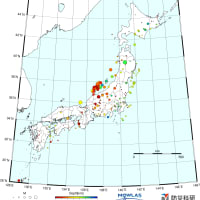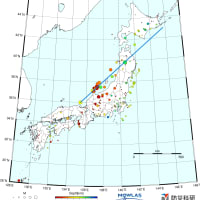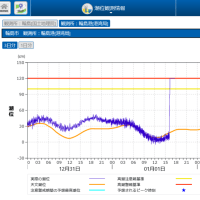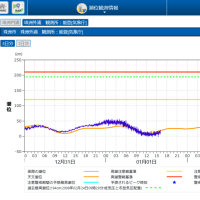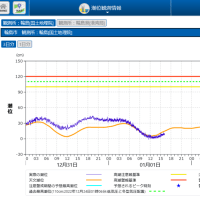2016年2月1日の拙ブログを再掲
ーある日ネット上で、慰安婦問題に関わる記事の中に、この問題とは縁遠いはずなのにと訝しく思いながらも懐かしい名前を見つけた。
それは仏文学者の田辺(田邉)貞之助先生の名前だった。
昔受けた田辺先生のフランス語の講義は、古き良き時代の東京の話だとか洒落話が満載で、とても楽しいものであった。
大方の記憶が薄らいでしまったのは残念であるが、ある夏の暑い日、先生は「暑い、暑い。」と言いながら、講義室に入って来られた。エアコンなどない時代のことで、学生に窓を大きく開けさせると、いつものように「その昔」という感じで、話は始まった。
「僕が暁星中学で教えていた時の話だ。フランス人の女教師が何やらブツブツ言いながら、廊下を向こうから来やがるんだ。『しょー、しょー、しょー』と言ってるんだ。すぐに判らなかったんだが、『chaud,chaud,chaud.』と言ってたんだ。講義じゃ『Il fait chaud.』と教わるが、そんな堅苦しいことを言うはずはないだろ。話し言葉というものは大概そんなもんだ。」という具合に。
あの洒脱な江戸っ子の田辺先生が、どうして慰安婦問題と関係が、と思い、ネットの記事を読んでみると、先生の『女木川界隈』(小名木川の古名、芭蕉の句碑にも女木川、とあるので借用した、と前書きにある。)という随筆集の中に、関東大震災の記憶がつづられており、朝鮮人虐殺に関わる記述があるのだ、という。
関東大震災の話は何度か聞いていたはずだったが、そんな生々しい話はきいた記憶がなかった。
調べてみると『女木川界隈』は昭和37年刊だったが、amazonで容易にみつかり、まるで新品のような本が二日もすると手元に届いた。往年の田辺先生の洒脱でユーモアに富んだ語り口が蘇ってくるような楽しい随筆集であったのだが、この話だけは別であった。
旧制第一高等学校の一年生であった田辺先生が、始業式から帰宅し、昼飯を口に運ぼうとしていたその矢先、大きな揺れに襲われたところから始まる「新巻の鮭」という話は、被害の大きさが明らかにつれ、次第に不安に満ち深刻な話になってゆく。
武装した朝鮮人が襲って来るという流言蜚語が広まり、自警団が結成された。大震災発生後四日目になると、家が兵隊さんを泊める屯所に定められ、銃剣に染みついた血が中々落ちないため、兵隊さんに磨き砂を求められ、それを何に使ったか知ったお母さんが磨き砂の入った箱を投げ捨てる場面など、次第に話は凄惨さを増してくる。
虐殺された遺体の有様について淡々とした記述が続き、余りに客観的で冷静なので、読んでいるこちらが驚くほどだが、その細部にわたる描写から、若かりし日の田辺先生がいかに大きな衝撃を受け、その記憶が脳裏に深く刻みつけられたのかがわかる。
『(中略)まだ若いらしい女が―女の死体はそれだけだったが―腹をさかれ、六七ヵ月になろうかと思われる胎児が、はらわたのなかにころがっていた。が、その女の陰部にぐさりと竹槍がさしてあるのに気づいたとき、ぼくは愕然として、わきへとびのいた。われわれの同胞が、こんな残酷なことまでしたのだろうか。いかに恐怖心に逆上したとはいえ、こんなことまでしなくてもよかろうにと、ぼくはいいようのない怒りにかられた。日本人であることを、あのときほど恥辱に感じたことはない。』
ここまで書いてきて、「新巻の鮭」という題名が何を指すのかを語る気持ちがすっかり失せてしまった。
慰安婦問題にしろ、南京大虐殺にしろ、「事実と異なり、被害者数や規模に誇張がある。」と主張する人々は、誇張と思われるその表現こそが、被害者の計り知れない心の傷の深さを表わしていることに気づくべきである。
そのことに気づかないで、頑なに自論の客観性や論理性の正しさばかり主張しても、必ずしも理解は得られないように思う。
別に中国や朝鮮半島の人々に媚びを売っているわけでも何でもない。このままでは日本人が同じ目に遭うだろう。子どもや若者の行く末が心配である。
以前、香港マカオを旅行した時のことである。澳門博物館を訪れたところ、『抗戦時期的澳門』展が開催されていた。内容が予想できたので、引き返そうかと思ったが、思いなおして入ってみた。
キッズコーナーでは、人感センサーつきの銃剣を持った旧日本兵の作り物が、叢から飛び出して剣先を突き付けてくるのだった。ああ、恨み骨髄に徹すとはこのことか。子どものころからこういう教育をされているのだ、と末恐ろしくなった。映画シアターは立ち見が沢山いて、皆真剣な面持ちで記録映画の画面を見つめていた。無言でそぅっと入ったのだが、当時はどことなく雰囲気が違うためか、すぐに日本人と気づかれ、周囲から穴のあくほどジロジロ見られ、恫喝されるのではないかと冷や汗が出たものだった。
日本はこれまで十分に補償を行ったはず、と思っている人も多いだろう。しかし、肉親や同胞を銃剣で突かれ目の前で殺された人間が、いくら金を積まれたからと言って、その心の傷まで癒されることはないはずである。
一体いつまで謝り続ければよいのだ、という問題ではない。
これは、人間的、根源的な感情のせめぎあいの問題だと考える。
田邉貞之助先生がこのようなことを書いておられたことは知らなかった。今回再びまみえることになったのは幸いであった。
『ふらんす伝説大観』という著書にサインを頂きにいったところ、「一体、君はこれを読むことはあるのかねぇ。」と言いながらサインを呉れた。そこに「田辺貞之助」ではなく「田邉貞之助」と書かれたのである。
あれから数十年、その本は私の書棚に眠ったままである。―
それは仏文学者の田辺(田邉)貞之助先生の名前だった。
昔受けた田辺先生のフランス語の講義は、古き良き時代の東京の話だとか洒落話が満載で、とても楽しいものであった。
大方の記憶が薄らいでしまったのは残念であるが、ある夏の暑い日、先生は「暑い、暑い。」と言いながら、講義室に入って来られた。エアコンなどない時代のことで、学生に窓を大きく開けさせると、いつものように「その昔」という感じで、話は始まった。
「僕が暁星中学で教えていた時の話だ。フランス人の女教師が何やらブツブツ言いながら、廊下を向こうから来やがるんだ。『しょー、しょー、しょー』と言ってるんだ。すぐに判らなかったんだが、『chaud,chaud,chaud.』と言ってたんだ。講義じゃ『Il fait chaud.』と教わるが、そんな堅苦しいことを言うはずはないだろ。話し言葉というものは大概そんなもんだ。」という具合に。
あの洒脱な江戸っ子の田辺先生が、どうして慰安婦問題と関係が、と思い、ネットの記事を読んでみると、先生の『女木川界隈』(小名木川の古名、芭蕉の句碑にも女木川、とあるので借用した、と前書きにある。)という随筆集の中に、関東大震災の記憶がつづられており、朝鮮人虐殺に関わる記述があるのだ、という。
関東大震災の話は何度か聞いていたはずだったが、そんな生々しい話はきいた記憶がなかった。
調べてみると『女木川界隈』は昭和37年刊だったが、amazonで容易にみつかり、まるで新品のような本が二日もすると手元に届いた。往年の田辺先生の洒脱でユーモアに富んだ語り口が蘇ってくるような楽しい随筆集であったのだが、この話だけは別であった。
旧制第一高等学校の一年生であった田辺先生が、始業式から帰宅し、昼飯を口に運ぼうとしていたその矢先、大きな揺れに襲われたところから始まる「新巻の鮭」という話は、被害の大きさが明らかにつれ、次第に不安に満ち深刻な話になってゆく。
武装した朝鮮人が襲って来るという流言蜚語が広まり、自警団が結成された。大震災発生後四日目になると、家が兵隊さんを泊める屯所に定められ、銃剣に染みついた血が中々落ちないため、兵隊さんに磨き砂を求められ、それを何に使ったか知ったお母さんが磨き砂の入った箱を投げ捨てる場面など、次第に話は凄惨さを増してくる。
虐殺された遺体の有様について淡々とした記述が続き、余りに客観的で冷静なので、読んでいるこちらが驚くほどだが、その細部にわたる描写から、若かりし日の田辺先生がいかに大きな衝撃を受け、その記憶が脳裏に深く刻みつけられたのかがわかる。
『(中略)まだ若いらしい女が―女の死体はそれだけだったが―腹をさかれ、六七ヵ月になろうかと思われる胎児が、はらわたのなかにころがっていた。が、その女の陰部にぐさりと竹槍がさしてあるのに気づいたとき、ぼくは愕然として、わきへとびのいた。われわれの同胞が、こんな残酷なことまでしたのだろうか。いかに恐怖心に逆上したとはいえ、こんなことまでしなくてもよかろうにと、ぼくはいいようのない怒りにかられた。日本人であることを、あのときほど恥辱に感じたことはない。』
ここまで書いてきて、「新巻の鮭」という題名が何を指すのかを語る気持ちがすっかり失せてしまった。
慰安婦問題にしろ、南京大虐殺にしろ、「事実と異なり、被害者数や規模に誇張がある。」と主張する人々は、誇張と思われるその表現こそが、被害者の計り知れない心の傷の深さを表わしていることに気づくべきである。
そのことに気づかないで、頑なに自論の客観性や論理性の正しさばかり主張しても、必ずしも理解は得られないように思う。
別に中国や朝鮮半島の人々に媚びを売っているわけでも何でもない。このままでは日本人が同じ目に遭うだろう。子どもや若者の行く末が心配である。
以前、香港マカオを旅行した時のことである。澳門博物館を訪れたところ、『抗戦時期的澳門』展が開催されていた。内容が予想できたので、引き返そうかと思ったが、思いなおして入ってみた。
キッズコーナーでは、人感センサーつきの銃剣を持った旧日本兵の作り物が、叢から飛び出して剣先を突き付けてくるのだった。ああ、恨み骨髄に徹すとはこのことか。子どものころからこういう教育をされているのだ、と末恐ろしくなった。映画シアターは立ち見が沢山いて、皆真剣な面持ちで記録映画の画面を見つめていた。無言でそぅっと入ったのだが、当時はどことなく雰囲気が違うためか、すぐに日本人と気づかれ、周囲から穴のあくほどジロジロ見られ、恫喝されるのではないかと冷や汗が出たものだった。
日本はこれまで十分に補償を行ったはず、と思っている人も多いだろう。しかし、肉親や同胞を銃剣で突かれ目の前で殺された人間が、いくら金を積まれたからと言って、その心の傷まで癒されることはないはずである。
一体いつまで謝り続ければよいのだ、という問題ではない。
これは、人間的、根源的な感情のせめぎあいの問題だと考える。
田邉貞之助先生がこのようなことを書いておられたことは知らなかった。今回再びまみえることになったのは幸いであった。
『ふらんす伝説大観』という著書にサインを頂きにいったところ、「一体、君はこれを読むことはあるのかねぇ。」と言いながらサインを呉れた。そこに「田辺貞之助」ではなく「田邉貞之助」と書かれたのである。
あれから数十年、その本は私の書棚に眠ったままである。―