
 29/22℃ お彼岸の中日
29/22℃ お彼岸の中日
四方の青竹でしめ縄の屋外能舞台は神戸市内の識者が左右のかがり火籠燈籠に点火して薪能の雰囲気が出てきた。

最終の演目なので小用を済まして席に戻ると響き渡る鼓の音があり始まっていたが能の演目は「土蜘蛛」とあり、源頼光(平安中期の武将で摂津源氏)の土蜘蛛退治の能で最後の演目だった。「源頼光の大蜘蛛退治」子供の頃絵本で見たような気がする。

調べてみると源頼光は平安中期の武将で摂津国多田(兵庫県多田)源氏の開祖で蜘蛛の妖怪(天皇に恭順しなかった土豪)を成敗した武将だったとされている。


野外能舞台は土蜘蛛成敗の最後の山場


源頼光は土蜘蛛(土豪)成敗し時の天皇に恭順させたたようです。
能”は室町時代初期から足利義満により安土桃山時代に完成された日本の舞台芸能で織豊時代の信長・秀吉に親しまれ、さらに徳川幕府の藩政時代に大名や高級武士に普及し武家社会の諸芸能として明治初期まで定着した。 現在の能楽の流派は五流家あり金剛流波は京都で本部のある、唯一の流派で日本の伝統芸能であり、国の重要無形文化財であり、ユネスコの無形文化遺産になっているそうです。

能舞台は20時前に終演し帰りは丹波の枝つき枝豆のお土産付で生田神社の楼門の東南の夜空には満月が綺麗に輝いていた。



















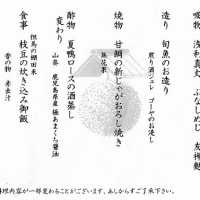
どちらにしましても、舞台が、近いので、凄い迫力だったでしょうね、それに、火を使うので大した物だったと思います。
これは観劇に、近いものだとは、思いますが、何を現した物なのでしょうか、先祖を敬うとか・・・・・・? それにしましても、楼門と満月は絵に成りますね-。
何時もコメント
歌舞伎の大立廻りより派手ではありませんが、謡曲に合わせた能と思いました。
日本の伝統芸能は神に奉納する舞からのような気がします。