フランソワ・モーリャックのこの有名な小説は10代の頃読んだ記憶があるが、
内容はほとんど覚えていなかった。
日本里帰りの際の、飛行機内で見た映画の一つが
『テレーズ・デスケルゥ』であったのだが、
正直言って、内容がよく把握できなかったので、
日本で遠藤周作訳の小説の文庫本を買って読んでみたら、
ますます混乱した。
時をおいて、何度か読み返し、ようやく自分の中で、
この小説の持つ魅力が理解できるように
なってきたような気がしている。
モーリャックも遠藤周作も、カトリック作家、として
世間では知られているが、まず
「カトリック」という先入観を排除しなければ、
冷静にこの小説の評価はできないであろう。
カトリックの観点から罪や道徳や救いを描いた小説ではなく、
まず小説家としてのモーリャックがあり、
そしてモーリャック自身がカトリックであった、という
認識のもとにこの作品を『小説』として読むことによって、
モーリャックが仕掛けた迷路から
抜け出すことができるのだ。
私は小説を読むとき、作家はなぜこのような表現をしたのだろう、とか、
なぜこの人物はこのような言動をするのだろう、
と言う疑問を持ちながら読み進める。まるで推理小説をよむように。
というのも書かれた言葉の背後には必ずなにかしら
意味があるからである。
もちろん、それが小説の価値を直接決めるものではなく、
作家が意味したことと、読者が読み取るものとの関係には
つねにずれが生じる可能性を含んでいる。
しかし『テレーズ・デスケルゥ』においては、
冒頭から大きな疑問があった。
それは、まえがきの部分のことである。
テレーズ、あなたのような女がいるはずはないと
多くの人がいう。
だがぼくにはあなたは存在しているのだ。
長い歳月の間、ぼくはあなたを探り時には追いすがり、
その素顔をみつけようとしてきたからだ。
この書き出し部分に言及する人は多い。
しかし私にはこの文章に続く次の部分がつねに頭にひっかかったのである。
あれは青年のころだった。
あなたは裁判所の息苦しい法廷で、
弁護士たちに自分の運命をゆだねていた。
その弁護士たちは傍聴席につめかけている着飾った婦人にくらべれば
まだ人間味があった。
あなたの顔は小さく白く、唇には血の気がなかった。
つまり、モーリャックは自分がその法廷で実際にテレーズを見た、と
まえがきで証言しているのである。
ところが、いざ小説の本文に入ると、モーリャックという目撃者は
姿をくらませてしまう。
小説はテレーズが裁判所の暗い裏廊下で、弁護士から「免訴です」と
告げられるところから始まる。そして
彼女と父親と弁護士のデュロースの三人は町はずれの街道に
待たせておいた車へと歩いていく。
ここからアルジュルーズの夫の待つ家までの家路のあいだ、
テレーズは虚偽の証言で自分を救ってくれた
夫のベルナールに「告解」をして許してもらえば楽になる、と考えた、
そして夫にわかってもらうためには、どのように話そうか、
と思いあぐねるのである。
しかしテレーズ自身、なぜあのような罪を犯したのか、自分でもよくわからないのだ。
彼女は少女時代までにさかのぼって回想する。
三人称で語られる少女時代から結婚、妊娠、
そして親友であり、また義理の妹であるアンヌの恋の告白のこと…。
そのアンヌの恋の相手、
ジャン・アゼヴェド青年にアンヌと別れるよう、
テレーズが一人で話をしに行く時から、
「わたし」という一人称に変わる。アゼヴェドと会った時のことは、
一人称のモノローグとして語られるのである。
こうしたフラッシュバックによって、読者はモーリャックと一緒に、
その半生をなぞっていくわけだが、それはテレーズの内面の物語でもあり、
モーリャック自身、彼女の心を追って、なぜあのような行為をしたのか、
さぐっていく旅でもあるのだ。
家路の果て、ついにベルナールがテレーズの目の前に現れた時、
それまでは話し合ってわかってもらえる、
と思ったテレーズの希望がすべてくだけてしまうのである。
今、夫をちらっと見ただけでありのままのこの男の姿が
浮かび上がった。
生涯に一度でも、他人の場に立ってものを考えることのできない男
――自分自身から抜け出て、
相手が見ているものを見ようとする努力をしない人間。
この瞬間から、テレーズとベルナールの関係が逆転する。どちらが被害者で、
どちらが加害者か…。
テレーズが自殺を考え、死後の世界について恐怖を感じ、自分を卑怯だ、と恥じる。
そして初めて母親として子供に慈悲の心を示すのである。
もしあわれな盲目の魂が道を外れたとしても、
それが神の意志ならば、
神は少なくとも愛を持ってこの罪びとである被造物を
だきしめてくださるのではないか。
今まで神を信じていなかったテレーズが回心を試み、
自ら死の世界に飛び込もうとした瞬間、
年取った伯母のクララの急死によって、その実行は阻止されてしまうのだ。
そのときから、テレーズは、生きる屍のように生きる決心をする。
そしてその苦しみがこの世で生きる支えになっていくのである。
ベルナールは「生きる屍」となったテレーズの姿を見て、少年のときに見た
「ポワチエの女囚」という絵を思い出す。彼はテレーズに憐みを感じ、
彼女を解放することを了解する。
テレーズをパリまで送っていったベルナールはテレーズを理解しよう、
と最後の努力をする。
しかしやはりベルナールには無理だったのだ。
テレーズは言う。
「あなたのような人間は、いつも
自分の行為の動機がわかるのね」。
ランドの良家に嫁いで満足していたテレーズという女のために、
もう一人の別人のテレーズを犠牲にする理由などなかった、と言う
テレーズの言葉をベルナールは理解できない。
ベルナールは一瞬でも心を動かされたことに
いらだちをおぼえていた。
自分のしなれない動作に対する嫌悪や、平生使い慣れていた言葉と
違う言葉を使った嫌悪しか感じなかった。
ベルナールにとっては家の名誉のためには
「腐った手足を人々の面前で切り取って捨て、これを否認する」ことが
一番大切なのである。
パリで、「きっちりと敷かれた車輪のように道幅にあわせる人生を何の疑いもなく
歩んでいる人々の住む世界」から、テレーズは自由になろうとしている。
しかし、なぜ、あんなことをしたのか…。
今、あたし、『自分でもなぜそうしたのかわからない』と言いかけたんだけど・・・・・
おそらくあなたの目の中に不安と好奇心の色を見たかったのかもしれないわ、
―― つまりあなたの心の動揺よ。さっきからあなたの目にあるものよ。
つまり、いつも自信満々なベルナールに、少しでも人間的な弱さがあることを、
彼女は知りたかったのである。
それを「罪」とし、神の慈悲によって「救われた」ということを、
モーリャックは言っているのではない。
罪であるかどうか、救いであるかどうか、それは読む側に
さらに疑問を投げかける。
冒頭に記した、まえがきの部分に戻る。
青年の頃、裁判所の息苦しい法廷で、弁護士たちに自分の運命をゆだねていた
蒼白な顔の女性を、
モーリャックは実際に見たのであった。
その女性の名前は、アンリエット・カナビー(一説によると
ブランシュ・カナビーという名前)。
1905年、ボルドーの葡萄酒仲買人の夫に大量の毒薬を与えた罪で告訴され、
1906年、劇薬の処方箋偽造の罪に問われたが、夫の証言により、
殺人罪を免れた女性の重罪裁判所での公判に、
若きモーリャックは立ち会っていたのである。
その後1925年になってから、モーリャックは兄のピエールに
公判の書類を入手するよう依頼した、という。
「テレーズ・デスケルゥ」が小説として発表されたのは、
その2年後の1927年のことであった。
だから、テレーズはモーリャックのまったくの空想の人物ではないのである。
アンリエット(あるいはブランシュ)・カナビーがなぜあのような罪を犯したか、
それをテレーズという女性になりきって
その心の苦悩を追求して書いた、小説なのである。
内容はほとんど覚えていなかった。
日本里帰りの際の、飛行機内で見た映画の一つが
『テレーズ・デスケルゥ』であったのだが、
正直言って、内容がよく把握できなかったので、
日本で遠藤周作訳の小説の文庫本を買って読んでみたら、
ますます混乱した。
時をおいて、何度か読み返し、ようやく自分の中で、
この小説の持つ魅力が理解できるように
なってきたような気がしている。
モーリャックも遠藤周作も、カトリック作家、として
世間では知られているが、まず
「カトリック」という先入観を排除しなければ、
冷静にこの小説の評価はできないであろう。
カトリックの観点から罪や道徳や救いを描いた小説ではなく、
まず小説家としてのモーリャックがあり、
そしてモーリャック自身がカトリックであった、という
認識のもとにこの作品を『小説』として読むことによって、
モーリャックが仕掛けた迷路から
抜け出すことができるのだ。
私は小説を読むとき、作家はなぜこのような表現をしたのだろう、とか、
なぜこの人物はこのような言動をするのだろう、
と言う疑問を持ちながら読み進める。まるで推理小説をよむように。
というのも書かれた言葉の背後には必ずなにかしら
意味があるからである。
もちろん、それが小説の価値を直接決めるものではなく、
作家が意味したことと、読者が読み取るものとの関係には
つねにずれが生じる可能性を含んでいる。
しかし『テレーズ・デスケルゥ』においては、
冒頭から大きな疑問があった。
それは、まえがきの部分のことである。
テレーズ、あなたのような女がいるはずはないと
多くの人がいう。
だがぼくにはあなたは存在しているのだ。
長い歳月の間、ぼくはあなたを探り時には追いすがり、
その素顔をみつけようとしてきたからだ。
この書き出し部分に言及する人は多い。
しかし私にはこの文章に続く次の部分がつねに頭にひっかかったのである。
あれは青年のころだった。
あなたは裁判所の息苦しい法廷で、
弁護士たちに自分の運命をゆだねていた。
その弁護士たちは傍聴席につめかけている着飾った婦人にくらべれば
まだ人間味があった。
あなたの顔は小さく白く、唇には血の気がなかった。
つまり、モーリャックは自分がその法廷で実際にテレーズを見た、と
まえがきで証言しているのである。
ところが、いざ小説の本文に入ると、モーリャックという目撃者は
姿をくらませてしまう。
小説はテレーズが裁判所の暗い裏廊下で、弁護士から「免訴です」と
告げられるところから始まる。そして
彼女と父親と弁護士のデュロースの三人は町はずれの街道に
待たせておいた車へと歩いていく。
ここからアルジュルーズの夫の待つ家までの家路のあいだ、
テレーズは虚偽の証言で自分を救ってくれた
夫のベルナールに「告解」をして許してもらえば楽になる、と考えた、
そして夫にわかってもらうためには、どのように話そうか、
と思いあぐねるのである。
しかしテレーズ自身、なぜあのような罪を犯したのか、自分でもよくわからないのだ。
彼女は少女時代までにさかのぼって回想する。
三人称で語られる少女時代から結婚、妊娠、
そして親友であり、また義理の妹であるアンヌの恋の告白のこと…。
そのアンヌの恋の相手、
ジャン・アゼヴェド青年にアンヌと別れるよう、
テレーズが一人で話をしに行く時から、
「わたし」という一人称に変わる。アゼヴェドと会った時のことは、
一人称のモノローグとして語られるのである。
こうしたフラッシュバックによって、読者はモーリャックと一緒に、
その半生をなぞっていくわけだが、それはテレーズの内面の物語でもあり、
モーリャック自身、彼女の心を追って、なぜあのような行為をしたのか、
さぐっていく旅でもあるのだ。
家路の果て、ついにベルナールがテレーズの目の前に現れた時、
それまでは話し合ってわかってもらえる、
と思ったテレーズの希望がすべてくだけてしまうのである。
今、夫をちらっと見ただけでありのままのこの男の姿が
浮かび上がった。
生涯に一度でも、他人の場に立ってものを考えることのできない男
――自分自身から抜け出て、
相手が見ているものを見ようとする努力をしない人間。
この瞬間から、テレーズとベルナールの関係が逆転する。どちらが被害者で、
どちらが加害者か…。
テレーズが自殺を考え、死後の世界について恐怖を感じ、自分を卑怯だ、と恥じる。
そして初めて母親として子供に慈悲の心を示すのである。
もしあわれな盲目の魂が道を外れたとしても、
それが神の意志ならば、
神は少なくとも愛を持ってこの罪びとである被造物を
だきしめてくださるのではないか。
今まで神を信じていなかったテレーズが回心を試み、
自ら死の世界に飛び込もうとした瞬間、
年取った伯母のクララの急死によって、その実行は阻止されてしまうのだ。
そのときから、テレーズは、生きる屍のように生きる決心をする。
そしてその苦しみがこの世で生きる支えになっていくのである。
ベルナールは「生きる屍」となったテレーズの姿を見て、少年のときに見た
「ポワチエの女囚」という絵を思い出す。彼はテレーズに憐みを感じ、
彼女を解放することを了解する。
テレーズをパリまで送っていったベルナールはテレーズを理解しよう、
と最後の努力をする。
しかしやはりベルナールには無理だったのだ。
テレーズは言う。
「あなたのような人間は、いつも
自分の行為の動機がわかるのね」。
ランドの良家に嫁いで満足していたテレーズという女のために、
もう一人の別人のテレーズを犠牲にする理由などなかった、と言う
テレーズの言葉をベルナールは理解できない。
ベルナールは一瞬でも心を動かされたことに
いらだちをおぼえていた。
自分のしなれない動作に対する嫌悪や、平生使い慣れていた言葉と
違う言葉を使った嫌悪しか感じなかった。
ベルナールにとっては家の名誉のためには
「腐った手足を人々の面前で切り取って捨て、これを否認する」ことが
一番大切なのである。
パリで、「きっちりと敷かれた車輪のように道幅にあわせる人生を何の疑いもなく
歩んでいる人々の住む世界」から、テレーズは自由になろうとしている。
しかし、なぜ、あんなことをしたのか…。
今、あたし、『自分でもなぜそうしたのかわからない』と言いかけたんだけど・・・・・
おそらくあなたの目の中に不安と好奇心の色を見たかったのかもしれないわ、
―― つまりあなたの心の動揺よ。さっきからあなたの目にあるものよ。
つまり、いつも自信満々なベルナールに、少しでも人間的な弱さがあることを、
彼女は知りたかったのである。
それを「罪」とし、神の慈悲によって「救われた」ということを、
モーリャックは言っているのではない。
罪であるかどうか、救いであるかどうか、それは読む側に
さらに疑問を投げかける。
冒頭に記した、まえがきの部分に戻る。
青年の頃、裁判所の息苦しい法廷で、弁護士たちに自分の運命をゆだねていた
蒼白な顔の女性を、
モーリャックは実際に見たのであった。
その女性の名前は、アンリエット・カナビー(一説によると
ブランシュ・カナビーという名前)。
1905年、ボルドーの葡萄酒仲買人の夫に大量の毒薬を与えた罪で告訴され、
1906年、劇薬の処方箋偽造の罪に問われたが、夫の証言により、
殺人罪を免れた女性の重罪裁判所での公判に、
若きモーリャックは立ち会っていたのである。
その後1925年になってから、モーリャックは兄のピエールに
公判の書類を入手するよう依頼した、という。
「テレーズ・デスケルゥ」が小説として発表されたのは、
その2年後の1927年のことであった。
だから、テレーズはモーリャックのまったくの空想の人物ではないのである。
アンリエット(あるいはブランシュ)・カナビーがなぜあのような罪を犯したか、
それをテレーズという女性になりきって
その心の苦悩を追求して書いた、小説なのである。
参考:
『テレーズ・デスケルウ』モーリアック 遠藤周作 訳 講談社文芸文庫
Therese Desqueyroux fr.wikipedia.org
Mauriac (1885-1970) Therese Desqueyroux (1927) Therese Desqueyroux ou l'itineraire d'une femme libre
Etudeslitteraires www.etudes-litteraires.com














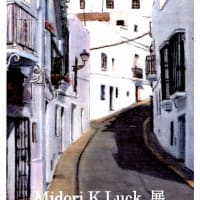





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます