昨晩遅く、犬が吠えた。夜更かししてようやく眠りについたころだったので
起きるのが億劫だったが、犬は鳴きやまない。
しかたなく起きだしてなだめに行くと、
犬はおとなしくなったが、今度はわたしの目が冴えて寝付けない。
ベッドに寝転がって、iPadでTwitter を見ていたら、
「ほぼ日刊イトイ新聞」のツイートで、
きょう6月19日が桜桃忌なので、吉本隆明氏の
太宰治に関する講演をアップした、とある。
糸井重里氏が発行している「ほぼ日刊イトイ新聞」では
吉本隆明の183講演を、ただでダウンロードできる
素晴らしいサービスをしてくれているのだ。
以前、なんの講演だったか忘れたが、聞いてみたのだが、
あの難解な文章で知られる吉本隆明氏の、
実際には口下手で、朴訥と言っていいような話し方が
もどかしく、いつのまにか居眠りしてしまったことがあったので、
本日新しくアップされた講演は121分もあって長いから、
きいているうちに眠りにつくだろう、
子守唄のかわりにしようという、吉本隆明氏には
そして糸井重里氏にも、はなはだ不謹慎な動機で
ききはじめたのだが、いやはや、あの朴訥な話し方でさえ
気にならないような内容で、結局最後まで
全部聞いてしまったのであった。
吉本氏が好きな作家は、太宰治、宮沢賢治、そして親鸞だそうだ。
太宰のことは、「短編の名手」、「天才」と賞賛している。
太宰は志賀直哉に対して、小説にはおののきが必要だ、
お前の小説にはおののきがないじゃないか、と絡んだことがあるそうだ。
そして小説は書きはじめの数行ですべて決定する、
書きだしてみないと小説の行方はわからない、無事小説が終わるのかどうか
書いてみないと最後までわからない、と言っていたそうである。
その太宰に影響を及ぼしたのは、まず落語であった、と吉本氏は
意外なことをおっしゃる。太宰は落語をよく読んで、小説の
オチも落語的である、というのだ。
そしてもう一つは森鴎外の翻訳した短編小説の影響である、という。
吉本氏によると、鴎外自身は短編はあまり得意ではないらしい。
しかし訳した短編は素晴らしい。その短編の一つにドイツの
オイゲンベルグという作家の書いた『女の決闘』という作品が
あって、太宰はこれを徹底的につきくずし、分析し、
そして自分自身で勝手に構成しなおして、同じ題名の短編小説を書いた。
吉本氏は言う。作家は小説を書く際、作為性を隠すことによって
ドラマ性をもりたてる。しかし文体分析をして、作家と
作中人物の距離を見れば、位置のとり方があいまいな作品は
どこか通俗性がある。大衆小説とはちがう、通俗小説の特徴として
どんなに文学作品にみえても、読む側が直感的に作家と登場人物の
距離にあいまいさを感じた場合、通俗であることを確かめられるのである。
つまり、作家が意識なくして作品に入ってきてしまう描写、そういう
曖昧な描写が混入していることに気付いたとき、その小説を
崩す、というのが20世紀の解体の芸術なのである。
と、吉本氏は言って、オイゲンベルグの『女の決闘』のあらすじを
かなり詳細に語るのであるが、それはこんな内容である。
ロシアのどこかの町で若い女の医学生のところに手紙が届く。
それはある女からで、その女の亭主が女学生と関係をもったことを知ったから、
拳銃での決闘を申し込む、というものであった。そして手紙の主の女は
町の銃器店で拳銃を買い、店主に使い方を習い、
翌日、女学生との決闘となる。お互いに銃の扱いに慣れていないから、
なかなか相手に当たらないのであるが、女の打った最後の弾が
女学生にあたって、彼女は死んでしまう。
女は狼狽して、警察に自首するが、監獄の中で
食事を拒否して、最後は餓死してしまう。そんな内容である。
女が拳銃の打ち方を習ったあとのせりふが生々しいのだが、
吉本氏は、作家が、「女は考えたが」と書いたその、
「女」を「私(作家自身)」にすり替えてもぜんぜんおかしくない、
それは作家自身が小説に忍び込んでいるから、というような
ことを言っている。そしてこの小説の崩し方として、作者が
ことの一部始終を見ていた、そこをつこうと太宰は思ったのだ。
つまり作者自身と作中人物があいまいである。作者はこの女房の
亭主自身として作中で一部始終を影から覗き見していたのである、と。
作者の潜在的な自分自身が表現の中、
フィクションである作品の中に紛れ込んでいる、だからこそ
生々しい描写になっているのだが、それが通俗的である
と太宰は思ったのである、という分析をしている。
オイゲンブルグという小説家はトマス・マンなどと同時代の
作家で、当時はドイツでもかなり有名だったらしい。しかしその後
忘れ去られる存在となったのは、先にのべたような通俗性が
古典となったトマス・マンの資質とをわけるポイントであったのだろう、という。
このような、主人公=作家が見えている小説は太宰に
不快感を与え、それが次第に原作者に対する不愉快さとなって、
太宰はこの小説を徹底的に書きなおし、通俗でない作品に
仕立て上げた根拠なのである、という論理展開は、
吉本隆明氏の話の下手さも気にならない程、痛快でなるほどとうなずく。
太宰がこの『女の決闘』を書いたのは昭和15年、
日中戦争のあと、昭和16年には大東亜戦争が勃発する、
その前年である。この頃、ドイツのオイゲンベルグは沈黙を保っていた。
太宰はオイゲンベルグをよく知らない、と言っているが、おそらく
鴎外の書いた雑誌の記事などで知っていたのだろう、だから沈黙する
オイゲンベルグに対して、戦争へのアンチテーゼとして
書いたのかもしれない、と吉本氏は言う。氏によれば
太宰が戦中に書いた作品は純文学としてどれも立派なものばかりである。
このあと吉本氏は森鴎外の作品についても語っている。
明治天皇崩御に続く乃木大将殉死の衝撃、そのころから
鴎外は『阿部一族』に始まる歴史小説、史伝小説を書くようになる。
いわゆる鴎外の晩年の根本をつらぬくモチーフである。
冷静に、記録とフィクションが紙一重で混在する小説であるが、
『灰燼』の節蔵がいうような公平無私、ではありえない。しかし
私感的でもない。
文学は、場面場面をどうつなげるかの表現に作者の潜在意識が
出てくる。たとえば『大塩平八郎』では暴圧や飢餓を冷静に描いているように
見えるが、文体分析すれば公平無私ではない。秩序に抗するものの
内心の不安、危惧、孤独、そういったものを跳ね返す遺志の強さ、
そこにみじめさを感ぜざるを得ない、冷静に書いたからこそ逆に
感じられるのだ。作中人物との距離の取り方、そこを読み取ることで
通俗小説と文学の違いがわかる、それは直感で感じられるものだ、
と吉本隆明氏は言って、講演を聞いている人たちに文体分析の
重要性を説くのである。
聴いていて、あっというまに2時間がたった。外はしらじらと明けて
結局ほとんど徹夜してしまったが、疲労感はまったくなく、
むしろ、たいへん知的な講義をきいたあとの、刺激を受けた脳の快感が
さわやかに感じられた。文学を読む、とはこういうことなのだろう。
直観から疑問がわき出てくる。それを推理や憶測によって分析していく。
下手に時代や政治への批判に流れることなく、作者の意図、潜在意識を
まさぐってジグソーパズルのように一つずつはめこんでいく知的作業である。
小林秀雄が、いい質問をすれば答えはすでに出たのと同じだ、と言っているが
まさにその通りであろう。
吉本隆明氏は難解である、という先入観からあまり読んだことがなかったが
講演では話し方に人格や品格が出る。きっと心やさしいおじさんだったのだろう、
という気がする。
太宰治の『女の決闘』は青空文庫に収録されているので
これも一気に読んでしまった。わたしはずっと太宰は毛嫌いしてきたが、
やはりこの人は天才じゃないか、と思うし、諧謔精神もユーモアのセンスも
そのうますぎるほどの文章からにじみ出ている。
やはり落語が好きだっただけあって、文章は目で追っていても
耳から音声として自然に入ってくるような流れがある。
太宰の『女の決闘』についての感想は、長くなるので、
ここでは書かない。
『ほぼ日刊イトイ新聞』のURLはこちら↓
http://www.1101.com/home.html
このページを開いて、スクロールダウンし、
なかほどの『吉本隆明の183講演』というボックスをクリックすると目次が出てきます。
音声のみの講演です。














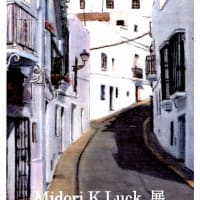





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます