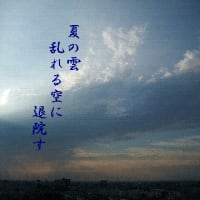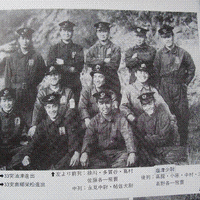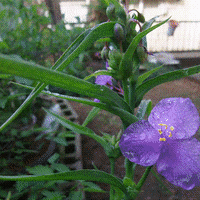冬型の気圧配置は西から緩む。 

「氷面鏡」(ひもかがみ)
木漏れ日を崩して写す氷面鏡
(こもれびを くずしてうつす ひもかがみ)

氷面鏡
「氷面鏡」(ひもかがみ)とは凍った氷の表面が鏡のように
平らで光っている状態をいいます。

木漏れ日
氷は、ご存知の通り、水が氷点下以下で固体に凝結したものを
言います。暖冬で暖かい年とは言われていますが、流石に
寒の入りと同時に寒さも増し、沼の表面も凍りました。

大きい沼なのでは、穴釣りと称して、暖炉を抱き公魚(わかさぎ)
釣りなどを好む人もいます。
また北のオホーツク海などからの流氷が港を埋め尽くす風景
にも接します。矢張り、氷の風物詩は雪と共に冬には欠かせない
最高のものです。

読売・編集手帳・1・9より
1月9日の晩、町の人々は家の前に飾った門松を上下が逆になるように付け替えた。恵比須さまが馬に乗って町をお通りになるとき、馬が松の葉で目を傷つけないようにと教えられた
◆作詞家の岩村時子さんが随筆集「愛と哀しみのルフラン」(講談社)のなかで、兵庫県西宮市で過した少女時代を回想している。子供たちには「二度目のお正月が来たような楽しい日」であったという
◆きょうは「宵戎」、あすは「十日戎」(本戎)、11日は「残り福」(残り戎)と、祭礼がつづく。恵比須さまにゆかりの神社は、福笹を手にした人でにぎわうことだろう
◆昭和40年代前半の「いざなぎ景気」を抜き、実感の伴わないまま戦後最長の景気拡大がつづいている。大判小判の飾り物をつけた福笹を手に取るたび。「本物ならば、ね」とつぶやくのが常だが、家計を置いてけぼりの最長景気にも同じ言葉が浮かばぬでもない
◆恵比須さまはイザナギ、イザナミ二神の子ともいわれる。高度成長期の名前をとどめたお父さん並とはいかずとも、賃金で、雇用で、かつての心浮き立つ好況感を味わってみたいというのが、詣でる人々に共通する願いだろう
◆山口青邨に「福笹をかつげば肩に小判かな」という句があった。小判殿、肩先なんぞと遠慮なさらず、どうぞ懐の奥へお上がりください。