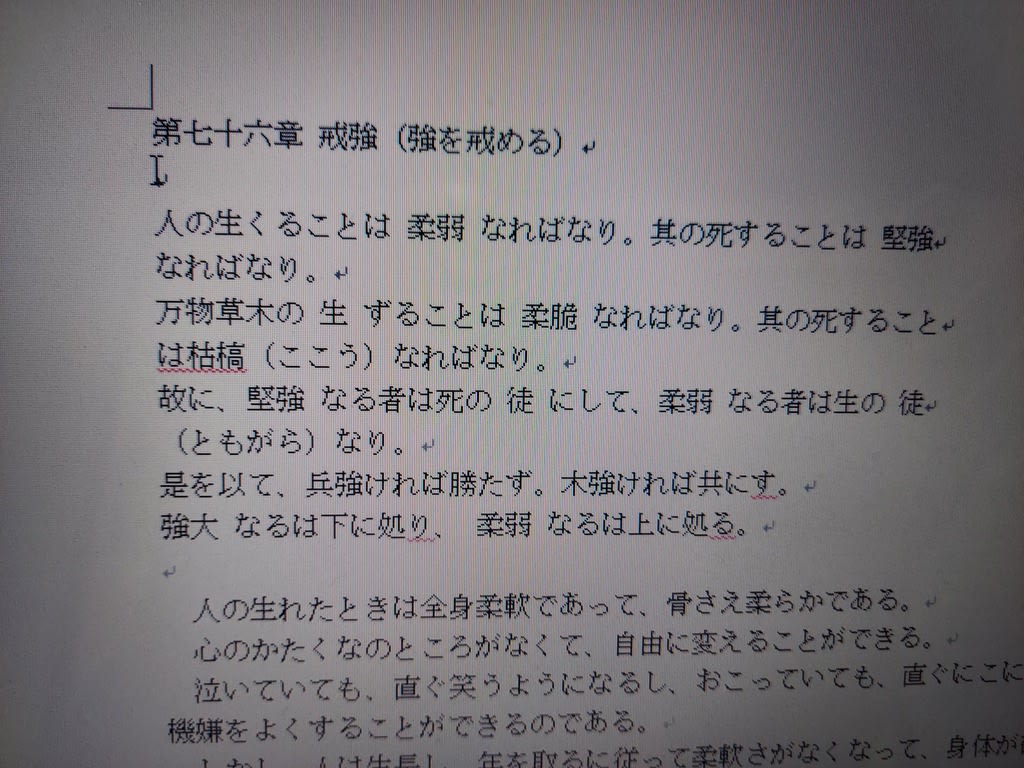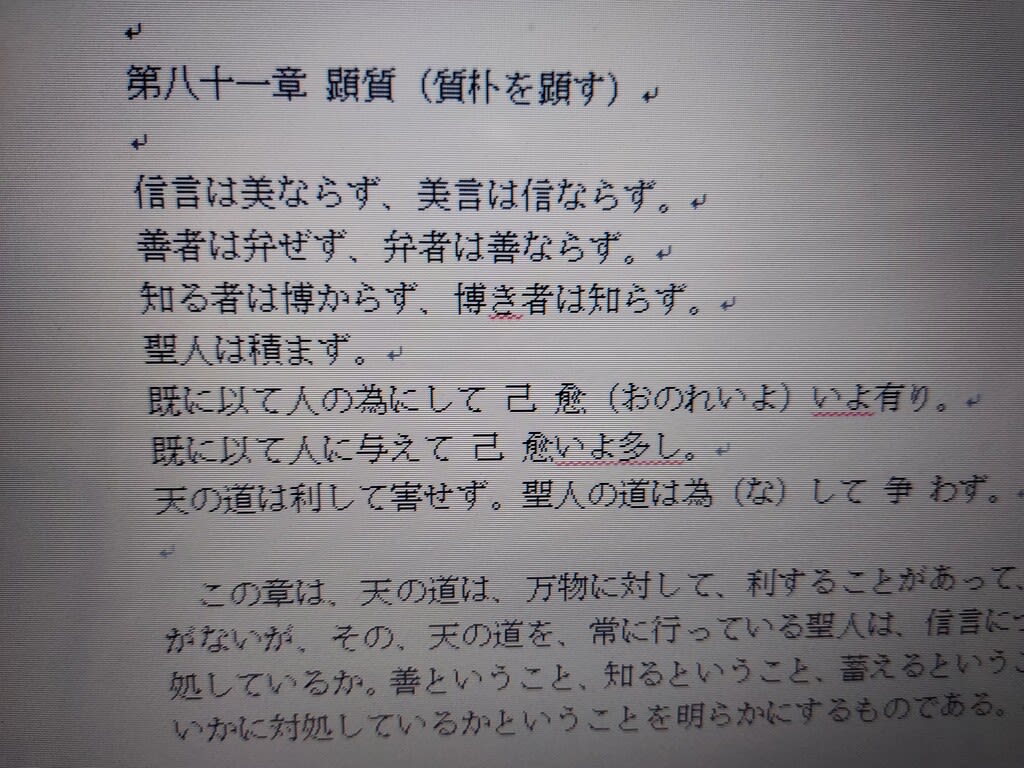
第八十一章 顕質(質朴を顕す)
信言は美ならず、美言は信ならず。
善者は弁ぜず、弁者は善ならず。
知る者は博からず、博き者は知らず。
聖人は積まず。
既に以て人の為にして 己 愈(おのれいよ)いよ有り。
既に以て人に与えて 己 愈いよ多し。
天の道は利して害せず。聖人の道は為(な)して 争 わず。
この章は、天の道は、万物に対して、利することがあって、損を与えることがないが、その、天の道を、常に行っている聖人は、信言については如何に対処しているか。善ということ、知るということ、蓄えるということについては、いかに対処しているかということを明らかにするものである。
老子八十一章を通じて、道について説いている言葉は、老子が、信言としているところであるが、世人の憧れるような、美言をもって述べることはできなかった。
また、道を行う善人は、世人の憧れるような活動をしているようには、弁ずることができなかった。また、真にものごとを知っているということは、華やかに見える博識のようには説くことができなかったことを、
信言は美ならず
と言ったのである。
美言は、聴く人の意を迎えるように、或は、感情を損なうことのないようにと、修飾せられた言葉であるから、それだけ信実とは違ったところがある訳である。
真にものごとをよく知っているものは、博くものを知っているものではないのである。博くものを知っている、という者は、外見のための物識りである場合が多いので、深く事理を極めているというわけではないから、信念というものがないのである。従って、知っているだけである博識は、よくものごとを知るものとは言えないのである。
天の道は、万物を養い育てるというところにあるのである。万物は、自然から限りなき恵みを受けて生れ、成長し、繁殖し、祖先から受けたものは、その子孫に受けつがせているのである。これは、万物が自然の恵みを充分に利用できる機能を備えているからである。
聖人が平等を尊ぶのは、人は、お互いが平均した力をもち、平等の立場にあるようにするのが、争いの心を生ぜしめないためには、最もよいことだと考えたからである。
人を、道から遠ざけているものは、争いの心である。
もし、争いの心が無くなれば、その人は、怒る心も、人を侮る心も、人を憎む心も、人を恨む心も、悲しみも、一切を忘れたようになって、心の平静を保つことができるようになるばかりでなく、何がなくても満ち足りた、豊かな心になれるのである。
老子の書に、一貫して述べられていることは、人の心から、争いの心を無くすことである。以上のような訳で、
聖人の道は為して 争 わず。
の言葉をもって、老子の全文の、結びの言葉にしたことと考えられるのである。
・『老子』<万物平等の人生論>瀬尾信蔵著より紹介しましたが、老子八十一章、いかがでしたか。長いお付き合いありがとうございました。
道を求めて、道に従って生きるということ。これは、きょうを生きるということであり、改めて、次のようになれたらなと思うわたしです・・・・。
人が、苦しむようなことがあるのも、
迷うようなことがあるのも、
悲しむようなこともあるのも、
争う心が起こっているのである。
もし、争いの心が無くなれば、
その人は、怒る心も、人を侮る心も、
人を憎む心も、人を怨む心も、
悲しみも、一切を忘れたようになって、
心の平静を保つことができるようになるばかりでなく、
何がなくても満ち足りた、
豊かな心になれるのである。