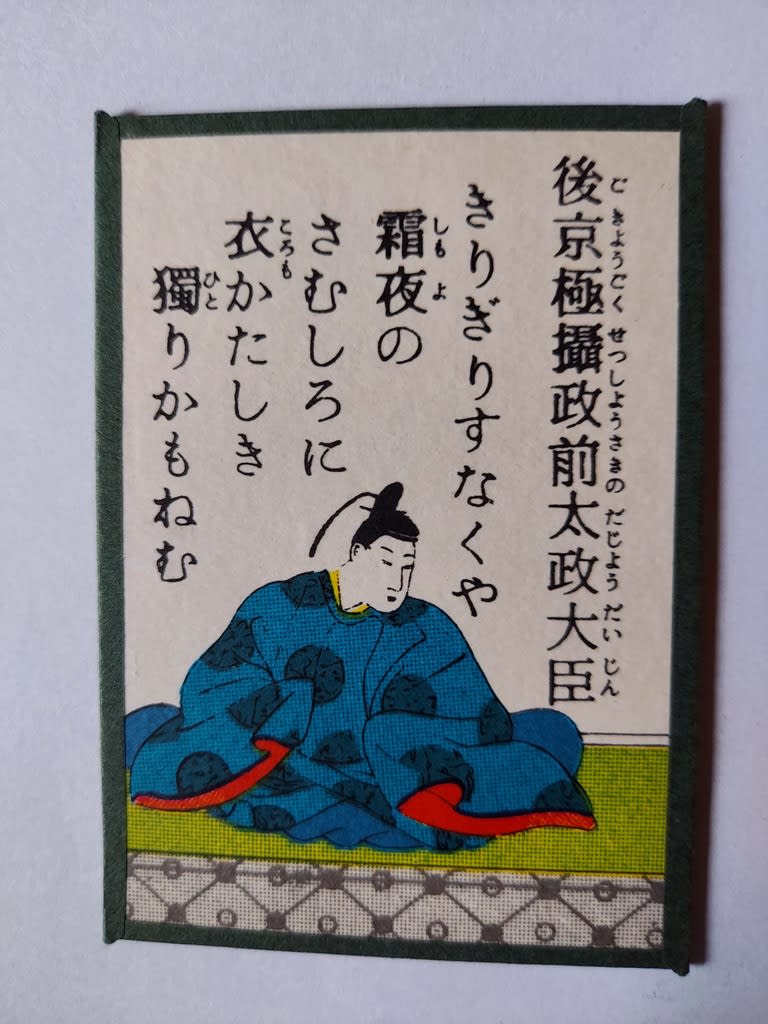第百首

百敷や ふるき軒端の しのぶにも
なほあまりある 昔なりけり
順徳院
(1197-1242) 後鳥羽天皇の皇子。藤原定家に和歌を学ぶ。承久の乱で敗れ、配流地の佐渡で没した。
部位 雑 出典 続後撰集
主題
栄えていた昔の御代を懐かしみ朝廷の衰微を嘆く心
歌意
宮中よ、時代を経て古びてしまった建物の軒の端に、しのぶ草が生い茂っている。それを見るにつけ、朝廷が栄えた昔のよき時代がしのばれて懐かしく思われることだ。
古くは、「ももしきの」で「大宮」の枕詞。「忍ぶ」と「忍草」とをかける。
宮中の、古く荒れた軒端には、忍ぶ草が生えているが、その忍ぶ草を見るにつけても、いくら忍んでも忍びきれない昔の御代であることよ。
『続後撰集』雑下、一二〇二に「だいしらず 順徳院御製」として見える。巻頭に天智天と持統天皇の御製二首をおき、巻末に御鳥羽院と順徳院のこれまた御製二首を据えたのは、やはり相照応しているものと見なければならない。
『百人一首』がはじめは色紙の形であって、定家自筆の色紙の残存から、すくなくとも撰歌までは定家と考えられるのに対して、それを成書し配列し、まとめるまでの段階は、確実には知るすべもないが、『百人秀歌』から『百人一首』への過程の間に、やがて配列にも意を用いていることは察せられよう。
後鳥羽院の期待を受け即位したが、討幕を計って承久の変に敗れ、佐渡に遷御。『続後撰集』以下に百五十四首入集。
・『百人一首』の紹介でしたが、長いお付き合いありがとうございました。
どれだけそれぞれの思いに近づけたか心もとないのですが、日本には、和歌という古典詩があったということ。そして、短歌は、俳句とともに日本人の心を表現する一篇の詩として、いつまでも愛され続けていくのでしょう。
私は短歌、俳句と作ったことはありません。自由詩というか、散文詩というか、若かりし頃、浮かんでくるおもいを詩にしていました。いつからか、醒めてしまったというか、詩を書くということから遠ざかっています。
こうして、初めて『百人一首』を読んだのですが、千年も前の平安時代の人、この令和の人、人としての思いは相通ずるのですね。これからも、その人としての思いを大切にして、平凡な日々を過ごしていけたらなと・・・・。