4
<しのぶの里>
明くれば、しのぶもぢ摺の石を尋ねて、忍の里に行く。遙か山陰の小里に石なかば土に埋れてあり。里のわらべの来たりて教へける。「昔はこの山の上に侍りしを、往来の人の麦草をあらして、この石を試みはべるをにくみて、この谷につき落せば、石の面、下ざまにふしたり」といふ。さもあるべき事にや。
早苗とる手もとや昔しのぶ摺り

・今、稲の苗取りをしている娘たちの手つきを見ていると、昔、衣にしのぶ摺りをしたときの手つきがしのばれて、なんともなつかしい。
<佐藤庄司が旧跡>
月の輪の渡しを越えて、瀬の上(福島市)といふ宿に出づ。佐藤庄司が旧跡は、左の山ぎは一里半ばかりにあり。飯塚の里鯖野と聞きて尋ねたずね行くに、丸山といふに尋ねあたる。これ、庄司か旧館なり。麓に大手の跡など、人の教ふるに任せて涙を落し、またかたはらの古寺に一家の石碑を残す。中にも二人の嫁がしるし、まづあはれなり。女なれどもかひがひしき名の世に聞こへつるものかなと、袂をぬらしぬ。堕涙の石碑も遠きにあらず。寺に入て茶を乞へば、ここに義経の太刀・弁慶が笈(おひ)をとどめて什物(じふもつ)とす。
笈(おひ)も太刀も五月にかざれ紙幟(かみのぼり)
・なお、芭蕉が実際に目にしたのは、義経の笈と弁慶の書写したお経だった。あえて、義経の太刀、弁慶の笈と虚構したのは、それぞれにふさわしいイメージを作ろうとしたためだとされる。
<飯塚>
其夜飯塚にとまる。溫泉あれば湯に入て宿をかるに、土座に莚を敷て、あやしき貧家なり。灯もなければ、ゐろりの火かげに寢所をまうけて臥す。夜に入て、雷鳴り雨しきりに降りて、臥せる上よりもり、蚤・蚊にせせられて眠らず。持病さへおこりて、消入ばかりになん。短夜の空もやうやう明くれば、また旅立ぬ。猶夜のなごり。心進まず。馬をかりて桑折の駅に出る。遙なる行末をかかへて、かかる病ひおぼつかなしといへど、羇旅邊土の行脚、捨身無常の観念、道路に死なん、これ天命なりと、気力いささかとり直し、路縦横にふんで、伊達の大木戶を越す。
<笠島>
鐙摺(あぶみずり)、白石の城を過ぎ、笠島の郡に入れば、藤中将実方の塚はいづくのほどならんと、人にとへば、「これよりはるか右に見ゆる山ぎはの里を、みのは・笠島といひ、道祖神の社、かたみの薄今にあり」と教ふ。このごろの五月雨に道いとあしく、身つかれ侍れば、よそながら眺めやりて過ぐるに、蓑輪・笠島もさみだれの折にふれたりと、
笠島はいづこ五月のぬかり道
岩沼にやどる。
・五月雨の泥道に邪魔されて、見損なった実方の遺跡に、「笠島はいづこ」と呼びかけて、遠くから思いを馳せている。あこがれと無念さがにじむ句である。
<武隈の松>
武隈の松にこそ、目さむる心地すれ。根は土際より二木にわかれて、昔の姿うしなはずとしらる。まづ能因法師思ひ出づ。往昔、陸奧守にて下りし人、この木を伐りて名取川の橋杭にせられたることなどあればにや、「松は此たび跡もなし」とは詠みたり。代々、あるは伐り、あるひは植え継ぎなどせしと聞くに、今はた千歲のかたちととのほひて、めでたき松のけしきになんはべりし。
「武隈の松みや申せ遅桜」と、挙白というものの餞別したりければ、
桜より松は二木を三月越し
・有名な歌枕、武隈の松が昔の姿を保持していることに大感激している。能因
の古歌や挙白の句を引いて、その喜びを俳味豊に表現した。
挙白の句に応えるかたちで、武隈の松を見ることができた喜びを表現した。「二木」「三月」には数詞を並べ、「松」に「待つ」意を、「三月」に「見つ」の意を掛けて、技巧を凝らした。
・次回に続く・・・・。













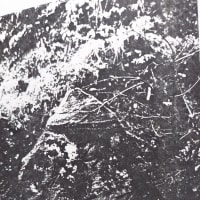






福島県にしのぷいう地があるのですね。
力士の若隆景たち三兄弟は福島県出身。
お父様が「わかしのぶ」の四股名で相撲をとっていました。
字は若信夫です。
義経の太刀・弁慶が笈のエピソードも知れて、嬉しいです。
また続きを楽しみにしております。